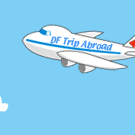2017年2月6日 更新
| ⇒ 情報ページへ | ||
| 通算回数 | テーマ / イベント名 | 実施日 |
|---|---|---|
| 第60回 | 「モンゴル・大平原の文化と景観」櫻井三紀夫氏 「スペイン・アンダルシア紀行」山口正道氏 |
11月24日(火) |
| 第59回 | 「マルタ共和国滞在旅行」今井智之氏 |
9月28日(月) |
| 第58回 | 「パリからの小旅行」濱本龍彦氏 「多様性と神秘の国インドネシア」寺尾勝汎氏 |
7月22日(月) |
| 情報 | 長期間滞在してみたい海外の観光地「マルタ共和国 」 |
7月15日(掲載) |
| 第57回 | 「ルツェルン撮影日誌」曽山高光氏 「米国西部の国立公園を巡る」濱本龍彦氏 |
5月18日(月) |
| 情報 | 海外旅行研究会「発足当時の思い出 」 |
4月15日(掲載) |
| 第56回 | 「最後の楽園―ミャンマー紀行」萩原秀留氏 「南フランスの小さな美術館を訪ねて」戸田邦男氏 |
3月30日(月) |
| 第55回 | 「夏のコッツウォルズのんびりドライブの旅」保坂洋氏 「中世の風の中で〜ベネチア・トスカーナ紀行」井上史男氏 |
2月9日(月) |
■ 第60回「海外旅行研究会」
第60回例会が平成27年11月24日丸の内倶楽部21号館で開催されました。60回記念事業ということで出席者は会場満席の20名に及びました。先ずは前回からのキャリーオーバーで櫻井三紀夫氏の「モンゴル・大平原の文化と景観」が発表され、次に記念イベントとして外部講師である山口正道氏による「スペイン・アンダルシア紀行」がプレゼントされました。
櫻井氏は、モンゴルの歴史、文化、宗教、芸術、建築そして食と花々について詳しく紹介し、同国観光資源の素晴らしさをよく訴えていました。
| 発表に聞き入るメンバー達 | 60回記念を乾杯! | 一同かしこまって集合写真 | 反対方向から集合写真 |
自ら写真教室を開くほどの写真家でもある旅行家、山口氏は昨年アンダルシア地方を再訪し、過去10年間に変わったもの、変わらぬものを見定めつつ、マドリッドからトレドを訪ねてから南下し、セビリヤ、ロンダ等の白い村を通過、マラガやアルハンブラ等も訪ねるという旅でした。数多くの美しい写真には皆感銘を受けました。因みに同氏のブログ4travel.jp/traveler/seidou/albumを開くと数多くの紀行文と写真を見ることができます。
以下は、両氏からの報告概要ですが、紙面の都合で極く限られた写真のみ掲載しました。
 「モンゴル・大平原の文化と景観」櫻井三紀夫氏
「モンゴル・大平原の文化と景観」櫻井三紀夫氏
私達夫婦の海外旅行は、訪ねた先々でできるだけたくさんの名所、旧跡、世界遺産を観て回り、過去にその場所で主人公が観たであろう光景、感じたであろう印象を自分達も味わってみる、という楽しみ方をしています。今回のテーマは、遠い過去に大帝国であった大平原の内陸国モンゴルが、今どういう国になっているかを見る視点で訪問しました。
ウランバートルの中央広場 |
国会議事堂 |
モンゴルは、国土156.6万Km2(日本の4.2倍)、人口287万人(日本の2%)、人口密度2人/Km2の、文字通り大平原の国。1206年、チンギスハーンにより大モンゴル帝国が建設され、世界史上最大の領土を持つ国家となりました。元の滅亡後は、ハーンの末裔が統治するいくつかの小国として存続し、16世紀には、チベット仏教を取り入れて、ダライラマを任命する役割を開始しました。1911年清国・辛亥革命の結果、モンゴル国として独立、1924年ソ連の影響下で人民共和国になり、1992年ソ連の崩壊により、民主化憲法・議会制民主主義共和国へと移行しました。宗教は引続きチベット仏教が信仰されており、各地に寺院が建設されています。国民の多くは草原で遊牧生活を送っています。清の辛亥革命後に成立したモンゴル国の国王には、ボグドという「生き神様」と信じられていた人物がボグドハーン8世として就任しました。そのボグドハーンの宮殿がきれいに保存されて公開されていました。
国会議事堂にあるチンギスハーン像 |
ガンダン寺本堂 |
ボグドハーン宮殿 奥の院 |
芸 ‥ なんという柔軟さ! |
モンゴルの文化としては、ホーミー*という低音と高音を同時に発声する歌唱法や、馬頭琴という二弦琴の音楽、曲芸などを鑑賞しました。一方、大モンゴル帝国そのものの歴史遺産は殆ど残っておらず、カラコルム(第2代オゴディハーン建設の首都)やアウラガ(チンギスハーンの最大拠点)も、荒廃したままでした。カラコルムは、16世紀にエルニデ・ゾー寺院建設のために資材として使われ、町の建物が消滅しました。アウラガは、大きなゲルの宮殿であったため遺跡として残っていないようで、現在も調査が進められています(日・モンゴル共同発掘)。
モンゴルは寒冷地のため、日本の高山植物に類似した花々が咲いていました。
大平原にゲルの集落 |
草原を乗馬で満喫 |
今回の旅行では、マルセル・プルースト(フランス・作家)の "旅行による新しい発見は、新しい景色ではなく、新しい視点である" という言葉を実感するということも目的の一つにしました。その意味で、モンゴルという国を見る際に、"国の外から"だけではなく、"国の中に入って、中から見る"という新しい視点が得られたと感じます。そういう目で見てみると、モンゴルのこれからの社会進展の見通しとしては、
- 大都市集中vs放牧民生活……ウランバートル近郊にゲルが集中、スラム化
- 資本主義化vs自給自足――経済成長率=約6%……格差社会の拡大
- 日本との関係――資源、観光、相撲などをどのようにバランスしていくか?
などが課題と考えられます。トータルの印象としては、 - 大帝国時代の痕跡はほとんど感じられない。
- 一方、人々の心は、「チンギスハーンという誇り」を抱いている。
ということを感じました。
(*編集註:ホーミーと馬頭琴は2015年11月の「DF講演・交流会」の折に演奏されました。こちらからご覧ください)
 「スペイン・アンダルシア紀行」山口正道氏
「スペイン・アンダルシア紀行」山口正道氏
情熱の国の最もスペインらしさを体感できるアンダルシア地方は、他のヨーロッパ諸国と違ってキリスト教文化とイスラム文化とが融合したエキゾチックな魅力が溢れているからだと言われる。その魅力をこの地域の都市や村で見出し、撮影描写することを目標にして、82歳の老体を顧みず、6月の暑い時期を選んだのは、アンダルシアの見渡す限りの広大なひまわり畑の中に立って夏の太陽の下で輝くひまわりの花を心ゆくまで撮ることと、時宜しく新国王の戴冠パレードに出会える楽しみがあったことも付言しておきたい。
1. 新国王フェリペ6世の就任式典とパレード
| 1.新国王フェリペ6世 |
国王フアン・カルロス1世が、2014年6月19日退位し、長男のフェリペ6世が同日即位ということで、その祝賀パレードがメインロードのグランビア大通りで華やかに行われた。新国王は皇太子時代から国民に親しまれ、即位が待ち焦がれるほどの人気だったので、パレードを見る群衆の熱気は大変なものだった。筆者が撮ったパレード画像をカメラモニタでチェックしている後ろから、会場に行けなかった人たちが覗きこんで、それを各自の携帯でコピーさせてくれと言い出すくらい人気が高い証(あかし)を感ずるのであった(写真1.)。
2.トレド
トレド旧市街地は、町全体が中世そのままの姿で変えることなく保存されて、世界遺産の街となったため、以前は町中に乗り入れたバスはすべて城壁外の駐車場止り。ただ観光客用に旧市街へ上る6層の長いエスカレーターが設置されたのがここ10年の変化である。
3.コルドバ
| 2.コルドバのメスキータ |
コルドバの街は元イスラム寺院のメスキータ観光でもっているようなもの。メスキータ内部はイスラム人が退去させられてから、イスラムの礼拝堂を東端に残したまま、キリスト教徒が堂内のど真ん中に教会を作ったので二つの宗教が併存するという珍しい聖堂構成になっている。圧巻は「柱とアーチの森」と称される内部の景観である(写真2.)礼拝堂の高い天井を支える柱が856本碁盤の目に並び、これに赤レンガと白石灰岩を組み込んだ二重アーチが架かる構造で、イスラム建築の合理性と装飾の視覚的効果に優れたものが残っている。このようにイスラム文化のいいところは保存し、技術を摂りいれていくという柔軟性をアンダルシアのキリスト教徒は持っていた。イスラム教徒たちがコルドバの町に残したものは寺院だけではない。迷路のように入り組んだ白壁の家並も、それを飾る花いっぱいのパティオと呼ばれる中庭も彼らから受け継いだ。なかでもパティオつくりはコルドバの人々の自慢で、頼めば愛想よく見せてくれる。
4.広大なひまわり畑
| 3.コルドバ郊外の向日葵畑にて |
コルドバの市街を抜け、セビリアに向かって高速道路をひた走ると、両側に起伏のある広大な丘に向日葵畑が現れる。さんさんと輝く太陽と青い空。その下にどこまでも広がるヒマワリ畑は、見渡す限りの丘一面を黄色一色に染め上げる。遠くの丘から吹くアンダルシアのそよ風にのって、ひまわりの黄色の波動が寄せたり返したりするのが実に美しいが揺れを止めて大輪の向日葵を撮影するには根気がいる。それがこの1枚(写真3.)
5.セビリアにて
| 4.セビリア 美術館前広場 |
セビリアで聖体祭が見られた。大聖堂は別として、町中の主な教会では、聖体顕示台を担ぎ出して、行列を組んで教区内の街中を行進する。アンダルシア特有の暑い日射しの中、祭礼服に身を包んだ神父や聖歌隊の少年たちが汗をかきながら行列し、マリア像を乗せた神輿は、かぐわしい香が焚かれ、見物の観光客にも香が振り掛けられる。やがて出発した行列は、日本の神輿のように大きく揺らすことなく、普段は情熱的なアンダルシア人でも、静かに讃美歌を歌い敬虔な眼差しで進む。親しみ深く分かりやすい聖体祭だった(写真4.)セビリアも旧イスラムの建物そのものやイスラムの様式が巧みに取り入れられた建物が多い。大聖堂鐘楼しかり、アルカーサルしかりである。ピラト-邸では、ムハデル様式パティオで三連アーチや装飾タイル壁が素晴らしい。セビリアのフラメンコも闘牛も良いが、ツアーでは行かないピラトー邸もお薦めの一つである。
6.山間の小さな美しい村や町を訪れる
| 5.白い村フリヒリアナ |
内陸のセビリアから山地を越えて地中海側のマラガへ南下する道筋に、アンダルシア特有の白い家の小さな群落からなる村や町がいくつも見られる。遠目ではどれも同じように見えるが、起伏の多いアンダルシアの地形・地質・気候を利用した種々の形体がある。それらの成因や由来(移動入植)について、一般的に①気候的要因酷暑からの避暑地②宗教的または政治的要因で、レコンキスタによるイスラム教徒(ムデハル)系人民の逃避地が挙げられているが、私はそれら成因を踏まえてかつ地形・地質的条件から集落形成の形体を下記の3つに分けて考え、そのいくつかを今回訪れた。これらは成立形態の違いがあっても、現在では観光地化して変化発展したものと、依然として静かな住居地を保つものがあるのを見たのは興味深かった。即ち、
①特異な岩盤、洞窟利用して出来た集落(最も原始的で簡素な建物クエバ住居)セテニール
②断崖の上に建つ集落(敵から攻められにくい地形)ロンダ、アルコス・デ・ラ・フロンテーラ
③山の中腹に建つ集落(中新統堆積岩で地盤工事がしやすい)ミハス、フリヒリアナ、カサレス(写真5.)、である。
7.地中海沿岸部コスタデルソルとその中心マラガにて
地中海沿岸部は対岸のアラブと近く相互の交流の伝統があった。フェニキヤ人によって建設され、ローマの重要な植民地となり、アラビア人の統治下ではグラナダ王国の港だったが、今でも立派な港湾設備が整った国際港の顔も持っている。大戦後のヨーロッパの観光ブームの影響で、寒村に過ぎなかった沿岸地域が、年間を通じて温暖な気候からリゾート地帯として開発されてきた。30年前までは瀟洒な低層ビラが多い海浜リゾート地だったが、10年ごとに行って見るとその変化は大きく、今や高層ビルが林立する近代都市に変貌した。多くの観光客を受け入れて観光産業が発展。増えた労働者のベッドタウンが山腹の白い村へ流入しているようである。
8.グラナダにて
| 6.グラナダアルハンブラ宮殿 |
グラナダではイスラム文化の洗練と爛熟の極みと言われたアルハンブラ宮殿が観光第一の目玉。レコンキスタの最後の防戦城塞であったが、無装飾な外観に比して内部はムカルナスなど当時の最高の技術を投入した豪華な装飾で埋め尽くされた。素晴らしい技能集団が存在していた証拠である。この装飾デザインが後世のスペイン芸術作品に与えた影響は大きい。宮殿内には様々な部屋があり、それぞれの壁、柱、天井に至るまで精緻を極めたアラベスク紋様の彫刻やタイル舗装が施されている。そのすべてを解説する時間がないが、その中でも私の好きな部屋がリンダラハのバルコニー(写真6.)である。壁面全体に繊細なアラベスク模様が施され、大きなアーチ型の窓から光がさしこみ、庭園の緑も映えて、暗い部屋が多い宮殿の中では、ここは開放的で非常に明るい印象を受ける。最後に宮殿対岸のアルバイシン地区から暮れなずむ宮殿の夕景を眺望して別れを告げた。
9.撮影後記
10年間の変化は、撮影者側でも起こっていた。デジタルカメラ機能の急速な進化で、フィルム時代に撮れなかったことが可能になったことである。暗いメスキータの中でも肉眼以上に明瞭な静止画像が得られ、手持ちで撮ったアルハンブラ宮殿の精緻な装飾レリーフは、パソコンモニタで拡大すると鑿跡などのテクスチャーが顕微鏡的視野で観察出来て、新しい発見に驚かされた。今後のIT技術の発展で古い10〜15世紀のイスラム技能者の伝えた文化財の正確な伝承や保存も、またそれ以上の技法開発が可能となるだろう。それを思うと、もう少し長生きして更に軽快・精密なカメラ持参で再訪・再発見の喜びを享受したいと願う次第である。
恒例の懇親会には、先ず常信伊佐夫氏によるご挨拶と音頭でスペイン産スパークリング・ワイン、ガヴァでの乾杯で始まりました。尚、サプライズに同氏より記念としてボルドーワイン1本が今井世話役に贈呈されました。限られた時間内にも20名全員によるテーブルスピーチが会に花を咲かせました。次回は、新年1月開催で、四方満氏の「ドイツ旅行(仮称)」が決まり、戸田邦男氏の「サンクトペテルブルグ(仮称)」または角谷光弘氏フランス・ワイン(仮称)」旅行のプレゼンを予定しています。。
今井智之記
■ 第59回 「海外旅行研究会」
第59回例会が平成27年9月28日(月)に丸の内倶楽部21号館で開催されました。この日は、ディレクトフォースの他のイベントと重なり、また秋の海外旅行に出掛ける方もいて欠席者が多かったのですが、ゲスト3名を迎えて総勢13名での例会となりました。ゲストの内、写真家でもある建築家の山口正道氏には外部講師としてプレゼンをお願いすべく、その環境を知って頂くためにお招きしました。他には、英国人J.サンリー氏と日本人である奥様で、おふたりは今年のクリスマスにマルタ島に行かれるのでこの日のプレゼンを是非とも視聴したいということでした。同氏は、30年前に初来日し、京都で日本文化に深く感銘し以来日本に在住しています。
プレゼンには、先ず櫻井三紀夫氏の「モンゴル・大平原の文化と景観」が予定されておりましたが、前代未聞のハプニングで延期せざるをえませんでした。同氏が、パワーポイントの資料をダウンロードしたところ、文字は出ましたが画像が全く出なかったのです。会場の責任者が種々手を尽くしましたが、甲斐なく40分経過、そこで世話役の資料をダウンロードしたところ、全く同じ結果でした。
最初は、資料とパソコンのバージョン違いが理由とのことでしたが、実はパソコンの故障が原因でしたから、責任者が別のパソコンを用意し、ようやく開始可能となりました。時間の制約もあり、プレゼンはサンリー夫妻のご期待に副うべく世話役の「マルタ共和国滞在旅行」のみとしました。櫻井氏に大変申し訳なく、次回は万全を期すよう心掛けることにしました。以下は、報告概要です。
 「マルタ共和国滞在旅行」今井智之氏
「マルタ共和国滞在旅行」今井智之氏
既にDFホームページ、同好会、海外旅行研究会の情報欄に掲載した「仮想旅行」に続き、数多い美しい画像とともに詳しく報告し、表題に示した通り「こんな旅をしてみませんか」という狙いがあった。マルタは地中海気候に恵まれた小さな国(淡路島の半分)でありながら、地中海のへそと言われるように、歴史的に交通上重要な戦略地点であり、多くの民族の文化が行き交い、歴史的エピソードや遺跡を残して魅力ある観光資源をもっている。
5-4千年BCに石器時代と巨石文化にはじまり、フェニキア、カルタゴ、ローマ、イスラム、ノルマン、スペインが支配したあと聖ヨハネ(後マルタ)騎士団が島を守り、オスマンの侵略を防ぎ、後、ナポレオン侵略後、最終的にはイギリスが支配し、第2次大戦で重要な基地であった。1964年に独立し、英連邦の一員であり、EUにも加盟している。
首都ヴァレッタは市全体が世界遺産であり、美しいふたつの港を見下ろし、騎士団が遺した多くの建物がある。なかでも聖ヨハネ准司教座聖堂は大変美しい。美術館となっている小礼拝堂にはカラバッジョの「洗礼者ヨハネの斬首」があるが見逃せない。マルタ島内陸には、美しい古都イムディーナと聖パウロのカタコンベで有名なラバトがある。
北島であるゴゾは、自然景観の他、マルタ島同様巨石神殿もあり、地産のワインも素晴らしいことから優れた観光地である。主都ビクトリアは、海賊の襲撃から逃れるために建てられた要塞、チタデルのラバト(郊外都市)である。島の見所のひとつはアズールウインドウで数千年に亘って風と波に浸食された天然のアーチであり、海水浴とシーフードを楽しめるのは、マルサルホルンである。ゴゾ島の、自然が潮を噴き上げ乾燥させてつくる塩田の風景は撮影ポイントとして興味深い。
三番目の島は小さなコミノ島で人口僅か4人、海と遊べる絶景の島であり、映画「トロイ」「モンテ・クリスト伯」そして「スエプト・アウエイ」のロケ地であった。
マルタ共和国には宿泊地として、贅沢なホテル並みのB&Bから、ホテルも5星から庶民的なものへと数多くあり選択に悩まされそうだ。美しい部屋やロビーのインテリアに加え、絶景の見える部屋とレストランのテラスとスイミングプールは保養に最適である。
食事も、伝統的マルタ料理の他、イタリアンや地中海料理と豊富であり、イギリス式パブでの食事も楽しめる。屋台で焼きたてのティンパーナ(挽肉とマカロニのパイ)で軽食とするのも粋である。
余暇の過ごし方に事欠かない。マルタはダイバーのパラダイスであり、1888年創立のローヤル・マルタ・ゴルフ・クラブではレッスンも受けられる。乗馬も初心者から歓迎されている。外国語学校へ通い多国籍のお友達をつくるのも一興であろう。
交通の便は大変よい。なかでもバスによる交通ルートは発達しており効率よさそうである。
最後に治安であるが、マルタもアフリカに近く例外なくアフリカの難民が漂着しているが、その多くは通過して他のEU諸国に移動しているので特に問題ないようである。
(仮想旅行記であるから自前の写真はありません。マルタ観光局からご許可頂いた画像はホームページの情報欄にてご覧ください)
懇親会は、恒例の全員参加のテーブルスピーチに加え、ゲストを交えての、期せずして国際交流の場と化し、普段より盛り上りましたから、ハプニングの後遺症は治癒されました。次回は、11月24日(火)同時刻、同会場で開催されます。前記櫻井三紀夫氏のプレゼンに続き、山口正道氏が氏のスペイン旅行に関して美しい写真と共に楽しいお話をしてくださいます。写真同好会メンバーの方々には特に興味深いものと期待しています。
平成27年10月5日 今井智之記
■ 第58回 「海外旅行研究会」
平成27年7月22日(水)の定刻5時より海外旅行研究会が丸の内「倶楽部21号館」で開催されました。
プレゼンのトップは濱本龍彦氏で、前回の「アメリカ西部の国立公園を巡る」研究報告に引き続いて、今回は欧州に移り、「パリからの小旅行」の発表でした。パリのホテルに滞在して、パリから60キロにあるバルビゾン村、ロワール地方、シャンパーニュ地方など日帰りでの探訪に加えて宿泊を伴うスペインのトレド、マドリッドまで足を伸ばし、それぞれの拠点に関わる歴史や絵画にまつわる秘話など豊富なコメントに触れながら数々の映像のご披露をされました。
引き続いて寺尾勝汎氏からは、「多様性と神秘の国インドネシアかけある記」と題してジャカルタを起点にスラウェシ、バリ、ジョクジャカルタを回ってジャカルタに戻る10日間の旅についての報告でした。ASEANで最大人口2、4億人を擁し、イスラム教徒が87%を占める同国は広範な領土と数百の民族、言語が混在し、タナトラジャにある桃源郷やバリのキンタマーニ地区の自然景観などに加えて、統治者の変遷による宗教や土着の風俗の融合が歴史遺産にも見受けられる現況の様子などを映し出して戴きました。
両氏からの報告概要は以下の通りです。
 「パリからの小旅行」濱本龍彦氏
「パリからの小旅行」濱本龍彦氏
周遊旅行でなく「拠点に滞在、拠点からのあちこち小旅行」という旅のスタイルをとり、今回は、パリの街歩きを楽しむとともに、パリを拠点にその近郊を美術、歴史、建築物、ワイン(今回はシャンパーニュ)に焦点をあてながら次の地に小旅行をした。
- バルビゾン村
- フォンテンブロー城
- ロワール河岸のシュノンソー城、クロ・リュセの館
- シャンパーニュ地方のランス
- スペインの古都、トレド
| フォンテンブロー城 |
ハルビソンの村はパリから車で1時間の距離にある。19世紀半ば、コロー、ミレ、ルソーなどがパリから移り住み、芸術活動を続けた静かな佇まいのある村である。フォンテンブローの森に近い。フォンテンブロー城はその森の中にある。16世 "フランス・ルネッサンスの王" と称されるフランソワ1世が多くのイタリア技術者を招聘してこれまでの館を改修し城とした。ナポレオン1世は、1814年4月、パリが連合軍により陥落し、エルバ島へ追放されたが、エルバ島へ発つときに、ここ、フォンテーヌブロー城の「馬蹄の階段」の上で演説をした。翌年2月、エルバ島から脱出しパリに戻り「百日天下」をとる。しかし、6月、ワーテルローの戦いで敗れ、セントヘレナ島へ幽閉された。その階段の上に立って庭園を眺めると歴史を感じることができる。
ロワール河はフランス中央部を東から大西洋にそそぐ、全長1000㎞以上のフランス最長の河。河岸のロワール地方は「フランスの庭」と呼ばれる風光明美な地である。11世紀から15世紀に防衛目的あるいは王侯貴族の居住を目的に各地に城が建てられ、その数は100を超えるという。今回はロワール河中流のツール近郊を訪れた。
| クロ・リュセの館 | ロワール・シュノンソー城 |
「なぜ、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた〈モナリザ〉がフランス(ルーブル美術館)にあるのか?」これをよく理解するためにトゥールから車で1時間走り、クロ・リュセの館を訪れた。レオナルド・ダ・ヴィンチは1516年、64才のときフランソワ1世の招きを受け、ロバの背に乗りアルプスを越えてこの地に来た。この館を王から与えられ1519年に没するまで住んでいた。2人はまるで親子のようであり、王はレオナルドを、我が父と呼んでいたという。館は600mの地下道でアンボアーズ城と結ばれている。レオナルドはこの地に来るときに手元に置いていた3枚の絵を大事に携えてきた。その1つが「モナリザ」である。だからフランスに残されたということだ。館は現在公開され、周辺はレオナルドに因んだ公園にしてある。館から車で30分程で、シュノンソー城に着く。16世紀創建以来19世紀まで代々6代の城主がすべて女性であったので6人女の城とも呼ばれる。城内にロワール川の支流シェール川が流れ、川をまたぐように白い城館が建ち、姿美しく、ロワールの古城の中でも人気が高い。アンリ―2世王(1547年即位ー1559年)をめぐる2人の女性の愛憎、熾烈な確執の舞台としても有名である。1人がアンリ2世の12歳年上の美貌の愛妾がディアーヌ・ド・ポアチエであり、もう1人が王妃であるイタリア・メデイチ家出身のカトリーヌ・ド・メディシスだ。これは長い物語になるので続きは省略する。
| ランス シャンパーニュ地下蔵 |
これぞランス! 大聖堂とシャンパーニュ |
シャンパーニュ地方のランスはパリの東北東140キロにあり、TGVで45分で行ける。13世紀に着工されたノートルダム大聖堂はゴシック建築の傑作と言われる。898年のシャルル3世から1825年のシャルル10世まで、歴代の王はランスの大聖堂で受洗式や戴冠式を行なった。英国との百年戦争のさなかの1429年にジャンヌダルクがオルレアンを解放したとき、シャルル7世にランスへ向かわせ戴冠式を行い彼女も立ち会っている。彼女は翌1431年、捕らえられてルーアンに送られ火刑にされたが、その時19歳であった。ランスはシャンパーニュの産地の中心地でもある。数多くのシャンパーニュ・メゾンが社屋を構えている。今回はポメリー社を訪れた。地下蔵が石灰岩の地下深く掘られ、気温は10℃くらい。この中で熟成を待つ。地下蔵は街全体では240kmにもなるというから驚きである。
| トレドへの入り口―ピサグラ門 | トレドの全景 パラドール・デ・トレドのベランダから |
スペインのトレドはパリから2時間弱のフライト。711年、イスラム教徒ムーア人がイベリア半島を侵し、トレドも支配下においた。1085年、イベリア半島一部を取戻したスペインはトレドを首都にした。1492年にはスペイン全土でのレコンキスタ(国土回復運動)が成就し、スペインは大航海時代へ入る。1561年、首都がマドリードに移った。トレドは "16世紀であゆみを止めた街" と言われている。19世紀、欧州に旅行ブームが起こり "スペインで1日あればトレドへ行け" と言われていたという。マドリードには何回か仕事で来たことがあったが、残念なことにトレドを訪れる機会がなかったので大いに期待していた。夕日の中でトレドの街の全景をパラドール・デ・トレドのベランダから一望して長年の望みを果たした。
 「多様性と神秘の国インドネシア」寺尾勝汎氏
「多様性と神秘の国インドネシア」寺尾勝汎氏
仕事やプライベートで世界各国に行きましたが、いくつか抜けている所があり、インドネシアもその一つです。念願かない昨年7月12日〜21日の駆け足ツアーに参加しました。このツアーはDF会員萩原氏のご推薦のスラウェシ島(セレベス島)訪問が入っており大変興味深かったです。成田を昼に出て17時ジャカルタ到着(時差2時間―7時間のフライト)。乗継でスラウェシ島の表玄関ウジュンバンダンに着きました。インドネシアは世界最大のイスラム国家(人口の90%)で、空港の売店の間に祈祷室があるくらいですが中東ほど戒律は厳しくないようで、特にスラウェシ島(4番目に大きい)はキリスト教徒、ヒンドウー教徒も相当居るとのことです。翌13日終日バスに乗って島の秘境タナトラジャを訪問しました。有名な舟型屋根のある集落も残っています。ここの人々は2500年前に中国から船で渡って来た人の子孫だと信じられており舟型屋根はそれを残したもので、北の方向に向いています。祖先崇拝の土着宗教が強く、葬儀が人生最大のイベントで生贄の水牛を大切にしていました。
| タナトラジャの舟型屋根の集落 | タナトラジャの岩窟墓 |
15日にバリ島に移動。観光地として有名ですが愛媛県位の大きさの島で人口350万人、90%がヒンドウー教徒です。3万の寺院があるそうですが、最も美しいと言われるタマンアユン寺院を見物し、世界遺産の棚田、キンタマーニ高原を見て海中の岩礁にあるタナロット寺院で美しい夕日を拝みました。夜は民族舞踏ケチャダンスを見ました。
| 海中の岩礁にあるタナロット寺院 | ボロブドール寺院の全景 |
18日からジャワ島のジョグジャカルタの見物です。ジャワ島は5番目に大きな島で、首都ジャカルタもある人口密集地で本州と九州を合わせた位の広さに全人口2億5千万人中1億3千万人が住んでいます。ジョグジャカルタは古都で、何代も支配者が変わったので仏教、ヒンドゥー教の遺跡が多く残されています。まずボロブドウル遺跡。世界3大仏教遺跡での一つで8世紀の後半から50年かけて建立された壮大な石の建物です。4層からなる回廊は釈迦の生涯を浮彫にしています。千年間火山灰に埋もれていましたが1814年に英人ラッスルズにより発見されました。更にこれも世界遺産のヒンドゥー遺跡プランパナン寺院を見物しました。
翌19日にはサンギラン村を訪問しました。ジャワ原人が発見された所です。翌日はジョグジャカルタの王宮を見学しました。王様はこの地方の知事を務めており王家は健在です。人々の崇敬を集めており無報酬で衛士を務めています。
| サンギラン村の博物館 | 寺院で遊んでいた幼い姉弟 |
インドネシアは多くのエスニシティ、宗教、言語を持ち300年のオランダ植民地統治の行政範囲を基に第2次大戦後独立した若い国で、多くの難問を抱えていますがポテンシャルの高い国です。機会があればまた訪問したいと思いました。
お2人からのプレゼン醒めやらぬうちに第2部の懇親会が同場所にて始まり、事務局長としてご活躍の保坂洋氏による乾杯を皮切りに地中海料理と飲み放題ビール&ワインを嗜む場面に変わりました。今回は、世話役の今井様が急遽奥様の手術に対応されるためにご欠席されるなど、普段より少なめの12名の出席でしたが、恒例となりました全員のショートスピーチ(ロングの方もちらほら)で大いに盛り上がり、次回9月開催予定の発表者のうち1名が決まって9時近くにお開きとなりました。
(文責 鈴木 哲・今井智之)
■ 第57回 「海外旅行研究会」
海外旅行研究会第57回例会が平成27年5月18日(月)丸の内倶楽部21号館で開催されました。
最初に曽山高光氏により、「ルツェルン撮影日誌」と題して同地及び近辺の遺跡や絶景の写真撮影の旅の報告がありました。腰椎手術後はじめての海外旅行でしたが、緻密な移動計画と手段で無事初期の目的を達成されました。その証拠に、さすが写真同好会世話役でもありますが、数々の大変美しい写真を披露されました。
続いて、濱本龍彦氏が、「米国西部の国立公園を巡る」を発表し、イエローストーン、グランドティトン、ロッキーマウンテン、ヨセミテ、グランドキャニオン等広範囲にある8か所の公園を回り、その詳細を報告されました。グランドティトンは映画「シェーン」のロケ地で、その最初のシーンを映画から抜粋したものや、NHKのデスヴァレーに関する動画映像をパワーポイントに貼り付けるという新技術をも披露しました。
以下は両氏からの報告概要です。
 「ルツェルン撮影日誌」曽山高光氏
「ルツェルン撮影日誌」曽山高光氏
今回の旅は術後1年ぶりの海外旅行で私にとっては「リハビリ旅行」で次の海外旅行の確認となりました。旅の主なテーマは一か所に滞在しての「写真撮影」でした。その目的に叶う所としてスイスの「ルツェルン」を選びました。その理由はいくつかありますが、スイスの中でも「中世の街並み、山に囲まれ、湖があり景観に優れている」のが第1です。
撮影テーマの第1はルツェルンの市内を流れる「ローヌ川」の北側に位置する「旧市街」です。旧市街地では観光的にも有名な「カペル橋」と「旧市庁舎」がハイライトで、カペル橋は1993年に火災にあいましたが翌年再建されルツェルンのシンボルとしてその姿を現在でも留めています(写真①)そのほかにも中世に描かれた建物の壁画や、1386年に建造され、町を囲っていて現在はその一部が残っている城壁など「中世の姿」を見ることができました。
| 写真① | 写真② |
テーマの第2は町の両側にそびえるリギ山(1798m)とピラトス山(2067m)です。今回はリギ山へ。湖を船で渡りそこから登山電車で頂上へ。頂上では3000〜4000m級の「ベルナー・オーバーランド」地方の雪をかぶった山々が眺望でき、またその西側には「ピラトス山」が見えました(写真②)またかなり多くの高山植物がまだ咲いていました。
テーマの第3は「ルツェルン湖」のクルージングです。「ルツェルン湖」は通称で正式にはドイツ語で「四森州湖」と言われ4つの州に囲まれています。広さは114k㎡で「猪苗代湖」より少し大きい湖です。湖の最南端からルツェルンまで船で2時間50分かかりましたが、その風光明媚な湖岸の景色はあきませんでした(写真③)
| 写真③ | 写真④ |
テーマの第4は市街地からすぐの湖岸の景観です。湖岸にはスイス最大と言われる「スイス交通博物館」があり2000㎡の敷地内に陸、海、空を網羅した約3000のコレクションが展示されています。子供だけでなく大人も1日中楽しめるところです。湖に沿ってマロニエの並木の「プロムナード」が続きます。ここは、観光客は少なく町に住む人達が散歩を楽しんだり、ベンチで休憩をとる憩いのプロムナードです(写真④)
5泊のルツェルン滞在中は天気にも恵まれ、目的の写真も撮れて大変満足できる旅でした。
 「米国西部の国立公園を巡る」濱本龍彦氏
「米国西部の国立公園を巡る」濱本龍彦氏
米国には歴史的な所産は多くはありませんが、壮大で、かつ壮烈な自然があります。特に米国の西部には数億年前からの地殻変動、火山活動、海面変動・風化・浸食などによってつくられた自然の造形美を数多く見ることができます。
1800年代の初めから、米国の東部から探検、開発、移住のために西部へやってきた白人によってこれらの自然が発見され、保存されてきたのですが、それは紀元前5000年以上前からの先住民(ネイテイブアメリカンいわゆるインディアン)との抗争と協調の歴史でもありました。
米国は、世界で初めて1870年に国立公園法を制定しました(日本は1931年)。その指定第1号がイエローストーン国立公園、第2号がヨセミテ公園です。グランドキャニオンも指定され、これら3か所は世界遺産にも登録されています。
| イエローストーン国立公園 | グランドキャニオン国立公園 |
| モニュメントヴァレー | ヨセミテ国立公園 |
今回はこれらを含めて8か所の国立公園とその周辺のいくつかの景勝地を紹介しました。他の5か所の国立公園は、グランドティトン、ロッキーマウンテン、ブライスキャニオン、ザイオン、デスヴァレーです。
いずれの国立公園も途方もなく広大で、観光のために訪れ得る場所はごく限られていますが、皆さんも訪問されてその壮大・壮烈さを実感されてはいかがでしょう。
例会後恒例の懇親会が開かれ、出席者全員によるユーモア溢れるショートスピーチで会場を大いに湧かせました。次回は7月に、寺尾勝汎氏による「インドネシア旅行(仮称)」と、濱本龍彦氏の「フランス、フォンテンブローの旅(仮称)」が報告される予定です。日程が決まり次第ご案内致します。
2015・5・20(今井智之記)
■ 第56回 「海外旅行研究会」
平成27年3月30日、皇居界隈は正に桜が満開の中、第56回例会が丸の内倶楽部21号館で13名のご出席をもって開催されました。
最初に萩原秀留氏が、「最後の楽園」と題してミャンマー紀行を発表し、同国に関する情報を効果的に解説したあと、多くの歴史遺産、とりわけパゴダ等の木目細かい紹介をして頂きました。長年、政争や混乱が続いた国としては遺産がよく保存されて来たことが伺われ、今後は貴重な観光資源となりましょう。
続いて戸田邦男氏による「南フランスの小さな美術館を訪ねて」が発表され、パワーポイントをはじめて使用したというものの、資料が大変よく作成されていました。実は萩原氏と同様、動画さえも貼り付けて来たそうですが、会場のパソコンとの整合性がとれなかったせいか、いずれの動画を見ることが叶わず、誠に残念でした。戸田氏は、旅の途中いくつものトラブルに巻き込まれながら、却ってそれらをも旅の楽しみとして捉え、大変ユーモアに溢れた報告となりました。以下はご両氏からの報告概要です。
 「最後の楽園―ミャンマー紀行」萩原秀留氏
「最後の楽園―ミャンマー紀行」萩原秀留氏
軍政から民政に変わって4年、今、発展途上国の仲間入りをしようとしている国ミャンマーには、まだまだ自然が残り、人々の素朴さに触れることができるであろうことを期待して1月21日から8泊9日の旅にでかけた。昨年から毎日成田からの直行便も開設、東南アジアの最後の楽園でとなったミャンマーはこれから発展する国である。
仏教徒70%のこの国には、いたるところに仏舎利または法舎利を安置するためのパゴダ《ビルマ語パヤー、仏塔(ストウーバ)を意味する英語》があり、ミャンマー各所でのパゴダの見学が観光の対象であった。とくにパダンには数多くのパゴダがあり、あるパゴダの上から林の間のパゴダのシルエットの間に沈む夕日の観賞には、世事を忘れ瞑想にふける事ができた。
ミャンマーは上部座仏教の国、献金、托鉢その行為が功徳になり献金の行方は問わないとのこと。仏塔、仏像、涅槃仏は大きなものがあるかと思うと金箔でピカピカであったり、顔が真白であったりいろいろだった。
日本の1.8倍の面積に日本の約半分の人口。中央を流れるエイヤワディ(イラワディ)川流域に住むビルマ族が70%。全部で135の民族がいるとのこと。これら少数民族は国境地域の山岳に住み、民政化された政府と間はうまくいっていると思われていたが、時折戦闘状態の報道がある。ただ今回旅行した地域は非常に安定しており、都会地は別にして電力不足のためか蝋燭の灯りで夜の商店街も安心して散歩ができた。
ヤンゴン、インレー湖、マンダレー、バゴン(含むボッパ山)、へはそれぞれ飛行機で移動。チャイティーヨーへはヤンゴンから日本の中古バスで巡った。
ヤンゴンはミャンマー最大の都市、2006年にネーピードーに移る前の首都。経済の中心地である。車の渋滞が激しかった。イギリスから独立した時イギリス流はなにもかもやめたいとのことから車の左側通行を右側に変えたが、車はそのままで右ハンドルが多く。特に日本からの中古バスは乗り降りが道路の中央になり危険であった。
| クドードー・パヤー | パゴダに沈む太陽 |
足で櫂を漕ぐインレー湖の漁民(動画) (左下の三角マークをクリックしてご覧下さい。右下の矢印をクリックするとフルスクリーンとなります。<esp>キーで元に戻ります。音量は右下のスピーカーマークで行えます) |
|
インレー湖はシャン高原にあるミャンマー最大の湖。海抜884m 夜は寒くて毛布が必要だった。ボートで水上パゴダや足で櫂を操る漁民を見た。
マンダレーは王宮がおかれたミャンマー第二の都市。ヤンゴンの飛行場が国際線受入れ用に改築中で現時点では非常に貧相であったが、それに比べマンダレーの空港は1999年に街から40km離れた場所に作られた国際空港。しかしほとんどが国内線だけのためビルは豪華だが人がおらず閑散としていた。
バガンは多くのバゴダや僧院が林の中に点在しミャンマー観光の中心。とくに欧米人を多くみかけ東洋人はあまりいなかった。パゴダ参拝は裸足になることが決められており、多くの寺院観光を回ったため靴を脱いだり履いたりが大変であった。ミャンマーの土着信仰ナッ神の聖地ポッパ山山麓のタウン・カラットはバガンの南東50kmにあり、バスで往復。車からおりて両側に土産物屋が並ぶ約777段の階段の上にある。
| 今にも落ちそうな大岩 |
チャイティーヨーはヤンゴンの北東200kmにあり、大きな岩の上に一つの大きな岩が今にも落ちそうな格好で鎮座している。この岩の上に高さ7mほどの小さな仏塔が建てられており、早朝から夜遅くまで参拝者が絶えない。そこは山の上にあり麓のキンプンからトラックの荷台に簡単な座席を作ったトラックバスで登る。ヤンゴンの人は年に1回は行くミャンマー屈指の巡礼地。国境を越えタイからも信者がやってくる。
第二次世界大戦が終了しイギリスの植民地から独立後、社会主義国、軍政と代わったミャンマー、基本的に農業国で何も望まなければ食には困らず、そのままで十分暮らして行ける豊かさがある。果物が豊富で街道筋には売店が多くあった。ただ時代の波が押し寄せており、農村ではテレビ、バイク、携帯電話が、都会ではテレビ、冷蔵庫、クーラーが欲しがられるといわれており、日本をはじめ多くの国が援助を差し伸べているので、これからの発展で国が変わること必至。
期待通り自然と素朴さの残る最後の楽園での旅だった。
 「南フランスの小さな美術館を訪ねて」戸田邦男氏
「南フランスの小さな美術館を訪ねて」戸田邦男氏
2014.5.30〜6.16南フランス(コートダジュール)の小さな美術館を巡る旅をして来ました。パリからニース、エクス・アン・プロバンス、アルル、アヴィニオン、トゥルースそしてパリと国鉄を使った旅です。南フランスには小さな美術館が沢山あり、その内10か所の美術館を廻ってきましたが、その一部を記述いたします。
シャガール美術館(ニース)
正式には国立マルク・シャガール「聖書の言葉」美術館で1973年創立、サーカスと聖書を題材とした大作がズラリと展示され圧巻である。青の時代、赤の時代と分類されており不思議な異次元の世界であった。
グラネ美術館(エクス・アン・プロバンス)
個人所有の小さな美術館でセザンヌの絵が8点あった。
エクスはセザンヌが殊の外愛した場所で彼が生涯多数描いたサント・ヴィクトール山の所在地でもある。
ゴッホ財団の美術館(アルル)
ゴッホ財団の事務所かとおもったが2013年に美術館が開設され、珍しいゴッホの作品を数点見ることができた。アルルの街中では「夜のカフェテラス」のモデルになったカフェで休憩、暫し感概にひたることができた。
| シャガール美術館にて | シャガール美術館にて | ガ—ニッシュメールの路地 |
| ゴッホ財団美術館にて | 「夜のカフェテラス」のモデル | アン・グラトン美術館にて |
アン・グラトン美術館(アヴィニオン)
常設展以外にちょうどロートレックの特別展が開かれていた。館内では子供達がいくつかのグループに分かれ、ロートレック、セザンヌ、思い思いの画家の絵の前で模写をしていた。数年前に行ったパリのピカソ美術館や今回のダリ美術館でも遭遇、ヨーロッパの国々ではよく目にする光景であるが日本では考えられない。
今回の旅は美術館訪問が中心であったがそれぞれ美術館への往き来に偶然目にした街中の景観、人々との出会い、触れ合いには思い出深いものがあった。またニースでのスリ事件、国鉄のストのために起きた数々の問題、深夜のパリ到着とタクシー争奪戦、モンサンミッシェルツアーのバスのパンク事故等アクシデントの多い旅でもありました。その成果はさておき今回のフランス旅行は私にとって記憶に残る旅になったことは間違いあいません。
ニース: |
マティス美術館、シャガール美術館、ルノワール美術館 |
エクス: |
セザンヌのアトリエ、グラネ美術館 |
アルル: |
ゴッホ財団、レイチェル美術館 |
アヴィニオン: |
アン・グラトン美術館 |
パリ: |
ダリ美術館、オルセー美術館 |
恒例の懇親会は同会場で、真瀬宏司氏の乾杯の音頭で開かれ、地中海料理とワインを堪能しながら、全員がスピーチ合戦で会場を沸きたてました。次回(5月)は、濱本龍彦しによる「アメリカ国立公園(仮称)」と曽山高光氏の「スイス旅行(仮称)」が発表の予定です。
2015・3・31(今井智之記)
■ 第55回 「海外旅行研究会」
第55回例会が平成27年2月9日丸の内倶楽部21号館で開催されました。麗しいご婦人2名のゲストを迎えての和気藹藹とした楽しい会合でした。プレゼンテ-ションは、先ず保坂洋氏による「夏のコッツウォルズのんびりドライブの旅」でした。昨年6月、英国では一番気候のよいとき、オックスフォードと、ウインストン・チャーチル生誕地ブレナム・パレスを皮切りに20か所近くの村々をドライブした様子がまざまざと感じられました。ザ・ローワー・スローターのホテルをベース・キャンプとして日々80キロ程度のドライブ旅行をされたのは極めて適切であったようです。ウイリアム・モリスが「英国で一番美しい村」と言ったバイブリーは日本人観光客が溢れ失望し、比較的地味な村であるスノーズヒルが一番お気に入りであったとか。
続いて、井上史男氏が「中世の風の中で〜ベネチア・トスカーナ紀行」と題して歴史遺産、景観そしてグルメとワインを楽しむイタリア旅行の神髄を披露されました。年間2000万人もの観光客が集まるベネチアは、イタリアの、いや世界の宝石とも言えましょう。観光客で溢れるサンマルコ広場を離れ、運河にかかった無数の橋を渡って小道を散策する楽しみは格別なものです。トスカーナでは、ワインとグルメの他、オルチャ渓谷のような自然の美しい景観とシェナのような中世の町にタイム・スリップするような歴史遺産を大いに楽しまれたようです。おふたりとも写真が大変お上手ですから美しい景色を満喫させて頂きました。
以下はお2人からの報告概要です。
 「夏のコッツウォルズのんびりドライブの旅」保坂洋氏
「夏のコッツウォルズのんびりドライブの旅」保坂洋氏
2014年6月27日から7月3日、英国コッツウォルズの村々を巡るドライブ旅行を楽しんできました。同地方は東京都より広い面積の中に200の小さな街と村が点在し、とてもすべてを訪れることはできません。何処を巡るか?「○○はガイドブックに載らず、殆ど観光客は訪れませんがすばらしい雰囲気です」などという情報に接すると迷ってしまいます。旅行経験者や駐在経験のあるDFメンバーの意見、ガイドブック、ウェブ情報を参考にしてコースを決めました。初めてなので著名で基本的な場所は入れ、その他はホテルを含め団体客が訪れ難い所を選ぶように心掛けました。
コッツウォルズの入口でいかにも英国らしい雰囲気を持つ学生街オックスフォード、スコールが降り虹の掛かる街はずれからレンタカーで出発しました。
王室のどの邸宅よりも壮麗と言われるブレナム宮殿で結婚式に出席する正装した紳士淑女に感動、3泊した住宅街・小川・羊牧場が調和した小村ロウワースローター、フットパスを散策して行ったアッパースローター、茅葺屋根のブロードカムデン、最古の市場街チッピングカムデン、展望のドーバーズヒル、駅馬車の宿場町ブロードウェイ、のろし塔ブロードウェイタワー、静かで落ち着いた小村スノーズヒル、映画のロケ地スタントン、ウィンチコム、シェークスピアの生誕地ストラトフォードアポンエイボン、ミッケルトン、親子3代で築いた花の庭園キフツゲートコートガーデンズ、ナントン、リトルベニスと言われるボートンオンザウォーター、ハリーポッターのロケ地大聖堂がある街グロスター、2泊したウイリアムモリスが一番美しい村と称賛し、日本人にも人気のバイブリー、ウィリアムモリス記念館ケルムスコットマナー、王室の避暑地テッドベリー、ベレー夫妻の庭園バーンズリーハウスガーデン、ローマ遺跡が残る要衝の街サイレンセスターを6日間で回りコッツウォルズの旅を終えました。
一昨年仏ミディ・ピレネー地方をドライブした時は1日200㎞走りましたが、最終地に午後7時ごろ着くことが多く余裕を感じられなかったため、今回は1日100㎞以下とし、のんびりと安全にドライブすることができました。日本で目的地をセットして持参したカーナビは今回も間違いなく案内を務めてくれました。
コッツウォルズはロンドンから近く、少し走れば村や街があり、ひなびた田舎ではありませんが、村の間は緩やかな起伏の道が結び、両側は手入れの行き届いた畑や牧草地が広がり、村々は人の暮らしと自然が調和した落ち着いた佇まいです。幸い初日のオックスフォードでスコールに遭遇しただけで好天にも恵まれ、適度に地元の人達との交流もあり、心が洗われるすばらしいひと時を過ごすことが出来ました。
バスに乗り次の目的地ロンドンへ向かいました。
| 朝のお散歩 ロウアー・スローター |
昼の ボートン・オン・ザ・ウォーター |
夕方の バイブリー アーリントン・ロウ |
| オックスフォードに掛かる 虹の架け橋 |
ブロードカムデンの藁葺の家 | スタントンの落ち着いた家並 |
 「中世の風の中で〜ベネチア・トスカーナ紀行」井上史男氏
「中世の風の中で〜ベネチア・トスカーナ紀行」井上史男氏
毎年絵になる風景を求めて国内外を旅行し、その時のスケッチと写真をもとに水彩画を描くことを楽しみにしているが、今回の旅先はベネチアとトスカーナ、どこを見ても絵になる風景ばかりの場所である。事前の準備でベネチアやトスカーナを描いた有名画家の絵を目に焼き付け、あるいは写真を撮って持参した。それはターナーやモネから荻須高徳、そして堀文子などの絵であった。また絵を描く者にとって重要なのはホテルの部屋のロケーション、十分な調査とホテルへの確認も怠らなかった。今回ベネチアのホテルはサン・マルコ運河が見渡せるテラス付きの部屋を予約し、ホテルの部屋から描けるお膳立てを整えた。また、ベネチアやトスカーナは中世に繁栄した歴史文化豊かな地域。塩野七生氏の「海の都の物語」や堀米庸三氏の「中世の光と影」なども読み直し旅の楽しみに加えた。
ベネチアの5日間は晴天に恵まれ心配したアクアアルタ*もなく、この比類なき水と光の中の中世の町を満喫。有名画家のスケッチポイントを探しながらの散策は大変楽しい時間であった。また、本場の魚介類のパスタやリゾットは旅の楽しみを倍増させ忘れ得ぬ思い出になった。
トスカーナの風景やオルチャ渓谷の美しさも期待通りだったが、特にコルトーナが素晴らしかった。ダイアン・レイン主演の映画「トスカーナの休日」の舞台になった町は小さいながらも眺望の良さ、中世がそのまま残っている街並み、珠玉のルネッサンス絵画、知る人ぞ知る美味しいワインなどトスカーナの魅力をすべて備えている町であった。ここのワインに魅了されたことにより、その後7日間毎晩その土地のワインを1本ずつ空けてしまった。フランスでも必ず旅先のワインを楽しんできたが、そのワインリストにトスカーナのワインが加わった。絵になる風景と美味しい料理とワイン、今回の旅も期待以上の素晴らしさだった。
| 早朝のサン・マルコ運河 | ベネチア絶景 | ゴンドラに揺られて |
| 黄昏のベネチア | オルチャ渓谷展望 | シエナの鐘楼 |
*註:ベネチアで秋から春にかけて頻繁に発生する異常潮位現象でサンマルコ広場等が冠水する
恒例の懇親会は、鈴木哲氏ご手配の地中海料理とアサヒビールで乾杯のあとチリ産の白赤ワイン飲み放題で盛り上がりました。世話役の、ゲストへの紹介を含めての司会による全出席者のテーブル・スピーチは、ユーモラスで話す人も聞く人も大いに楽しまれたようでした。次回は、3月30日(月)に同会場で開催されます。発表は、萩原秀留氏による「ミヤンマー紀行(仮称)」と戸田邦男氏による「南仏美術館巡り(仮称)」と決定しました。