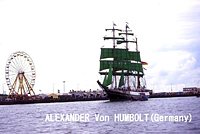海外旅行研究会第26回例会
第26回例会が11月26日午後ディレクトフォース会議室で、会員11名の他石原正之氏の特別参加を得て、開催されました。今回は、常信伊佐夫氏の「ハンガリー&フィンランド気まま旅行」というテーマで、続いて井上史男氏の「アルザスワイン街道とノルマンディー印象派の旅」でプレゼンが行われました。
常信氏は当会の大ベテランであり、自由旅行の企画に長けており、今回も美しい写真を多数紹介しつつ大変楽しいお話をされました。特にブタペストで出合った、若く美しい女性の写真はプロ並みの腕前でした。アニメーション効果はもとより動画や音楽を交えてのプレゼンは一段のスキル向上を示していました。
井上氏は、フランス北半分を列車やレンタカーで緻密に巡る旅を堪能されたことを窺わせました。アルザスワイン街道とトローヴィルの紹介は当会では今回初めてでした。写真もプレゼンスキルも横綱格です。ご自身でお描きになったイラスト風地図はフランス的な雰囲気を漂わせていました。以下はプレゼンの概要です。(写真をクリックすると拡大できます)。
「ハンガリー&フィンランド気まま旅行」常信伊佐夫氏
ハンガリーを旅行先に選んだ第一の理由はドナウの真珠と称されるブダペストの夜景を撮影したいということだったという。フィンランドに立ち寄ったのは、フィンランド航空がストップオーバーフリーなので、ヘルシンキに降りて中世の雰囲気を色濃く残すエストニアの首都タリンに行ってみたいと思ったからと説明があった。
ブダペストでは観光だけではなく美人に出会いポートレートを撮らせてもらったとか、市内の伝統ある温泉に入るなど新しい出会いや体験をしたそうで、さらには世界遺産ホッロクーを1日1便のバスを使って訪れるなどチャレンジ精神あふれる個人旅行を楽しまれたとのこと。有名なトカイの貴腐ワインをホテルの部屋で賞味し、その美味なことに感銘を受けたとのエピソードを披露されました。
ヘルシンキでは近郊のポルボーに出かけのどかな風景を楽しみ、宿泊ホテルで本場のサウナに入り病みつきになったことや、日帰り小旅行でエストニへと足を伸ばし中世ハンザ同盟の町タリンを散策したことなど、いつもながらの気ままで自由なスタイルの個人旅行を紹介する発表でした。
旅行中にブダペストのトラムの中でスリに遭遇し、あやうく財布をすられそうになった話があり、海外旅行における危機管理のあり方が参加者の話題になったのも海外旅行研究会らしいところでした。 |
「アルザスワイン街道とノルマンディー印象派の旅」井上史男氏
 |
| アルザスワイン街道リボーヴィレの村 |
 |
| 画家に人気のオンフルール旧港 |
パリから東へTGVで2時間半行くと美味しい白ワインを産する里とおとぎの国のような村々があることは日本ではあまり知られていない。井上氏がアルザスを知ったのは約15年前に自動車部品の調達の仕事でこの地を訪れたからで、その時の「再びこの地に来たい」との思いを昨年6月に実現させた旅だという。ドイツ国境の町ストラスブールに1泊した後、アルザスワイン街道の中心地コルマールを拠点にワイン街道に連なる小さな村々をレンタカーで巡った様子が紹介されました。どの村も花で飾られた木骨組の家に石畳の道、いつでもワインが試飲できる醸造所と雰囲気がよいカフェやレストランなど人気の観光地であるとのことでした。
旅の後半は英国海峡に面したノルマンディー・ドライブでした。印象派の画家クロード・モネの足跡を追い、ノルマンディーの景勝地、例えば白亜の断崖が続くエトルタ海岸や多くの画家が描いたオンフルールの旧港などの紹介とそこでモネが描いた絵が同時に紹介されたのです。モネがノルマンディーで描こうとした、太陽の光に照らされ輝く海、白い砂浜、切り立った断崖、そして風や波など自然の素晴らしさを感じさせるものでした。
総じて、アルザス、ノルマンディーともに木目細かな個人旅行の楽しさが伝わってくる報告でした。 |
恒例の懇親会には10名が参加し、ビールの他、白ワイン2本、赤ワイン4本を飲み干して、いつものイタリア料理を飽きることなく堪能し、話が盛り上がりました。ワインのせいか、四方
満氏から「大変素晴らしい会で幸せだ」という溜息交じりの格別のお言葉がありました。ヴィバ・マンマミーア!
(文責 今井世話役) |
海外旅行研究会第25回例会
第25回例会が10月1日(木)DF会議室で開催されました。今回はベテラン・メンバー2人の初の発表で、会場は12名と満杯になりました。
まず坪井荘一郎氏は、研修とは名ばかり現役時代の観光旅行を発表されました。写真をデジタル化しソフトを使って動画風に取り込み、ミュージックを挿入し効果的な演出を工夫されました。続いて河島彦明氏がミラノ駐在時代に訪れたシチリアの史跡を紹介され、風景に合わせて美しい奥様の写真も沢山見せて頂きました。同氏はパワーポイントの技術を独学で取得し、今回の発表となったものです。以下は両氏の発表の概要です(写真をクリックすると拡大できます)。
「信和会第4回海外研修」という名の観光・ワイン・グルメの旅 坪井荘一郎氏
日産デーゼル工業時代(1996年)「大手部品メーカー23社による欧州研修団」が編成され、ヨーロツパ市場におけるトラツク及び関連部品産業の安全と環境面(長期排ガス対策、リサイクル、産業廃棄物)での開発状況調査を主眼に、「ドイツ、イタリア、ベルギー、スペイン、フランス、スイスの6ケ国を15日間に亘り訪問した際、公式訪問の合間に観光した6ケ国の名所、旧跡巡りをした模様を報告したもの。
ドイツではライン下りを満喫、途中城めぐりをし、船上から伝説で有名な「ローレライ」を眺望。フランクフルトへの帰路東西ドイツの統一を象徴する大記念碑ニューダーヴァルト・デルクマールやゲーテの生家を見学。イタリアではバチカンのサン・ピエトロ寺院に次ぐ巨大なゴチック建築の大聖堂であるDUOMO(ドウオーモ)、グエル公園、サンタマリア・デレ・グラツイエ教会でレオナルド・ダ・ビンチの壁画「最後の晩餐」他を見学。イタリアでの料理・ワイン・ビールの味は格別だったという。イタリアでは格式あるレストランは午後8時以降に開店し、2~3時間かけて、ゆっくり食事とワインと会話を楽しむのだそうで、ミラノのレストラン「GIANNINO」「SAVINI」は料理・雰囲気とも格別であったとか。
スペインもイタリア同様、料理・ワインの味は素晴らしく、特に地中海から採れた新鮮な海鮮料理は美味で、食後のフラメンコ・ショーでダンサーの迫力ある踊りを満喫したという。建築物では天才建築家ガウディーの設計による聖家族教会はそのとき既に圧巻であつたという。
スイスでは、ユングフラウヨツホを訪ねた。標高800MのU字谷の底にあるラウターブルーネンより登山電車に乗り牧歌的なハイジの世界、雄大なアルプスと迫力あるアイガー北壁、壮大なアレツチ氷河を見ながら標高3,454Mにあるヨツホ駅に到着。自然の美しさを改めて実感、心が洗われる思いがしたそうな。
ベルギーでは、ブリュツセルにある有名な「王の家」を見学。その壮大さとグランプラスのレイアウトに感嘆し、またビールの種類とうまさには脱帽したという。最後に訪ねたフランスでは、ベルサイユ宮殿とルーブル博物館が圧巻であつたと説明。
発表の間、及川民治によるピアノ演奏でベートーヴェンの皇帝・熱情の曲が画像と共にバツクグラウンドに流されたのは印象的でした。 |
シチリア周遊 車の旅 河島彦明氏
 |
| アグリジェント コンコルディア神殿 |
 |
| シラクーサ ゲレコ劇場 |
河島氏は旅行研究会発足以来のメンバーで満を持しての初登場であった。題した通り、同氏が8年にわたるイタリア在住中の2000年正月に夫妻でミラノから車でフェリーを利用してシチリアに渡り周遊したものです。帰路は長靴半島の先端を経て陸路アドリア海側を北上し、ラヴェンナ経由でミラノに戻るという、シチリアを含めてイタリアを殆ど一周する短期間での長距離ドライブ旅行の記録である。その距離はなんと2千キロを上回る。しかし主な目的はシチリアを周遊することで、シチリアの遺跡、歴史建造物をカメラに収めながら、シチリア3千年の歴史を垣間見ることができるというものでした。文豪ゲーテも有名なその著“イタリア紀行”において“シチリアにこそイタリア全てに対する鍵がある“と言っているようにシチリアは素晴らしいところであるという。既にイタリア各地を観光しイタリア好きを自任するメンバーの方々は、次は是非シチリアへと印象付けた今回の発表であった。 |
懇親会はマンマミーアで10名参加。政権交代という新事態で話題も豊富であったせいか、いつもより盛り上がりました。乾杯のビールの他、白2本、赤(シチリアの少々東で半島のかかと部分にあるブーリア産)4本のワインを飲み干しました。
(文責 今井世話役) |
海外旅行研究会第24回発表会
7月14日に第24回目の例会が開催されました。田中代表の飛び入り参加を含め総勢13名で会議室は超満席となりました。今回は、井上史男氏の「中世の巡礼路 ロマネスク美術と美食を求めて」及び四方満氏の「カンボジアー地雷と民族織物の復活」が発表されました。前者は、もっぱら手作り自由旅行を楽しむ井上さんの初めての発表でした。写真、イラストそして解説は大変素晴らしく、プロに負けぬ優秀なものでした。後者は、ロータリアンで社会貢献に大変熱心な四方さんが、仲間と共にカンボジアの地雷処理の視察を行ったときの事情を発表されたものです。なお、今回の懇親会も定番のマンマミーアで大変盛り上がりました(写真をクリックすると拡大できます)。
「中世の巡礼路 ロマネスク美術と美食を求めて」井上史男氏
フランスに魅力を感じ、テーマを持って毎年フランスの各地方を旅行している井上氏が、ミディ・ピレネー地方とブルゴーニュ地方の美しい写真を映写しながら旅行紀行を報告された。
今回のテーマの中世の巡礼路とは、キリスト教の聖地スペインのサンティアゴ・デ・コンポステラに向かう、世界遺産に登録されているフランス国内4つの街道である。巡礼は10世紀に始まりピーク時には年間50万人にも達し、現在も10万人以上の巡礼者がいるという。街道の要所には中世の面影を残す教会や修道院があり、付近の美しい景観とあいまって一般の観光客も数多く訪れている観光地である。
それらの教会にはロマネスク建築の傑作といわれる建物や彫刻がある。実際に同氏が訪れたモワサックやヴェズレー、オータン等の教会入口上部タンパンの彫刻や柱の上部に施されている彫刻の写真が映し出され、その意味するところも説明された。ロマネスク彫刻は聖書の一場面を表したものの他に奇怪な動物や悪魔の彫刻も多く、何故これに興味を持つのかも皆理解できたようであった。また、モワサックにあるサン・ピエール修道院の回廊は同氏が「ここを訪れるのが長年の夢でした」と話す様に、写真からも中世の雰囲気を感じる回廊である。
ミディ・ピレネー地方でドルドーニュ渓谷と聖地ロカマドールの話は、共に陸の孤島のような場所で日本ではほとんど知られていない地域だが、次々に映し出される美しい村々の景観は誰しも機会があれば一度は行ってみたいと思うものであった。
最後に、「この旅行で一番美味しかった物は?」との質問に「カオールでのフォアグラとボーヌでの牛肉の赤ワイン煮」と、その地方を代表する食べ物と料理が挙げられた。黒いワインと呼ばれるカオールワインに感動したようだ。
聖地と教会、美しい景観、美味しい料理とワイン、フランスの巡礼路紀行は大変興味深いものであった。 |
第23回海外旅行研究発表会
5月19日定例の発表会が開催されました。当初14名の会員の出席が予定されていましたが、業務上の都合と体調不調により3名の欠席となりました。今回は、冒険旅行で定評のある萩原秀留氏の「《三多》と《三無》の島チェジュ」及び今井智之世話役の「2008年チェコ古都の旅」が発表されました。
前者は、地政学的視点で旅をされたことを巧みなプレゼン技術で示しました。三多とは、石、風そして女、三無とは乞食、泥棒そして大門とのことでしたが、女について興味を抱かれた方には失望感は免れませんでした。近年、ヨーロッパの古都に関心が高い後者は、クロアチア旅行が不成立となり、代わりにチェコを旅したのですが、十分満足できる結果であったそうです。
以下にふたりの発表要旨を掲げます。恒例の懇親会もマンマミーアで盛大に開かれ、安く美味しい料理とワインを堪能しました(写真をクリックすると拡大できます)。
「《三多》と《三無》の島チェジュ」萩原秀留
 |
世界遺産「済州の火山と溶岩洞窟群」のひとつ、城山日出峰を菜の花畑から海を隔てての遠望 |
チェジュ、済州島は成田から飛行時間が僅か2時間半程度の距離にある外国。この島は、日本最大の島(本州、北海道、九州四国を除いて)、沖縄本島の1.5倍の広さがあるそうです。折からの円高ウォン安で日本からは20代30代の若いカップル、または、若い女性グループの滞在客が多く、萩原さんのように観光目的の訪問者は少なかったのこと。戦前はここから多くの人が日本に渡った結果、済州島の人は日本に親戚が多く、半島からの韓国の人と同様に多くの日本人が訪れているという。
1日目はホテルでくつろぎ、2日目は、島の東側にある世界遺産「済州の火山と溶岩洞窟群」のうち、城山日出峰を訪ね、菜の花畑から海を隔てての遠望と登山を満喫、そして溶岩洞窟万丈窟を探訪し、最後に、現在も人が実際に住む、城邑民俗村への観光を果たしたそうです。3日目は島の西側と南側を回り、翰林公園(狭才窟)、済州西広茶園、山房窟寺(竜モリ海岸)、大侑ランド(射撃場)、天帝淵滝、薬泉寺、ウエドルグエ(海岸景勝地)を観光。4日目は、韓国最高峰のハルラ山の登山口蛍室及びオリモクで雪を見たとのこと。帰路、登り勾配なのにエンジンを止ても車が動き出すという神秘道路がある、トッケピ道路、伝説発祥の三姓穴(サムソンヒョル)、東門市場等を回ったそうです。
ゴルフ場も多くあり、ホテルにはカジノや免税店など充実していそうです。みかん栽培以外これといった産業がなくチェジュは全島観光の島であるとのこと。
風と女と石が多く泥棒と乞食と塀には門がないのが島の特徴。これを称して三多、三無の島というそうだ。 |
「2008年チェコ古都の旅」今井智之
チェコで連想できることは、音楽でプラハ音楽祭とスメタナとドボルザークでしょう。スメタナの「我が祖国」をインターネットで取り込みBGMとして流しましたが、音が小さくて聞きにくかったのは残念でした。政治では、プラハの春、宗教ではヤン・フスの火刑でしょうか。ボヘミア王ヴァーツラフ騎馬像が立つ新市街の広場は、ヤン・プラフという学生が、ソ連の介入に抗議して焼身自殺したところであり、100万人に上るプラハ市民がここに集まり、無血革命を果たしたところでもある。
プラハでは多くの橋、とりわけ美しいカレル橋が掛かるヴルタヴァ川を挟んでいる旧市街や旧市庁舎の塔から眺める旧市街の景色は素晴らしいことが分かります。近郊にあるコノピシチェ城は、第1次世界大戦のきっかけとなるオーストリア皇太子が暗殺されるまで住み、狩猟の場としたところだそうな。
世界遺産のテルチはルネサンス様式とバロック様式がユニークに混合された家々が建っていて16世紀の町そのものだそうです。湖に囲まれたこの街は端に立つ中性教会の塔の上から眺めると時代錯誤を起こさせるような光景が目の前に広がるという。
チェスキー・クルムロフは日本人観光客に評判のよい中世都市。スロベニアからきた旅人が言ったという「ヨーロッパの古都で君がまず訪れなければならない街がふたつある。ひとつがクロアチアのドウブロヴニク、もうひとつがチェコのチェスキー・クルムロフだ
」と。クルムロフは「川の湾曲部の湿地帯」を意味する。ここは、クルムロフ城を含む優れた建築物と歴史的文化財で知られる。城から見える古都の景色は大変美しいそうです。
ユーモアに溢れる写真も紹介されました。スヴォルノステイ広場で出合った地元の家族とプラハ、カレル橋上での研修中らしき坊さんの写真と各々のタイトル等。 |
海外旅行研究会第22回発表会
恒例の発表会が3月19日(木)17時から行われました。今回は第22回目で、先般開催されたワイン同好会が20回目でしたから、DF同好会の中で、当会は最も活発な活動をしているグループではないでしょうか。
さて、今回は、丸山さんの「カリフォルニア、ある視点」と曽山さんの「男のロマン」と題する発表が行われました。ふたつとも謎めいたタイトルでしたが、前者の「ある視点」とは、観光というより、人類学的考察であって、興味深いものでした。後者の「ロマン」とは、クラシック・カー、SLそして帆船の3ジャンルにあり、英国その他で動画を含む写真撮影をし、モデルまで作るという曽山さん自身のロマンで、その情熱と執念には一同感服しました。おふたりともプレゼンのスキルは素晴らしいものでした。報告内容の要旨は以下の通りです(写真をクリックすると拡大できます)。
1.「カリフォルニア、ある視点」
 |
アバロン港の波止場からカタリナ島のカジノボールルームをのぞむ |
丸山氏のカリフォルニアは3度目のプレゼンとなります。
同氏は、年に2度、各1ヶ月の長期滞在を続けているカリフォルニア、サンディエゴで見聞した事の中から、今回、究極のエコリゾート、カタリナ島の様子を紹介しました。続いて、クリスマスの時期に家や街路に現れる派手なイルミネーション、家族全員が贈り物を交換し合ってお互いの健康を喜ぶアメリカ人の様子を紹介しました。また、同時期に、紀元前2世紀頃の故事を偲んで、8日間?燭の明かりを灯して、油で炒めたポテトパンケーキやドーナツを食べ、故事に由来する独楽を回す家族ゲームを楽しむユダヤ人や、娘が15歳になったら、その成長ぶりを世間に派手に披露するというメキシコ系のカトリック信者の、今も根強く残る習慣などを紹介した。
 |
 |
メキシコ系カソリック教徒に伝わるお祭り
15歳の少女が6人の侍徒を従え初めてのダンスを踊るホールに向かう |
あるユダヤ系アメリカ人一家
毎年クリスマスに記念写真 後ろに各自のネーム入りの大きな靴下をぶら下げている |
|
第21回 海外旅行研究会報告
第21回DF海外旅行研究発表会が、平成21年1月15日、DF会議室にて13名の出席者を得て開催されました。今回は、前に「モンゴル」を発表された田中健一氏(DF代表)の「エジプト紀行」とベテラン渡邊章氏の「ペナンとサラワクのリソート」が発表されました。
前者はエジプトの数多くの遺跡のみならず奥様との仲睦まじい写真を豊富に投影し、ユーモアを交えた関西弁での親しみ溢れるお話で大変印象的でした。
後者は東南アジア旅行の愛好者で、いかに安く、自由で快適な旅を楽しむかの専門家ですが、今回はマレーシアで結構贅沢なリソート・ホテル滞在を満喫してきたようでした。プレゼン技術もアニメーション効果を駆使するなど、めざましい向上がみられました。コンテンツも素晴らしく臨場感が溢れていました。
懇親会は12名参加し、恒例によりマンマミーアにて開催。田中代表を囲んでの楽しい新年会となりました。参加全員、今井世話役の独断と偏見で選んだ料理とワインを満喫し、ひとり2,100円という会計には驚嘆しました。以下は発表の概要です(写真をクリックすると拡大できます)。
1.「エジプト紀行」田中健一氏
今回は、昨年10月、日本旅行によるツアーに参加しての10日間の旅であった。ツアーには若年者が多く、田中夫妻は最高齢であった由。エジプトは東西南北の1辺1000kmの四角形をした国土で、カイロに次ぐ第2の都市アレクサンドリアが丁度鹿児島の位置にあたるという。カイロまで直行便で12、3時間の旅であるから比較的容易。さすがピラミッドの国エジプト、カイロのホテルの窓からもピラミッドが見えるという。ギーザの3大ピラミッドをはじめ、国内には無数の大小のピラミッドが散在する。5千年も昔に立てられたピラミッドは一体何であったのか、いまだに定説はないようだ。かの有名な吉村教授は、墓ではなかったという。辺りには白バイならぬ白いラクダに乗った警官が見張っているそうだ。スフインクスは、ピラミッドよりも前の時代に立てられた根拠が多く存在するという。ルクソールに入ると紺碧の空が広がり、遺跡がその美しさを一段と増していた。ここには王家の谷がり、ツタンカーメン王の墓は有名である。ここでは王宮を改造した素晴らしいホテルに滞在、偶々、ムバラク大統領の訪問を垣間見たそうだ。ナイル河の両岸には無数の遺跡が林立するので、興味のある向きには豪華客船で訪ねることが望ましい。カルナック宮殿は古代エジプトの最大の宮殿である。オベリクスの製造方法も紹介されたが、巨大な岩石から一本を切り出すなど興味深い。アスワンダム湖は琵琶湖の30倍の大きさと言われるものの、遥かに大きいという印象であったとか。最後にアレクサンドリアで見たベリーダンスは、高齢ダンサーで美しさよりも哀れみを感じたという。
|
2.「ペナンとサラワクのリソート」渡邊 章氏
マレーシアは渡邊夫妻が大好きなリゾートのひとつだそうです。今回の紹介は、英国によって開拓されたペナンからでした。英国統治時代の雰囲気を今に伝えるE&Oホテルは、同じ意味では、シンガポールのラッフルズが有名ですが、開業はE&Oが早かったそうだ。同じアルメニア人が建築したホテルで、互いによく似ていて、コロニアルな雰囲気を今でも醸し出している。次に滞在したシャングリラ・ラサ・サヤンはその昔家族旅行でたびたび訪れたところとのことで、正に大人のリゾートの雰囲気満点のところであるという。
次に訪れたサラワク州のクチンは、19世紀から開かれた都市で、首狩族が住んでいるところとのこと。たまたま遭遇したサラワク・レガッタでは、少数民族の皆さんが心の底から祭りを楽しんでいる様子だった。いまだ先進国の観光客に汚されていない地域で、素朴な人情味溢れるところとのことである。
最後はサバ州のコタ・キナバル。以前は木材関係で日本人ビジネスマンが多く滞在していたが、今は観光客ばかりで、静かな観光地となっている。数々のゴルフコースがあり、いずれも素晴らしいくゴルフ愛好者には理想的なリソートとのことであった。
マレーシア・リゾートの魅力は、第一に訪問者が欧州人主体で、落ち着いた雰囲気を今でも残しているところにあるようだ。第二に、屋台での美味しくて安いマレーシア料理の数々を堪能することができ、それらは中華料理の影響を強く受けながらも素朴なもので、香辛料も強くなく、日本人の口に合うということだ。第三は、国民は小学校から英語の教育を受けていることから、どこでも意思疎通の心配がないことだという。気楽に一流リゾート・ホテルのプールサイドで時の経過に身を委ねるように過ごすには最良のところだと力説していた。
|

 2009年版
2009年版 

















s.png)