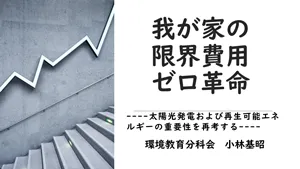2023年11月29日
2023年9月29日15:00~16:45、「太陽光発電」をテーマとして環境サロンを開催した。
参加者(対面+Zoom)は約40名。小林基昭会員(725)から「我が家の限界費用ゼロ革命」、高尾正人氏(経営支援NPOクラブ)から「太陽電池パネルのリサイクル」と題する話があった。
小林さんの話は以下の通り。
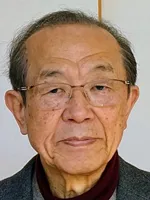
- 我が家の限界費用ゼロ革命 ~ FIT終了後のプロシューマーの実力
- 限界費用ゼロ社会と日本経済へのインパクト ~ 再生可能エネルギーの原料コストゼロの意味
- 太陽光発電はまだ拡大できる ~ ソーラーシェアリングと日本発新技術「フィルム型」太陽電池「ペロブスカイト」
高尾さんの話は以下の通り。(最初に経営支援NPOクラブの紹介があった)

- 太陽光パネルのリサイクルの現状
- 太陽光発電システムの概要
- 使用済パネルのリサイクルシステム
- パネルリサイクルの課題
以下は質疑応答・意見交換。(Q:質問、A:回答、C:コメント)
- Q(高尾)
- 小林家の「蓄電池導入後の1日の動き」を見ると、電入計19.15kWh(発電:14.43kWh、買電:2.07kWh、放電:2.65kWh)、電出計19.15kWh(売電:8.91kWh、消費:7.09kWh、蓄電:3.15kWh)とある。放電はどこで起きるのか?
- A(小林)
- 日中、一部の発電電力は蓄電池に蓄えられ、夜間、自動的に取り出されて消費される。このことを放電と言っている。太陽光発電量が過剰で消費しきれないために、捨てている訳ではない。
- Q(石毛)
- 太陽光パネルを設置してから10年の間に、部分的にパネルが故障したことはないか?産業用の大規模太陽光発電所では、部分的な故障が発生すると聞いている。
- A(小林)
- 一度も故障したことはない。パネルは20年メンテナンスフリーであり、20年補償である。
- Q(河井)
- 現在住んでいるマンションの3年後の大規模修繕工事時に、ペロブスカイトの設置を考えている。ペロブスカイトは近年急速に開発が進み注目されているが、どんなネガティブ要素があるのかを知りたい。小林家の太陽光パネルは普通のパネルだが、今まで問題はなかったか? 1日2回発生する瞬断時に、電気製品が故障するようなトラブルはなかったか。
- A(小林)
- 問題は全くなかった。本当のメンテナンスフリーで、何もやっていない。
- Q(高尾)
- 角度によっては隣家に光が反射して眩しくなるトラブルが発生すると聞いたことがある。そのようなことはなかったか?
- A(小林)
- なかった。
- Q(高尾)
- パネルの経年変化はどうか?
- A(小林)
- 日照時間が減少した年もあったが、発電量はそれ程減少しなかった。1年目の発電量は5100kWh、10年後の発電量は4600kWh、10年間の平均発電量は4800kWhであった。発電量は10年経ってもそれほど落ちない。ただ、「20年経つと発電量は落ちてきているようにも感じる」と聞いたことがある。
- Q(高尾)
- 因みに太陽光パネルは日本製か?
- A(小林)
- 中国のSUNTECH製だ。
- Q(河井)
- 九州電力は太陽光発電の出力制御を行っている。(注:10kW以下は対象外)東京電力はどうか?
- A(小林)
- 今まで出力制御はなかった。これからはあるかもしれない。ただ、家庭の太陽光発電は出力制御の対象外である。
- C(石毛)
- 太陽光発電が大量に導入されている九州では、需給バランスをとるために出力制御が頻雑に行われている。中部電力、関西電力でも太陽光発電の出力制御が始まっている。(注:家庭用太陽光発電は対象外)
- C(中西)
- 「再生可能エネルギーの最大の強みは原料コストがゼロであることで、初期投資回収後の再エネ発電の限界費用はほぼゼロである。これは化石燃料発電や原発では絶対に到達できない強みである。」という小林さんの指摘は大変重要だと思う。太陽光発電・洋上風力発電はこれからも大幅な発電コストの低下が見込まれている。日本の脱炭素社会への取り組みにとって、これらの国産再エネ電力を使用してグリーン水素を生産することが重要と思っている。皆さんの御意見を伺いたい。
- Q(小林慎)
- 太陽電池のシリコンウエハーは、珪石を電気炉で還元して金属シリコンを作り、それを結晶化して製造する。電気炉は電気を大量に使用するので、CO2が大量に排出される。結晶化の工程でも大量の電気が使用される。ジェレミー・リフキン(「限界費用ゼロ社会」の著者)の言う限界費用には、このようなコストが全部含まれていて、トータルとして太陽光発電や風力発電は、化石燃料発電や原発よりも優位性が高いと言っているのか。
- A(小林)
- 良く分らないが、そこまで遡って計算していないと思う。
- C(高尾)
- 再エネ発電は本当に環境にやさしいのかという問題である。ライフサイクル・アセスメント(LCA)が重要である。
- C(中西)
- 太陽電池のシリコンウエハーの製造に大量の電気が使用されCO2が大量に排出されるが、再エネ電力を使えば問題はない。
- A(小林)
- 燃料費がゼロである太陽光発電は、初期投資の回収後、限界コストはほぼゼロになる。長い目でみれば化石燃料発電より太陽光発電の方が安い。
- C(中西)
- 現時点では安い再エネ電力をいつでもどこでも必要なだけ手に入れることはできない。しかし、それを目指す方向性をもったエネルギー政策が大事だ。今はそれが見えない。
- C(山田)
- 太陽光発電のLCAは厳密になされているはずである。ヨーロッパでは小麦由来のバイオエタノールが製造されているが、小麦を育てるところから、小麦糖液を発酵させてエタノールを作るまでの全過程を含めたLCAがなされている。
- C(高尾)
- そこまで踏み込まないと客観的な評価ができない。
- C(石毛)
- 原子力発電はその最たるものだ。
- Q(石毛)
- 高尾さんの話を聞いて太陽光パネルの廃棄処分は、プラスチックの廃棄処分と同じと感じた。ところで、東京都は新築住宅に太陽光パネルの設置を義務付けたようだが(注:2025年4月から義務化)、リサイクルのPDCFA (Plan、Do、Check、Feedback、Action)はできているのか。
- A(高尾)
- 東京都は色々検討している。しかし、十分検討して大丈夫とはなっていない。処分場も東京都ではなく、茨城県に設置するようになっている。新築住宅に太陽光パネルの設置を義務付けたのも見切り発車である。
- Q(山下)
- 自宅に設置した太陽光パネルが20年過ぎて処分する場合、何処に依頼すれば良いのか。また、その処分費用は何処が負担するのか。
- A(高尾)
- 太陽光パネルの使用中に故障等でリプレースする場合、パネルの販売先が責任をもって処理することになる。太陽光パネルが何らかの理由で地面に落ちてしまった場合は、一般廃棄物として個人が処理しなければならない。一般廃棄物は市町村が管理しているので、市町村の指示を受けて廃棄物処理業者へ持っていくことになる。太陽光パネルには有害物が入っているので、個人で勝手に処分できない。(処理業者は産業廃棄物として処理するが)太陽光パネルの撤去、運搬、廃棄には15万円位かかる。場合によっては100万円かかると言う業者もいる。
- Q(中西)
- 「太陽光パネルのリサイクルを推進する法律がまだきちんとできていない」とのことだが、拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility: EPR)という概念がある。パネルの製造者は①リサイクルし易いように設計を工夫する、②パネルの材質の表示を行う、③パネルの製造者自らが引き取りやリサイクルを実施するなど、製造者はリサイクルや処分に一定の責任を負うという考え方だが、この点、日本の現状はどうか。
- A(高尾)
-
難しい質問だ。(太陽光パネルのリサイクルの議論は始まったばかりであり)、はっきりしたことは言えない。パネルメーカーは有害物質情報を公表しなければならない。太陽光発電協会は有害物質を開示しているメーカーを公表しているが、そのメーカーのホームページに行ってもその情報がなかなか見つからない。(EPRの一形態として)情報公開が一番の問題と思っている。(参考資料:「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルについて」資源エネルギー庁、2023年4月
https://www.env.go.jp/council/content/03recycle03/000129236.pdf
)
- Q(中西)
- 中国のパネルメーカーの情報開示はどうなっているのか。
- A(高尾)
- どこまでやっているのか、詳しいことは分らない。(参考資料:IEA Report “Status of PV Module Recycling in Selected IEA PVPS Task12 Countries 2022”; https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/09/Report-IEA-PVPS-T12-24_2022_Status-of-PV-Module-Recycling.pdf )太陽光パネルは日本製が良いと思っているが、中国もしっかりした品質のものを作っている。(ただ、リサイクルへの取り組みはこれからだ)
- C(中西)
- 世界最大の太陽光発電導入国である中国では、廃棄される太陽光パネルも多い。 それらの中にはまだ使えるものもあり、低開発国に輸出されている。太陽光パネルの廃棄物処理・リサイクルは大きな問題だ。
- C(石毛)
-
蓄電池の廃棄はもっと大きな問題になる。
参考資料:「第1回 蓄電池のサステナビリティに関する研究会」2022年1月21日 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chikudenchi_sustainability/pdf/001_04_00.pdf - Q(河井)
- 使用済太陽光パネルは排出・解体され、リユース/リサイクル/埋め立て処分になるが、ペロブスカイトは解体しないで再利用したらどうか。そういう研究はされていないのか。
- A(高尾)
- ペロブスカイトは日本では実証試験段階でまだ実用化されていない。まだそういう研究はされていない。ペロブスカイトは桐蔭横浜大学の宮坂力教授が発見したが、海外特許は取得していない。世界中でペロブスカイトの研究開発が進められているが、中国が一番進んでおり、既に大量生産段階に入っている。
- Q(小林)
- リユース/リサイクルの処理の仕方で、新しいやり方は出てきていないか。
- A(高尾)
- 特にそのようなものは見ていない。
- Q(石毛)
- パネルのガラスのリサイクルは難しいものなのか。
- A(高尾)
- 色の違うガラスが混ざると難しい。ヨーロッパでは分別、回収、処理が出来ている。日本はまだそこまで行っていない。
- Q(中西)
- 「水田で太陽光発電を行うソーラーシェアリングによって、農家は4倍の所得増になる。ソーラーシェアリングは日本農業再生の可能性がある。」との話があったが、そのような実例はあるのか。
- A(小林)
- 実例は結構ある。千葉県の匝瑳市では耕作放棄地を利用し、市民が中心となって合同会社を作りソーラーシェアリングをやっている(匝瑳第一市民発電所1MW:ソーラーパネルの下地に大豆や麦などを作っている。) https://agrijournal.jp/renewableenergy/37506/ 日本の農地(440万ヘクタール)の5%をソーラーシェアリングすれば、日本の消費電力の2割位賄える。(注:耕作放棄地は耕地面積の約10% 42万ha)
- C(石毛)
- JAはもっとソーラーシェアリングの旗振りをやったらどうか。(注:JAバンクはソーラーシェアリングを支援: https://www.nochubank.or.jp/efforts/newsletter/023/feature1/ )
- C(小林)
- カーボンニュートラルの実現には、太陽光発電の導入量を現在の64GWから320GWへ増やす必要があると試算されている。私の試算だが戸建て住宅の40%に太陽光パネルを設置すると46GW、耕作放棄地と農地(全農地の5~10%)のソーラーシェアリングで210GWが得られると試算している。
- Q(河井)
- ペロブスカイト太陽電池の原料のヨウ素は日本に豊富にあり、三井化学が生産していると聞いたことがある。詳しいことを知りたい。
- A(小林)
- 日本はヨウ素の生産世界第2位である。
- A(中西)
- 千葉県の茂原、大多喜周辺に水溶性ガス田がある。天然ガスを含んだ地下水にはヨウ素が含まれており、関東天然ガス開発(株)(一時期、三井東圧(現三井化学)が筆頭株主)が副産物として生産している。
- Q(山田)
- 経営支援NPOクラブには、新素材研究会などの支援研究会があるが、どのような活動をしているのか。
- A(高尾)
- 車のEV化には車両の軽量化が必要であり、新素材研究会は車両の軽量化に対応する新素材の動向調査に取り組んでいる。
- C(小林慎)
- 経営支援NPOクラブが素晴らしいのは、支援する会社があることだ。DFの環境部会は環境の勉強をしているが、それがない。
- C(小林健)
- 日本の場合、太陽光発電は脱炭素の切り札である。商社勤務時代、日本の太陽光発電導入の初期、国内ではパネルが大量に売れないので、ドイツに輸出していた。輸出すれば量がはけるのでそっちに出て行った。どうして国内で売れないかというと、当時の政府の考え方と補助金の出し方に問題があったからである。ドイツの補助金制度はすっきりして分かり易かったし安心できた。しかし、日本の当時の補助金制度はちまちましていて、どうしようもなかった。いまだにそのへんはネックになっている。風力発電についても、今回汚職の話があって色々裏をみてみると、全部政治が壊していると思っている。そこが変わらない限り、日本の再エネ政策は全然進まないと思う。この20年間化石燃料と減らしましょうと言い続けているが、ほとんど減っていない。このような状況に諦めてしまっている。批判しても前向きでないので、皆で纏まって声を出さないといけない。そうこうしている内に中国は強大になり、北朝鮮は勝手なことをやっている。このままでは日本そのものが潰されてしまうという危機感をもっている。
- C(小林)
- 政治は本当にダメだと思う。
- C(中西)
- 同感だ。ただ、諦めてはいけないと思っている。我々環境部会は大学で環境の講義をしている。小林健さんが提起されたような問題を学生に伝えたいと思っている。環境部会に入会し、小林さんから直接学生に話をして頂ければ有難い。
- C(石毛)
- 今の話は良く分る。エネ庁の仕事をしているが、単年度制度で成果が残らない。その点に一番イライラしながら、仕事をしている。政府は税金の無駄使いをしている。
以上(中西 聡)