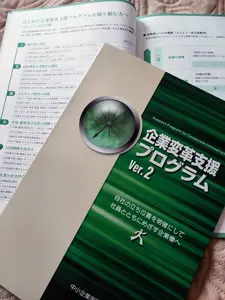中小企業は社会の主役
「中小企業憲章」(2010年閣議決定、以下「憲章」)前文には、「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である」とあります。実際、企業数の99.7%を占め、民間の雇用の7割を中小企業が担っています。
実はこの「憲章」、私が36年7ヵ月働いてきた「中小企業家同友会全国協議会」(以下、中同協)が国に要望・提言し、実現したものですが、現在も引き続き「国会決議」となるよう要望しています。
中小企業家同友会全国協議会とは
中同協は中小企業家同友会(以下、同友会)の協議体として5つの同友会と2つの準備会によって1969年に設立されました。同友会は、それより12年早く1957年に東京で日本中小企業家同友会として創立されており、2005年に秋田に同友会ができてすべての都道府県に同友会が設立され、現在では47都道府県47,000名を超える組織となっています。
中小企業が主に組織された経済団体としては、「商工会議所」「商工会」「中央会」などがありますが、同友会は自主・自立の理念団体として、会費と入会金で運営されている任意団体(一部「一般社団法人」もあり)です。
https://www.doyu.jp/
理念は
-
「三つの目的」
(よい会社をつくろう、よい経営者になろう、よい経営環境をつくろう) -
「自主・民主・連帯の精神」
-
「国民や地域とともに歩む中小企業」
の三つで構成され、中小企業家が自主的に参加し、手作りの運営を心がけ、中小企業家のあらゆる要望にこたえて活動するという特色があります。政治に対する同友会の姿勢は、会の目的を達成するために、どの政党ともわけへだてなく接触しますが、会としては特定の政党と特別な関係をもたないようにしています。会員個人の思想・信条の自由は当然のこととして保障されています。
同友会の基礎組織である支部や地区は全国で500を超え、会員の経営体験報告とグループ討論を柱とした月例会を中心に活動しており、例会は年間6000回ほど開催されています。
「人を生かす経営」~経営姿勢の確立に「労使見解」
企業づくりでは、「中小企業における労使関係の見解」(労使見解、1975年発表)を学んで経営姿勢を確立し、「経営理念」「10年ビジョン」「経営方針」「経営計画」の四つからなる「経営指針」の成文化と実践に向けた活動が軸です。
「社員教育」「共同求人」「障害者雇用の促進」「異業種交流(企業連携、産官学連携)」など、総合実践にも積極的に取り組んでいます。
原点となる「労使見解」は、「経営者の責任」を最初の項で問いかける5,000文字ほどの文書ですが、私がこの団体に確信を持った文書でもあります。中小企業は経営資源の中でも「人の成長」に依拠して発展するものであり、そのことを重視した「人間尊重経営」を推進する会の気風が確立されている基本文書ともなっています。
なかでも「経営者としてやらねばならぬことは山ほどありますが、なによりも実際の仕事を遂行する労働者の生活を保障するとともに、高い志気のもとに、労働者の自発性が発揮される状態を企業内に確立する努力が決定的に重要です」と言い切ったところに潔さを感じるとともに、企業側だけの努力では経営環境は変えられないが、社員や労働組合との連携でそれも変えていこうと連帯を呼びかけるものでもあります。
いまでは、「労使見解」を同友会がめざす企業像の「人を生かす経営」として、具体的に「企業変革支援プログラム」にまとめられ、広く活用されています。しかし、このプログラムを作る2007年には全国から15名ほどの優れた経営実践を行っているメンバーでプロジェクトを組んだものの、「セルフアセスメントとはいえ経営を点数評価するのか」「中小企業に標準化した経営スタイルは当てはまらない」など、反対意見も多く、試験運用も2回行うなど全国的に理解を求めるのに2年を超える月日を要しました。今では改訂版として Ver. 2 が昨年10月にリリースされ、すでに5,000部を超える普及数となっています。
中小企業の経営環境を改善するために
「よい経営環境」という点では、「国の政策に対する中小企業家の重点要望・提言」を毎年発表。また、コロナ禍で「中小企業の倒産・廃業を避け、雇用と日本経済を守るために~新型コロナウイルスに関する緊急要望・提言」を10次まで発表し、国会各政党や中小企業庁、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会(連合)、全国労働組合総連合(全労連)などとも懇談してきました。
2012年から事務局長を務め、2020年には政策広報局長として対外活動を軸に、これまで定期的な懇談の機会がなかった中小企業団体や金融機関の全国組織(金融庁、全国銀行協会、地方銀行協会、第二地銀協会、信用金庫中央協会、全国信用組合協会)との懇談を、定例化し中小企業を取り巻く経営環境の改善に向け、連携と協力への理解を求めました。
事務局長時代には全国組織の経済団体では初の女性局長ということもあって、国連や内閣府、中小企業庁、労働団体、女性団体での報告の機会がえられ、中小企業の魅力や同友会の活動を知らせることで対外的な糸口をつかむことができ、その後の対外活動もスムーズに進んだものです。
金融問題は死活問題
金融問題では、1990年代末には「金融検査マニュアル」の一律適応で、融資における物的担保優先主義に陥っていた金融機関による「貸し渋り」や「貸しはがし」が横行し、将来性のある企業が定量評価のみで厳しい状況に追い込まれることに矛盾を感じ、「どうなる金融~不良債権処理最終処理」「どうなる金融~信金再編の余波」などの連載を執筆し、金融機関や中小企業、金融庁などの取材に入りました。中同協としては「金融アセスメント法制定運動」として、100万署名、1,000を超える自治体決議を集めました。
「どうなる金融~不良債権処理最終処理」
https://www.doyu.jp/finance/report/series.html
「どうなる金融~信金再編の余波」
https://www.doyu.jp/finance/report/shinkin.html
取材では金融機関がバブル期に物的担保や経営者保証などで融資をすすめたことで、目利きが育っていないことや、金融庁の査定に対し、金融機関が一律の貸倒率などに意見を出せる人材がほとんどいないことなどで金融機関も中小企業も追い込まれている状況が起きていました。それは10年後に「倍返し」で一世風靡したドラマにも描かれています。
「地域と中小企業の金融環境を活性化させる法律」(金融アセスメント法)は、円滑な資金需給や不公平な取引慣行(物的担保優先、連帯保証など)の是正などを軸として金融機関の自主的な取り組みを事後的に評価し、収益本位に流れがちな金融機関の資金配分を地域経済や中小企業に向けさせる仕組みの法律のことです。
その後、この活動が政策的に反映され、「経営者保証ガイドライン」の策定や「経営者保証改革プログラム」につながっています。また、中小企業の声を国の政策に具体的に反映できることを経験し、EU視察を通してEU小企業憲章にならい、日本にも「中小企業憲章」を策定しようと会内の学習活動を行い、国に要望・提言し、政権交代と同時に「中小企業憲章」の閣議決定となりました。
「経営者は孤独」ではいけない~地域の重要な人材
経営の悩みは社員にも取引先にも話せない「経営者は孤独」といわれます。しかし、一番の相談相手は先輩経営者であるとの調査結果もあり、同友会では「謙虚に学ぶ」「本音で語り合う」ことで、自らの経営姿勢を確立し、具体的な経営課題の解決へ向けた対応を同友会で学んでいます。会員である経営者の皆さんは企業規模や業種など分け隔てなく議論し、事務局をパートナーと位置づけ、共に学びあう場を積極的に提供するよう工夫しています。
中小企業の経営環境は常に厳しい状況にあり、日本の経済だけでなく社会を支える中小企業がもっと政策的にも重要視されるべきですが、現実は不公正取引や優越的地位の濫用、中小企業への社会的認識の低さ、中小企業自身に課題があるのも事実です。しかし、中小企業経営者は単なる企業の経営だけでなく、地域においてはPTA会長や祭りの実行委員長となり、人として企業としても地域社会や文化を支えています。
長く中同協に勤めて、優れた経営者に巡り合うことも多く、社員の家族にまで思いをはせ、自社の課題だけでなく、地域や日本の課題に積極的に問題意識を持ち、かかわる姿は、その地域を支える重要な人材であることを痛感するものでした。
コロナ禍での中小企業家の奮闘と教訓を研究者などとまとめた「ポスト・コロナ研究まとめ」にはその一端がまとめられています。
ひらた みほ(1428)
(中小企業家同友会全国協議会 前事務局長)
(理科実験G、地域社会デザインプロジェクト)