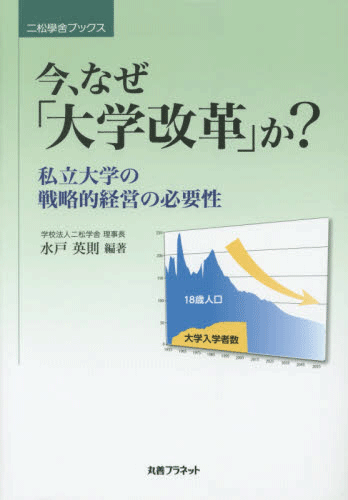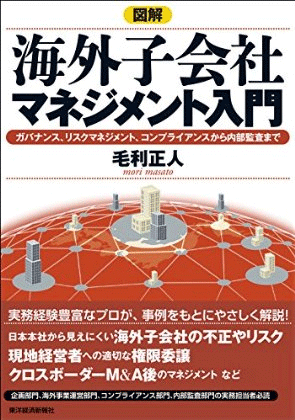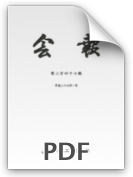2015年2月23日
 活躍するDF会員
活躍するDF会員
- 著書リスト
- 活躍するDF会員
 活躍するDF会員(2014年版)
活躍するDF会員(2014年版)
*自薦、他薦は問いません。近くで活躍されているDF会員をご紹介下さい。
(最終更新日: 2015年2月23日 / 記事の掲載順)
(敬称略)
| 会員名 | 掲載日付 | タイトル |
|---|---|---|
| 水戸 英則 | 2014年09月30日 | 水戸 英則さんが著書を上梓されました |
| 毛利 正人 | 2014年07月28日 | 毛利 正人さんが著書を上梓されました |
| 今井 祐 | 2014年07月06日 | 今井祐さんが著書を上梓されました |
| 林原 行雄 | 2014年05月19日 | 林原行雄さんが共同編著者として著書を上梓されました |
| 熊野 隆喜 | 2014年02月13日 | 熊野隆喜さんが、理科実験について記述されました |
| メンバー | 内容 | |
|---|---|---|
 水戸 英則 氏 |
水戸 英則 さんが著書を上梓されました現在、学校法人二松学舎理事長で会員の水戸 英則さんが「今なぜ『大学改革』かー私立大学の戦略的経営の必要性」と題する本を丸善書房から出版されました。
【おすすめコメント】 金融界から教育の世界に入った筆者がこれまで推し進めてきた「大学経営・教育改革の経緯」と、その中で触れてきた多くの私立大学に関する文献、同経営・教育改革等の資料を系統的に組み直した大学改革の参考書! 中小規模の私立大学が進めるべき「改革」とはどんなものなのか。「改革」を考える上での基礎知識となる、日本の大学の歴史、大学経営を取り巻く環境の変化などのまとめから、具体的な打ち手の事例までが網羅されている。(E-hon より) ⇒ 丸善書房のちらし |
|
 毛利 正人 氏 |
毛利 正人さんが著書を上梓されました元有限責任監査法人トーマツのディレクターで、現在、クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング(株)代表取締役社長の毛利正人さんが、「図解 海外子会社マネジメント入門 」を出版されました。海外子会社をいかにマネジすべきかは、多くの日本企業の重大な課題です。 本書では、海外子会社の不正やリスク、現地経営者への適切な権限委譲、クロスボーダーM&A後のガバナンス導入などの経営者の関心の高いテーマが、豊富な事例をもとに判り易く解説されています。
【主な内容】 日本企業のグローバル化とビジネスモデルの変化 海外子会社に対するガバナンスの導入(手法、体制、デザインと導入) 海外子会社におけるリスクマネジメント・コンプライアンス活動の展開 不正の予防、早期発見のための内部統制と内部通報制度、内部監査 など |
|
 今井 祐 氏 |
今井 祐さんが著書を上梓されました元富士写真フイルム(株) 副社長で、現在、日本経営倫理学会理事兼 監査・ガバナンス研究部会長をされている今井祐さんが、「経営者支配とは何か: 日本版コーポレート・ガバナンス・コードとは 」を上梓し、単行本(349ページ)として出版されました。 我が国では、事実上、経営者支配が株主総会支配にまで及んでいるのではないかといわれていますが、本書は経営者支配のあるべき姿について「経営者支配の正当性付与の条件」また、本年2月に金融庁が定めた「日本版スチュワードシップ・コード」に基づき準則「日本版コーポレート・ガバナンス・コード案」を提言し、これらが「なぜ必要か」が解説されています。
【主な内容】 フィルムの巨人 コダック社の凋落の真因 米国ゼロックス社の快挙 JALの再生に見る、稲盛経営哲学の普遍性 「川崎重工」社長解任事件 オリンパス社長解任事件 等13事例研究 所収
|
|
 林原 行雄 氏 |
林原行雄さんが共同編著者として著書を上梓されました
シティグループの監査役の傍ら東洋大学客員教授を務める林原行雄さんが、担当する「PPPビジネス論」における外部講師の講義録をまとめて、共同編著者として著書「PPP が日本を再生するー成長戦略と官民連携」を出版されました。アベノミックス「第3の矢」である成長戦略の中で、今後10年間に12兆円規模の PPP/PFI 活用を実行に移すことが明らかにされ、PPP(Public - Private Partnership-官民連携)が俄に注目されております。本書は「民間活力の爆発」をキーワードとして、PPP ビジネスに携わる経営者が、それぞれの業界の現状と課題を鋭く分析し、日本再生のための施策を熱く提言する好著です。
|
|
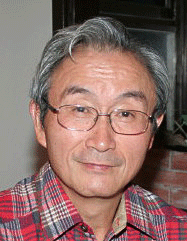 熊野 隆喜 氏 |
熊野隆喜さんが、理科実験の紹介を記述されました
熊野隆喜さんが、一般社団法人日本工業倶楽部の会報第247号(平成26年1月発行)にディレクトフォース理科実験についての紹介を記述されました。 前半のロータリークラブの青少年奉仕活動に続いてご覧下さい
|
|