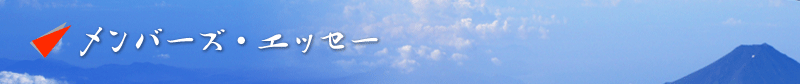
- メンバーズ・エッセー
- 「目 次」
2014/12/16(No187)
「今なぜ大学改革か 私立大学の戦略的経営の必要性」出版にあたって
水戸 英則
 わたしは、昭和44年日銀に入行、35年の金融界での生活の後、平成16年に教育の世界に入りました。入った理由は、地方勤務時に地元私立大学で、金融論の非常勤講師を経験する機会があり、大学教育の大切さ、重要性を身に染みて感じたからです。
わたしは、昭和44年日銀に入行、35年の金融界での生活の後、平成16年に教育の世界に入りました。入った理由は、地方勤務時に地元私立大学で、金融論の非常勤講師を経験する機会があり、大学教育の大切さ、重要性を身に染みて感じたからです。
さて「今なぜ大学改革か」ですが、これは、昨年初、第2次安倍政権において内閣府に設置された教育再生実行会議で、少子化に伴うわが国18歳人口の減少に伴う労働力減少が、今後我が国国力の減衰に繋がりかねないとの懸念もあり、労働力の大層を占める大卒層が、これからの我が国の土台を支える労働力であり、「大学力は国力である」(安倍総理大臣)との指摘もあって、国民の大学改革への認識の高まりがみられています。このような状況下、再生実行会議では、今後大学教育において、グローバル人材、イノベーション創出人材の育成を求め、高等教育に対する国の予算措置等を通じて、大卒層の質・量両面の引き上げのため、国公私全大学の教育・経営両面の全般的な改革を並行して進めていく必要がある、との提言を公表したことに由来します。
さて、我が国大学総数は現在国公私合せて784大学あり、その内私立大学は、606大学と総数の約7割強、また大学在籍者総数280万人の8割(216万人)を占めるなど、高等教育の約8割を担っており、日本の「分厚い中間層」を支える土台を構成しています。しかしながら18歳人口の急減、大学進学者の激減の進展等から定員を充足出来ない私立大学が、606大学の内46%(290大学)に上っており、とくに地方所在の私大経営は厳しいものがあり、経営・教育両面の改革を行わざるを得ない構造的な圧力に晒されるなど、大きな転換点を迎えつつあります。
従って、先ず教育改革については、これまでの大学教育が、基礎・専門知識を、一方通行的に行う教育から、理論面に加え実態面の事象を関連付けて教えるなど、双方向・課題解決型授業やアクティブラーニング等学生が主体的に学べるような教育に変えて行くことが必要となっています。さらに、グローバル化や知識基盤社会化、ICT化が進み、社会の価値観が目まぐるしく塗り替わる現在、学生はこうした動きを主体的に学びたいというニーズがあり、これらニーズを教育内容に加味して行く必要があります。言い換えれば、教育はいわゆる「マーケットイン」の考え方で、変化する環境に適応できる教育を行っていくことが肝要であり、この結果、学士課程4年間で、基礎・専門知識のほか課題解決力、想像力、構想力、社会的責任能力等社会を生き抜く力を身に付ける教育を行うとの観点で、改革を推進していく必要があります。
また、経営改革については、従来型の学校経営に、例えば企業経営の原則、「強いガバナンス」「マーケットインの考え方」「情報公開(ディスクロージャー)」「公共性・地域性」を、織り交ぜながら、新しい大学経営の形を構築していくことが必要と考えられます。
こうした環境下、わたしはこの10年間、経営改革面では、企業経営の原則を学校経営に応用できるところは導入するなど、各種試みを行ってきました。本書はこの間の経緯を、内外の講演、研修講話録を元に書き記したものです。また同時に、文部科学省国立大学法人評価委員会委員、同分科会委員・同専門員、私立大学協会監事などを兼任、文部科学省をはじめとする諸機関から発出されている多くの私立大学に関する文献、同経営・教育改革等関連資料に触れる機会も多く、本書では、これら資料を系統的に組み直しつつ引用、掲載することに努めました。
本書により、大学改革ならびに私立大学への理解を深め、同時に学校経営・教育両面において改革を進めるに際し新たな何らかの示唆を与えることが出来れば幸甚です。![]()
みとひでのり ディレクトフォース会員(会員No.774)
現 学校法人 二松学舎 元日本銀行
![]() 編集註:本書に関しては、著書の紹介ページ「活躍するDF会員(2014年版)」を併せご覧ください。
編集註:本書に関しては、著書の紹介ページ「活躍するDF会員(2014年版)」を併せご覧ください。
