
( 2016年9月9日 掲載 )
第165回 講演・交流会(2016年8月例会)
テーマ:『英国EU離脱へ!激動する欧州はどこへ行くのか』
講 師:熊谷 徹氏(在独ジャーナリスト、元NHKワシントン特派員)

8月30日(火)台風10号の影響で前日まで開催が危ぶまれていましたが、当日はその影響も特になく学士会館にて109名の参加者を得て165回目の講演・交流会がドイツ在住26年のジャーナリストであり、元NHKワシントン特派員の熊谷徹氏による『英国EU離脱へ!激動する欧州はどこへ行くのか』と題するテーマで開催されました。
恒例の保坂事務局長による講師の経歴紹介に続き、熊谷氏の講演が始まりました。
昨年から今年にかけてのヨーロッパの変化は、例えばISによるフランスでのテロなどを挙げ、過去に類を見ないものであり、ヨーロッパに在住しているという視点からのレポートであるとの前置きがありました。
概要は以下の通りです。
◇ ◇ ◇
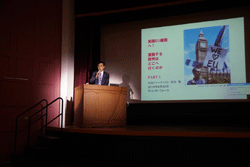
|
1.英国EU離脱派勝利の衝撃
BREXIT(BritainとExitの合成語。イギリスのEU離脱)の衝撃はベルリンの壁崩壊に匹敵するものです。投票直前残留派の要人が殺され残留となると考えられていましたが離脱が決定されました。BREXITもベルリンの壁崩壊同様、政府が抑え込めない庶民の力、非理性的な力を背景としていたため、今後の展開を予測することは極めて難しいものがあります。
欧州のエリートたちが、庶民不在で進めてきた政治統合・経済統合に庶民の不満が噴出したものと言えます。国民投票の結果は、「ヨーロッパ統合」に関する意識が、エリート層と庶民の間でいかにかけ離れているかをはっきり示しています。反EU勢力は、英国以外にも居り、職が奪われる等の危惧をもっておりグローバル化に懸念を抱いていますので同様の国民投票を実施する可能性があります。
BREXITの主な理由は、英国が最も重視する下記2点を満たしていないことにあるようです。
- Accountability of politician(政治家の説明責任)
- Sovereignty (主権性)
最も離脱を望んだのは、中高年層の有権者でありました。65歳以上60%、55歳から64歳57%に対し18歳から24歳27%が離脱支持をしたという調査結果があります。
英国経済にとって、EU離脱による短期的な利益がないという経済的合理性に反して感情論が勝ったようです。英国は、今後ノルウェーやスイスのようにEUとの個別交渉によって、関税の適用を免れようとしますが、英国とEUの貿易のためのコストがこれまで以上に増える可能性は残ります。
2.中東動乱と難民危機
2001年ドイツでは、難民を拍手で迎えいれましたが今や大問題になっています。ドイツでは、ナチスの負の遺産から、亡命権を認めているため、難民を受け入れています。
2015年9月に、EU加盟国は、ギリシャとイタリアに到着した難民16万人を人口、GDP、失業率に応じて各国に配分することを決めました。反対した東欧諸国は、多数決で押し切られたが実際に配分されたのは、2016年2月の時点で1,000人に満たない状態です。東欧諸国は、メルケル首相が一方的に難民受け入れを決めたために、シリア難民の亡命意欲を高め、難民流入数を増加させたと批判しています。難民受け入れの不均衡状態や国家エゴがむき出しになることによって欧州の連帯は崩壊しています。
ドイツの2015年の定住移民の内、最多はシリア人です。シリア内戦の見通しについては悲観論が強いのが現状です。シリア内戦が終わらない限り、難民危機は終わりません。
また、無差別テロ等の少なかったドイツでも発生し始め治安の悪化がしています。シリアやイラクでISが劣勢であり、身元チェックが甘いので難民に紛れ込んでテロリストが入り込みヨーロッパで活動をしています。このためパリでは、日本人や中国人観光客が減少しています。
ヨーロッパでは、イスラエルと同じように生活の仕方を変えることはテロに負けたということになるので今迄と変わりない生活を送っています。ヨーロッパが、イスラエル化しているようです。
3.右派ポピュリズムの高まり
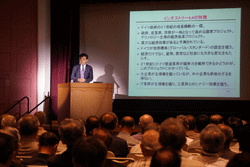
|
フランスには極右派のフロン・ナショナール(国民戦線)が2015年12月の地方議会選挙・第1回投票で勝利しました。英国のEU離脱は影響が少ないが、フランスが離脱した場合、EUの崩壊に結び付きます。ヨーロッパでは、反EUの動きがあり、難民対策は生ぬるいとのアンケート結果があります。
ドイツ語圏でも右派政党が躍進しています。EUに反対もしくは、EUに懐疑的な政党の比率が高まっています。EUの危機は、各国に格差があることです。今後EUをどのように改革してゆくかが鍵になります。欧州ポピュリスト政党は反イスラム、反グローバリズム、反EU移民の制限を求める等の共通点があります。
4.東西冷戦の再燃
ロシアによるクリミア併合以降NATOとの関係は悪化しています。欧州では「東西冷戦の再来」を危惧する声が強くなっています。プーチン大統領は、『ゴルバチョフの失策により、ロシア国外に2,500万人ものロシア人が取り残された。彼らの運命を偶然に任せることはできない。クリミアだけではなく、カリーニングラード地域も然りだ』と発言しています。クリミアの次の目標は、ロシア系市民が多数在住しているバルト三国の併合ではないかと思われます。このためスバルキ・ギャップ( ポーランドのスバルキ(Suwalki)の東にある長さ70kmほどの国境線によって、ポーランドは、リトアニアと直接領土を接し、この狭い「間隙」(ギャップ)の北西端はロシアの飛び地カリーニングラードに接し、南東端はベラルーシに接している。)が注目されるようになっています。
ドイツでは、ロシアによるサイバー攻撃に備え、10日間の水・食料の確保をしています。
5.ドイツの比重
ユーロ危機にもかかわらず、ドイツは好況なのは、2003年にドイツのシュレーダーが断行した、社会保障・雇用市場改革プログラム「アゲンダ2010」によって、ドイツは労働コストの伸び率を、EUで最も低い水準に抑えることに成功したことによります。ドイツは、ユーロ危機で過重債務に苦しむ国に対し、自らが実行できたので構造改革、規制緩和と緊縮策を要求していますが、南欧は反発しています。
6.Industrie4.0
ドイツは、21世紀の成長戦略として、Industrie4.0というプロジェクトに取り組んでいます。ドイツのものづくり産業では、製品のノウハウをソフトウェア化し、3Dプリンターを活用し生産コストの安い地域で生産する方式をとっています。即ち工場生産のデジタル化です。このことはあまり日本のメディアでは注目されていません。
質疑応答

|
- 質問:ドイツは中国をどのように観ていますか?
- お答:ものづくりの観点から、モータリゼーションのマーケットとして観ています。両国間には歴史的領土問題もなく、また、ドイツは、あえて中国の人権問題に関し過去には苦言を伝えていたが、現在は苦言を挟まないようになっています。
- 質問:英国と欧州との関係は
- お答:BREXITによる経済的損失を最小化するよう努力はするが、EUが甘い対応をすると離脱を促進することになるので、メンバーが離脱すると不利益を被ることを示すでしょう。
- 質問:プーチンの最終目標は
- お答.ロシア系住民が不都合を感じさせない様な対策をとるでしょう。ロシアは、外敵からの侵略にトラウマ的脅威を感じており、NATOの東方拡大が、ロシアの虎の尾を踏んでしまったようです。
EUの結束を脅かすため、フロン・ナショナール(国民戦線)への資金援助やトルコにNATOから分離するよう働きかけをする等です。 - 質問:日本はドイツに何を学べばよいでしょうか
- お答:ドイツは、ナチスを批判的に理解し、歴史的に真摯に取り組んできたことが近隣諸国に認められてきました。日本も歴史に真摯に取り組むことが必要です。
- 質問:ドイツの技術に関して日本の重厚長大産業はいじめられてきているがドイツはどうですか
- お答:ジーメンスも痛めつけられています。人件費が高いので付加価値の高いもの=知識に特化せざるを得ません。価格競争に巻き込まれない、他メーカーが必要とする分野に特化しています。IoTがキーワードです。
- 質問:フォルクス・ワーゲンの不祥事のようなことは再発する可能性はありますか
- お答:フォルクス・ワーゲン社は、従業員60万人(内4万人が技術者)の大企業であり、この不祥事は大企業の金属疲労がもたらした大企業病と考えることができます。ドイツでは、99%が従業員500人以下の家族経営の中規模企業のため再発の可能性は低いです。
- 質問:ロシアとの冷戦構造について
- お答:日本政府とロシアとの交渉が興味深いものがあります。プーチンは、西側同盟国が離散することが好ましいと考えているため日本に接近してきます。
◇ ◇ ◇
講演終了後保坂事務局長により下記の新入会員の紹介がありました。
 |
| 写真左から(敬称略) 大﨑鼎(1128)正木尚(1133)佐々木丈夫(1137)佐々木幸子(1138)恩田昭子(1141)横山英樹(1143)金澤尚武(1144)の皆さん |
交流会は、本日の講師の熊谷徹氏を紹介いただいた佐々木正延さんの乾杯の発声で始まり、熊谷氏を囲んで楽しい会話が続きました。

|
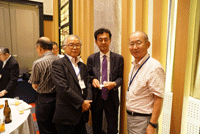
|

|
- 当日のアルバムはこちらからご覧いただけます
(森川紀一・記 三納吉二・撮影編集)