
( 2018年11月15日 掲載 )
2018年10月 講演・交流会(180回)
テーマ:『私の来し道。そして若い世代が創る明日の社会』
講 師:野依 良治 氏(科学技術振興機構 研究開発戦略センター長)
 2018年10月22日(月)14時から学士会館にて174名の参加者を得て、第17期会員総会が行われ、引き続き第180回講演・交流会が開催されました。
2018年10月22日(月)14時から学士会館にて174名の参加者を得て、第17期会員総会が行われ、引き続き第180回講演・交流会が開催されました。
講演会は、科学技術振興機構 研究開発戦略センター長 ノーベル化学賞受賞の野依良治氏から「私の来し道。そして若い世代が創る明日の社会」と題し、熱く示唆に富むご講演をいただきました。
なお、野依氏のご意向により、講演の内容のすべてを掲載できませんので、記録を担当した筆者(小林)の感想を以下に記載しました。よろしくご理解ください。
◇ ◇ ◇
野依良治氏は1945年末、母親とともに、疎開先から神戸に戻り、戦災で疲弊した厳しい生活環境の中で少年時代を過ごした。これがその後の研究人生にとって、貧しい環境を克服する意思と、絶対にあきらめない不屈の精神を身に着けることになった。1949年の湯川博士のノーベル賞受賞も、氏にとっては、きわめて大きな励みとなっている。
1966年、氏は世界に先駆け、不斉触媒反応の原理を発見した。目的とするキラル化合物とは左右の掌のように同じ化学式を持ちながら重ね合わせられない構造の異性体のことで、氏は自身の幼少期の実像と鏡を例にとり、その違いを説明し、立体構造が相互に左右逆転しており、例えば、香りの成分のリモネンでは、一方がレモンの香り、他方がオレンジの香りになることもあり、似て非なるものです。
野依氏の不斉水素化の成果を応用することにより、産業技術が醸成された。その後、米国FDAがキラル化合物の混在するラセミ体から純粋な鏡像体への転換の方針を出したことで、医療の大幅な改善が図られ、さらに注目を集めることとなった。キラル化合物の片方は有用な医薬品となるが、他方は効果がないばかりか毒になることもありうるので、FDAは有用成分のみの製造販売を促したのである。ちょうど、左足が右の靴に入らないように、片手利きの受容体と結合して、効能を発揮するのは、キラル化合物の一方だけである。サリドマイド事件がこの一例である。
このように人類の生活の発展に寄与できたことが2001年のノーベル化学賞 「不斉水素化および不斉酸化反応」受賞に結びついている。
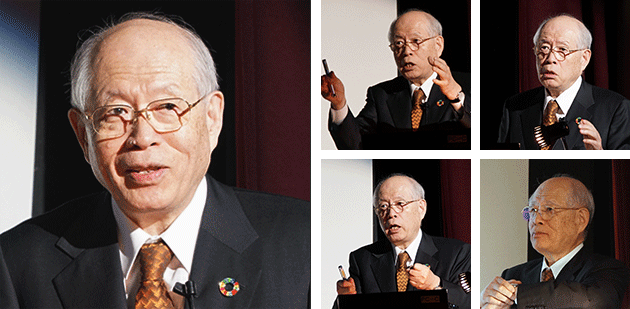
科学と芸術は異なる。芸術は進化するが進歩するとは限らない。即ち、ベートーベンから現代音楽へ進化していても、進歩したとは言い切れない。科学は必ず進歩し続ける。だから若い世代の研究者には自分を乗り越えてほしい。優れた研究を成就するには、過去に拘らない独創性、孤独に耐える精神力とともに、「異」に出会い多様な環境の中で感性を高めることが必要である。現代の日本の若者には不満はあっても、豊かさには慣れて、内向きになっている。また、他国が力をつけ、国際科学オリンピックのメダル獲得数も各分野で陰りが見える。論文投稿数の国際比較でも、年々、順位を下げている。米国大学での科学分野の博士号取得数も16位と低迷し、若世代が世界から孤立しつつある。
国際的な知の競争に勝つにはどうしたらよいか。発明協会による戦後日本のイノベーション100選では、1970年代、内視鏡、インスタントラーメン、新幹線、トヨタ生産方式、まんが・アニメなど、社会の要請に応えて卓越した意思と技術でやり遂げてきた。しかし、多くの日本人が協力する日本の一般的な開発方式が通用しない時代が来ている。
創造性の根源は多様な知性の累積にあり、ネットワーク時代の知の創造には、同質の集団の「グループ」ではなく、異なる専門能力者の集団である「チーム」の形成が必要である。米国工学アカデミーでも時代に合う教育と若者の挑戦が必須と訴えている。
文明の持続的発展には科学技術イノベーションが不可欠である。ビックデータに基づくAIのスーパースキルが人間にとって代わる中で、一方では、アントロポセン時代における地球環境の劣化が問題となっている。現代の人類は再生可能な天然資源の170%を消費している。しかも子々孫々の資源を許可なく濫費しているのである。水戸光圀が竜安寺に寄進した「吾唯知足」の精神も重要で、自らを糺すための価値のイノベーションが求められる。日本人は自らの文化に矜持をもち、責任を回避してはならない。
◇ ◇ ◇
経営経験豊かなディレクトフォースの皆さんの日本の英知をもって、若者たちの「維新の志」を喚起すべく、教育、経営指導などの社会貢献活動に期待していると結ばれました。同氏の示唆に富んだ講演に、会員一同、深い感動を得て、ディレクトフォースの社会貢献活動の推進に志を新たにした次第です。
以上
(文責:小林慎一郎 写真・三納吉二)