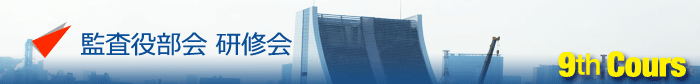
( 2014年3月26日 掲載)
DF監査役部会第9クール 第6回研修会
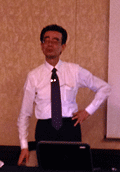 今回は、公表されている事業再生の実例を検討したうえで、早期の予防策をとるべく経営判断を行なうにはどう考えたらよいかを取り上げました。
今回は、公表されている事業再生の実例を検討したうえで、早期の予防策をとるべく経営判断を行なうにはどう考えたらよいかを取り上げました。
- 開催日時:2014年3月19日(水)午後3時〜5時
- 場 所:学士会館203号室
- テーマ:「事業再生の実例とそこから学ぶべき予防策
ーー 転ばぬ先の杖 ーー」 - 講 師:田作朋雄氏(プライスウオーターハウスクーパースパートナー)
【要 旨】
1.事業再生の過程と戦略実行の重要性
事業再生の実行は、早い時期に危機意識をもって、企業価値が毀損しないうちに、再生のための選択肢が多いうちに戦略実行することが肝要である。単に借金を減らしただけでは企業は再生しない。
2.予防策としての経営戦略
経営戦略には全社レベルの「企業戦略」と、個別事業レベルの「事業戦略」があるが、敵に対してどう立ち回るかを考える軍事理論的な戦略(相対的戦略)と、日々営々と内部資源を蓄積し続けることがおのずから敵に勝つと考える戦略(絶対的戦略)に大別できる。
3.従来の事業再生
かつては企業再建という言葉はあったが、事業再生という言葉はなかった。古きよき時代は景気循環的要因が大きかったため春待ち型経営で再生が可能だった。わが国の倒産法(民事再生法、会社更生法とも)もこれを前提としてきたため倒産予防策も金融支援依存の発想が主流だった。
2.予防策としての経営戦略
経営戦略には全社レベルの「企業戦略」と、個別事業レベルの「事業戦略」があるが、敵に対してどう立ち回るかを考える軍事理論的な戦略(相対的戦略)と、日々営々と内部資源を蓄積し続けることがおのずから敵に勝つと考える戦略(絶対的戦略)に大別できる。
4.「事業再生」の本旨
本来の意味での事業再生は、「事業」を「再生」させることであり、法務・税務・会計などの作業に矮小化されるものではない。最近は景気変動において構造的要因(IT化・少子高齢化・新興国の製造業への参入など)も無視できなくなり、春待ち型経営での再生は不可能になってきている。
5.事業再生の実例(1)ーーコア事業への特化ーー
多角化が成功した事例はきわめて少ない。多様な知財を事業に活用できる企業が多角化に成功するのであり、多角化したから成功するのではない。コア事業に戻るのが鉄則である。
6.事業再生の実例(2)ーービジネスモデルの転換ーー
構造的要因のもとで、従来どおりのビジネスモデルを踏襲していても春は来ない。経営戦略とその文脈内でのマーケティング(プッシュ型販売からプル型販売への転換など)が必要である。 早め早めの手を打てばU字型回復で回復できる。
7.プッシュ型マーケティングの失敗例
現場を見ずあるいは市場調査をせずに、思い込みだけのマーケティングによる失敗例である。再生戦略をたてる際には地域社会との役割分担なども考えて、分業を試みて共存共栄を図ることも必要である。
8.プル型マーケティングの必要性
成功例の単純な模倣はかえって失敗しかねない。ゼロサム・ゲームではなく「共存共栄」を図るプラスサム・ゲームを追及する。「近視眼的マーケティング」から脱却し、ライバルが上手くいけば我々も上手くいくという「補完的生産者」化の模索が必要である。
9.内部資源充実化と経験経済の必要性
多くの成功事例では、従業員の自発性が威力を発揮している。 対顧客、対競合先に加えて、内部資源(とくに人的資源)の視点が不可欠である。従業員に「経験」を与え、顧客に「経験」を売ること、つまり「経験経済」が必要である。
(出席者感想)
多くの出席者から事業再生の実例をあげてのお話だったの理解しやすく、参考になったとの賛辞が相次いだ。 全般に「明解で分かりやすい、かつ丁寧な説明で良く理解できた」と、好評であった。
以上
