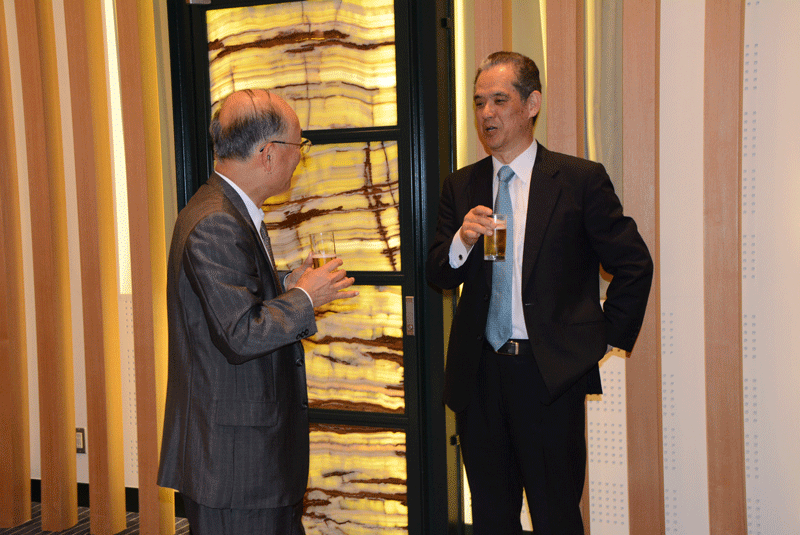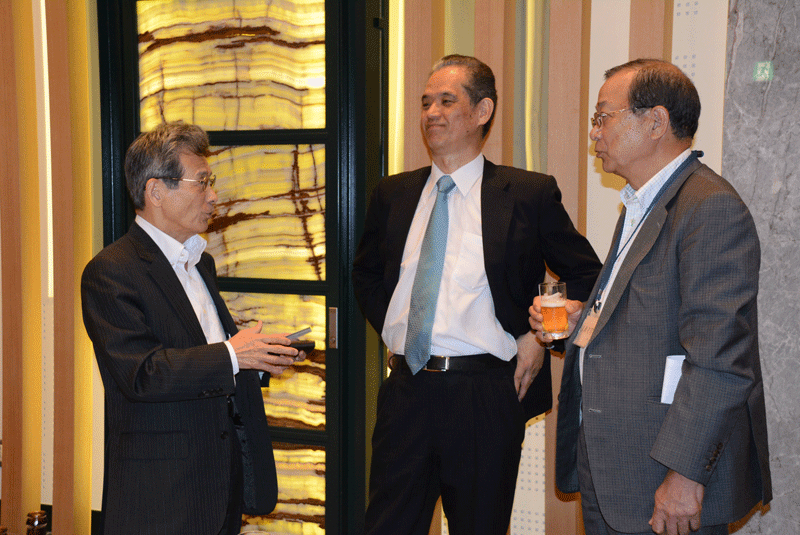(2013年5月30日 掲載)
DF監査役部会第8クール 第8回研修会
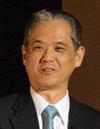
監査役部会第8クール第8回研修会が、次のとおり開催されました。
- 開催日時:平成25年5月15日(水)午後3時〜5時
- 場 所:学士会館202号室
- テ ー マ :求められるコーポレートガバナンスのあり方
近時の事例・動向から - 講 師:プロティビティLLC CEO兼社長 神林比洋雄 氏
- 参加人員:約50名
【講演概要】
1.ガバナンスの新潮流
ガバナンスに関し、以下に見るような新しい動きが出ている。
- 「企業のグローバル経営課題」にみる新しい動き(プロティビティ調査) 人材の確保・維持・育成、IT環境変化への対応、M&A後のPMIパフォーマンス向上、リスク管理体制の強化等、新しい経営課題が挙げられている。
- 「米国企業の監査委員会の課題」にみる新しい視点( PROTIVITI -USの2013年提言) 状況の変化に応じたリスクプロファイルの更新、内部監査部門の能力監査(QAR)、監査委員会自体の有効性評価等が、「監査委員会の新たな課題」として提言されている。
- グローバル企業への外部からの期待・要請の変化 ガバナンス強化(独立取締役の要請、適時開示等)、原則主義の支持(IFRS , GRC機能の連携・統合の動き)、統合報告の提唱等、外部からの期待・要請にも変化がみえる。
- 近時の内部統制に関する新しい動き(米国) SOX法制定後、企業による虚偽の財務報告の摘発件数は大きく減少している反面、FCPAの摘発件数(贈収賄)が大きく増加している。子会社はもちろん取引先が贈収賄を犯しても連座させられる可能性がある。
- 我が国の内部統制報告制度の動き 訂正内部統制報書での不備報告が増加している(日本の場合、課題が未だにすべて浮き彫りになっていない可能性が否定できないのではないか、一方で、訂正を出せばみそぎが済むという一部の風潮にも問題があるのではないか)
- SOXの効果によるガバナンスの変化 SOX以来、90%以上の会社は財務報告に係る内部統制が改善され、また、70%近くの会社はSOXの活動を業務プロセス改善に活用していると報告されている。
- COSO内部統制フレームワークの改定 21年ぶりに環境の変化を反映したものに改訂された(2013.5.14に公表)新COSOでは、ガバナンスとERMと内部統制の位置づけを明確化している。
日本型不祥事とガバナンスの特徴
- 日本企業における会計不正の事例
カネボウ、NECエンジニアリング、加ト吉、オリンパス、沖電気 - 日本型不祥事の類型と内部統制の問題点
- 経営効率過剰重視型(過大プレシャーをかけた)
- 情報の非対称性悪用型(不正の機会を与えた)
- 優越的地位濫用型(そんな姿勢を許した、不正の機会を与えた)
- 部門・子会社暴走型(不正の機会を与えた、不正の正当化を許した)
- トップ暴走型(トップの誠実性欠如)
- 尊大民僚型(そんな姿勢を許した)
- 日本型経営とガバナンスの世界的評価
ガバナンス・メトリックス・インターナショナル(2010)のレーティングによれば39ケ国中、36位であり、中国にも後れを取っているとの評価である。日本の実態を反映していないレーティングとはいえ、海外の投資家は、これを一つの指標として日本のガバナンスを判断していることも事実。日本側の情報開示が不足しているのではないか、PRに問題があるのではないか。コミュニケーションにおいて世界の潮流に乗り遅れているのではないか。 - 日本型経営とガバナンスに対する海外投資家の意見(パネルディスカッションより)
株の持合効果が不透明、意思決定プロセスが不透明(顧問の存在)、経営陣への的確な研修が不十分、変化への対応が遅い(適切なリスク管理が不可欠)などオリンパス事件を受けた意見が述べられている。 - 日本型ガバナンスの特徴 強大な権限を持つ代取のモラルと能力にガバナンスの良し悪しが依存。法律よりムラの掟が怖い(ムラの掟は常に客観的・公明正大とは限らない)監視役の取締役会が意思決定の落とし穴に落ちる危険性が高い。等
- 最近の日本の規制動向 外人投資家の批判、監査の限界論、監査事務所の品質管理の不十分さ等を契機に以下の施策が打ち出された。
- 企業統治の在り方:会社法改正要綱案が提出された。また、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正された。
- 会計監査のあり方:不正対応監査基準が実施された。
- 外部協力者:金商法が改正(外部協力者にも課徴金)された。
- 検査・モニタリングの強化等:内閣府令の改正、有証レビューの実施等が行われた。
3.信頼回復への道
- 日本企業のグローバル事業リスクの変化への対応状況
最近1〜2年の間にグローバル事業リスクが増加したとする企業が70%をこえている一方、そのリスクの識別・管理状況が出来ていないとする企業が50%近くある。 また、リスク情報の開示については、従来型のリスク開示はされているが、ガバナンスや誠実性等、会計情報以外の重要と思われるリスクについては、リスク認識が薄いのか、評価対象とされていないのか不明だが、開示されていない。 - 企業価値源泉の急激な変化 ブックバリューとマーケットバリューのギャップが拡大してきており、会計情報だけでは企業全容を語れなくなってきている。即ち、企業価値を生み出す資産(源泉)が急速に変化しており、オールドエコノミー(重厚長大産業)では物的資産が価値の源泉であったし、ニューエコノミー(IT企業など)は、顧客資産が価値の源泉であった。リスク新時代は、企業理念や無形資産など組織資産(企業の未来のバリューダイナミズム)が価値の源泉となってきている。
- 目指すべきリスク管理の在り方 変化・増大するリスクに組織としての必要なリスク管理能力が追い付かないと、リスクギャップが広がってしまう。従来のリスク管理は、戦術的、個別最適、過去の視点、受動的、年1回の評価、狭い視野、機能重視、ボトムアップの対応であったが、目指すべきリスク管理(ERM)は、戦略的,全社最適・統合的、将来の視点、能動的、継続的な評価と取組、広い視野、プロセス重視、組織的説明責任が果たされることなどでなければならない。
- 求められるコーポレートガバナンスのあり方 組織ガバナンスのあり方が、グローバル経営体制、リスク管理、コンプライアンスに大きく影響する。グローバル化におけるガバナンスの見直し(開かれた国際的ムラを目指して)のポイントは以下の実践である。
- 企業理念、ビジョン、行動基準、倫理基準の徹底。
- 組織(ビジネス)ガバナンスの高度化。
- リスク定義をチャンスと脅威と定義し、リスク管理と経営戦略とを結びつける。
- 理念の徹底を図るべくレピュテーションリスクとブランドマネジメントを強化。 *社内外への徹底的なコミュニケーションの拡充を推進する。
- 透明性を高め説明責任を果たす誠実性を常に保持する。 特に強大な権限を持つトップの誠実性が最も肝要である。
以上