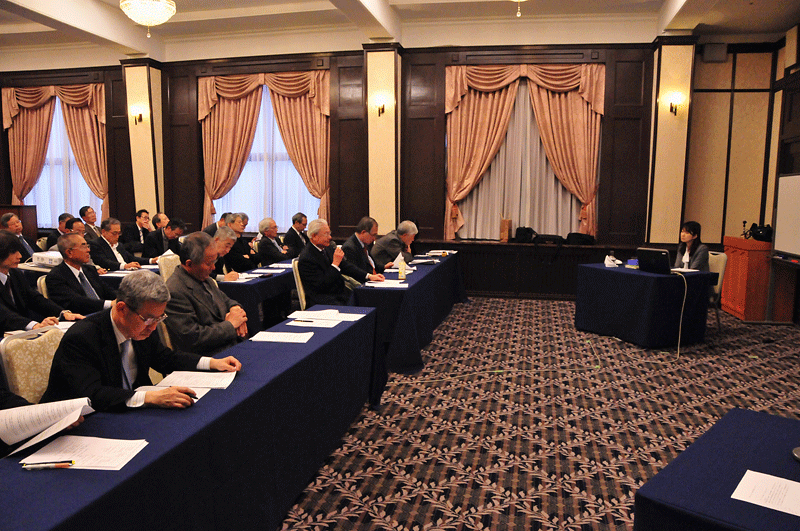(2013年3月27日 掲載)
DF監査役部会第8クール 第6回研修会

監査役部会第8クール第6回研修会が、次のとおり開催されました。
- 開催日時:平成25年3月13日(水)午後3時〜5時15分
- 場 所:学士会館203号室
- テ ー マ :日米の社外取締役制度について
- 講 師:成蹊大学 尾関幸美教授
- 参加人員:約60名
【概要】
日米の社外取締役制度について、導入の経緯、法令上の組立て、更に判例や実証研究も参照され、多角的にご説明いただいた。おおまかな流れと議論のポイントが良く分かり大変参考になる講演でした。質疑にも熱が入り予定時間をかなり超過しました。
【講演要旨】
1.我が国の会社法上の社外取締役制度、社外性から独立性へ
(1)社外取締役
会社法で定義されているが、ポイントは、過去・現在を通じ、当該会社あるいは子会社の代表取締役、業務執行取締役、執行役、従業員のいずれにもなったことがない取締役でなければならない、ということ。
この社外取締役制度については次のような経緯がある;
- 平成5年頃、日米構造問題協議において、米側から日本への投資増大を背景に「監査役制度というガバナンスの仕組みが分かり難い。米国の委員会設置会社制度(執行と監督を分離、監督機能の取締役会は半数以上が社外取締役)に近づけて欲しい。社外取締役制度の導入を。」との要請。日本は、「日本の社外監査役は、米国の社外取締役と呼称は違うがガバナンスの機能上は同じだ。」とかわした。
- その後、上場会社の不祥事が発生しガバナンスが効いていないのではないか、との議論となり、平成14年、委員会等設置会社制度が導入された。欧米の証券市場から資金調達するなど企業のニーズに合わせて任意に採用すれば良い、との考え。
- 因みに米国の取締役会は純粋な監視・監督であるが、利害関係の無い外部者である
法務省法制審議会会社法部会における「会社法制の見直し」は平成22年4月に始まった。社外取締役の選任の義務付けは米国型により近くなるのではないかと注目されたが、見送りとなった。現行の社外取締役の要件は形式基準であるが、実は、「会社と一定の資本関係を有する者の関係者でないこと」など実質的な独立性の基準を加えるかどうかの検討も行われた。これは米国の社外取締役の要件にほぼフィットするものであり米国型に近づけようとの狙いが窺える。
(2)社外取締役に期待される役割
審議会では社外取締役に期待される役割も検討された。助言機能、経営全般の監督機能、利益相反の監督機能といったもので、米国の社外取締役に期待されている役割により近い内容である。この法務省の答申を受けて東証は独立取締役制度を採用した。
さらに次の点が検討課題とされた;
- 監査役設置会社との調整
- 各会社の実情に合わせた柔軟な企業統治体制の構築を阻害することにならないか
米国での州会社法ではざっくりと決め詳細は証券取引所の規則で、という柔軟な規制に比し、なんでも実定法(会社法)で規定することが好ましいのか?との問題意識
- 人材確保の点で過度の負担を課すことにならないか
- 株主総会における社外取締役の選任手続きのありかた
検討されている監査・監督委員会設置会社制度では、それ以外の取締役とは区別して選任される方法が想定されている
(3)社外監査役
現行法では、過去・現在を通じ、当該会社あるいは子会社の取締役、会計参与、執行役、従業員のいずれにもなったことがない監査役でなければならない、と規定されている。
(4)独立役員制度(東証が平成21年12月導入、平成24年5月一部改正)
上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない会社法上の社外取締役または社外監査役)を一名以上確保しなければならない。
これは、米国ニューヨーク証券取引所の上場規則をかなり意識した要件で、会社法が定めた社外取締役または社外監査役の形式基準プラス独立性の基準を上乗せした内容になっている。
(5)まとめ
社外取締役・社外監査役は会社法にその定義規定は独立役員はない(会社法上の概念でではない。
社外性は経営トップからの独立性をたもつための必要条件であるが、十分条件ではなく、独立性の方がより高度な概念。
会社法が、社外取締役、社外監査役に法的に何の役割を期待するのかは、必ずしも明確ではない。いかなるガバナンス・モデルを想定しているのか不明。
独立役員については、現段階では、証券取引所の上場規則に根拠を有する。
2.アメリカの社外(独立)取締役制度について
(1)コーポレートガバナンスの変遷と深く結びついている
1950-60年は日本と同じように取締役会で業務執行の意思決定もするし執行もする、つまり監視・監督機能のみならず助言機能も果たしていた。この時代は、企業経営は株主利益の最大化という観点ではなく会社が適法に運営され社会的責任を果たすことを確保するかが課題とされた
80年代に入ると敵対的企業買収がブームとなったが、支配権市場によるモニタリングが効いている、と考えられた。経営陣の敵対的買収への買収防衛策・拒否の適否(株主の利益と相反する)が裁判で争われる、という状況が起きたが、デラウエア州を中心に敵対的企業買収への対抗手段を認める州会社法が制定された。
90年代に入ると機関投資家が台頭し積極体に経営改善を迫った。保有の増加や労働省により年金基金の議決権行使義務が確定されたことが背景だが、機関投資家がモニタリングのイニシアティブを握った時代であり現在に続いている。日本でも機関投資家の筆頭は年金基金であり米国の状況とあまり変わらないのではないか。
(2)取締役会の機能
理論上は二つに分類される。一つはCEOに対する助言機能を主とするアドバイザリーモデルで、1950年代の米国の取締役会の実態である。
60年代以降は、モニタリングモデルが主流となり現在の欧米のボードシステムの中心である。
日本も委員会等設置会社制度を導入し欧米型のボードシステムを選択することが出来るようになったが、採用は少なく、我が国においては日本型との制度間競争では敗れたと言えるのではないか。
ここで、アメリカ法を理解するための前提知識を整理すると;
- 州ごとに法律が異なる
- 多くの企業がデラウエア州一般会社法を設立準拠法とする
- 州会社法では、取締役・役員の責任など重要な問題について十分な規定がなされていない
- 判例法により①制定法の隙間が埋められ、②社会的要請の変化に対応している
- アメリカ法律協会の「コーポレートガバナンス原理:分析と勧告(1994年)」が実務において重要な指針となっている
- 連邦証券取引法、証券取引所上場規則等が上場会社のガバナンスのありかたに強い影響を与えている
(3)モニタリングモデルを前提とした監視・監督機能の中身
判例などから、前出のように以下の3点に整理される;
① 経営の効率性 ② 経営の適法性 ③ 会社・株主と経営者の利益相反の防止
(4)社外取締役制度の導入
実態を見ると、10年前のデータだが、取締役の人数は8〜16名程度、大公開会社の80%以上において社外取締役が過半数を占める、平均報酬は年4〜5万ドル。
社外取締役制度が普及したのか判例を調べ実証研究をすると、モニタリングが効いているから、というよりも司法審査の回避(訴訟リスクの軽減)という点で会社にメリットがあるので積極的に採用したのではないか。
- 経営の効率性という点では、有効という結論は出てこない。
- 経営の適法性の点で抑止力になっているか、積極的に良いという結論は出てこない。
- 司法審査の回避という点では次のような判例法;
取締役が会社に損害を及ぼしたにもかかわらず会社が取締役に損害賠償責任を追及しない場合に、株主は先ず会社に対し提訴請求をしてくる。すると、会社は社外取締役をメンバーとする特別訴訟委員会を任命し判断させる。提訴に至らず、株主が裁判所に提訴請求を起こしても、特別訴訟委員会の独立性に問題が無ければ訴えは却下される。
敵対的企業買収の場面では、社外取締役をメンバーとする独立委員会が、買収が株主利益になるかどうか審査し、取締役会はその決定に拘束される。後日、株主が裁判所に取締役の判断について注意義務違反を訴えても、独立委員会の手続き(メンバーの独立性など)に問題が無ければ訴えは却下される。
(5)諸外国の社外取締役に関する実証研究
実証研究はあくまで平均を示すものですべての企業にとって有益であることを証明するものではなく、また、相関関係を示すだけで必ずしも因果関係を示すものではない点、留意が必要である。日本の場合、法令上義務付けられていない社外取締役を採用する会社はそもそもガバナンス改革の意識が高く、社外取締役を採用したからROAが改善したのではなく、他に理由がある可能性がある、つまり、相関関係はあるが因果関係があるかは分からない。
3.最後に
社外取締役制度の採用を法律で強制する場合、社外監査役との法的な調整が問題となるが、両者に期待される法的な役割は違う。社外取締役の本質は取締役・経営者であり企業価値の向上という観点から職務・組織のチェックが期待される。社外監査役の本質は監査役であり取締役の職務執行の適法性のチェックが期待される。
最後に、監査・監督委員会設置会社だが、社外監査役から社外取締役へのスライドではないか、との問題指摘がある。日本型(監査役設置会社)と米国型(委員会等設置会社)の二つのモデルのあるところに、両者を足して2で割ったようなモデルを導入する意味があるのであろうか、かえって混乱するのではないか、との感想を持っている。なお、取締役との利益相反取引について、監査・監督委員会が事前に承認した場合には取締役の任務懈怠の推定規定を適用しない(損害賠償責任が発生しない)、との案だが、これは経営者がこの規定をうまく利用すると利益相反取引を簡単にやれることになり会社・株主の利益保護の面からは後退ではないかと疑問を感じている。
以上