
( 2012年3月1日 )
DF監査役部会第7クール - 第5回研修会
監査役部会第7クールの第5回研修会が、次の通り開催されました。

- 開催日時:平成24年2月23日(木)午後3時-5時
- 開催場所:学士会館320号室
- テーマ:最新の監査役の実務課題(その3)
コーポレートガバナンスから国際会計基準まで - 講 師:三優監査法人 統括代表社員 杉田 純 氏(写真右)
- 参加人員:約50名
【講演の概要】
杉田先生からは表題で3回目(3年目)の講義であり、内容の素晴らしさのみならず話しぶりの分かりやすさなど大変人気のある研修です。激変する世界経済の中での日本企業の海外進出や新しいビジネスモデルの模索、不祥事の発生と会社法改正の検討などコーポレート・ガバナンス強化に向けた動き、IFRSの最新の動向など、幅広い内容について明快なお話を伺いました。内容の豊富な資料も好評です。
【講演要旨】
1.激変する世界経済の現状
□日本経済は日銀の金融緩和・インフレ目標設定で株価も回復し少し明るくなった。ただ、EUの状況はひどく中国やインドへの影響は大きいので、EUの本格的な回復がないと安心出来ない。米国は底力があり頑張っているが、その基調が継続して欲しいですね。
□今後の日本企業の方向性ですが、円高による海外進出はすごい勢いです。従来は生産だけでしたが、今は販売もです。早く日本での生産をあきらめた方が良い。 家電はさもなくばサバイブ出来ない。米国のGEなどエクセレントカンパニーは業態を変えている。パナソニックやソニーは今の事業構造のままではだめです。
□経済産業省が元気な事業のビジネスモデルを提唱している。その一つの方向性がシステム5次産業型です。アップルモデルは開発・技術と販売のソフト、つまり2次産業と3次産業の融合、5次産業です。iphoneの8割は日本企業が生産しています。
例の前川製作所(産業用冷凍機)が中国で成功しているのはサービスです。パーツを切らさない、すぐ修理する。日本では当たり前のサービスを海外で実現するのはコストがかかる、それを中堅企業がやるのは非常にむずかしいがそれを実行している。
2.コーポレート・ガバナンスに係わる新たな動き
(1)ガバナンスを揺るがす企業不祥事

□去年はオリンパスや大王製紙などガバナンスを揺るがす企業不祥事が発生しました。気になるのは、経営トップの不正に対して内部管理体制・内部統制は埒外なのか、社長に本気にやられたらどうしようも無いのか、ということです。規制が強化されてきている近年に発生した大王製紙の方がこの点では一層問題です。 これは運用が甘かったのではないか。
社長の不正であっても社内に協力者が出てくる、誰かが知るわけですから内部統制の埒外ではないのです。社長の不正は内部統制の枠外にあるから防ぎにくい、だから社長の倫理観を高めなければならない、という論理は議論になっていない。良い内部統制制度を作ってあれば必ずどこかで引っかかって来る、そしてそこに内部通報制度が機能していれば大きな事件になる前に止めることが出来ると思っています。米国では内部通報制度が機能していると、事件が起きても 減刑などがされています。制度は作ったが運用が出来ていない、魂が入っていない状態なのだと思います。
(2)不祥事に対する対応
□実はこの3年で30件以上の会計不祥事が発生している。この4〜5年、コーポレートガバナンスも含めて体制の強化について会社法改正など検討が行われています。12月に出た会社法改正の中間試案では、独立役員の選任について東証の上場規則では監査役でも良いとなっており社外取締役は50%くらいにとどまっていますが、社外取締役選任の義務付けが議論されています。業種業態によってガバナンスの態様が異なるのだからそこまでやる必要はないとの見直し不要論もあります。この外、監査・監督委員会設置会社制度、社外取締役・監査役に対する規律では独立性について重要な取引先の関係者まで排除するのか、監査役による監査法人選任の決定権まで踏み込むか、支配株主の異動を伴う第三者割当、親会社株主による子会社取締役の株主代表訴訟などが論点です。社外取締役の人材を得られるか、米国では上場企業に必須の委員会設置会社が日本では50-60社にとどまっており不人気なのは何故かも議論になっています。また、東証では、オリンパス事件を受けて独立役員選任の理由・その役員の属性など開示を強化しようとしています。
(3)日本監査役協会の対応
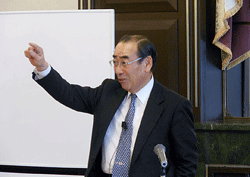
□監査基準では独立役員に関連した規程が置かれ、ベストプラクティスの提言内容を反映し、不祥事の際に設置される第三者委員会についても触れています。内部統制システムに係る監査の実施基準はこの間の実務の実績を踏まえて改定され、また、財務報告内部統制に関する監査役監査についての規定が監査法人との連携などについて見直されています。監査役監査実施要領の改定では第7章の内部統制システムに係る監査はきちんと読んでください。また、第8章の2企業不祥事発生時の対応はこの通りにやらないと職務怠慢になります。会計監査人との連携に関する実務指針の改定では監査役等がコミュニケーション対象者の統治責任者とされている点留意してください。監査役に期待されるITガバナンスの実践はコーポレートガバナンスをITサイドから見たものです。監査役がITの実際まで見るということでは無く経営がITを戦略的に考えているかを監査するという趣旨です。
(4)企業の国際化と新しい規制
□米国の連邦海外腐敗行為防止法・英国の贈収賄禁止法など欧米では確実に規制が強化されてきており、日本企業も巻き込まれるリスクが高く監査役も注意してください。中国も規制に乗り出しており恣意的な運用の可能性があり本当に要注意です。カルテル、紛争鉱物にも注意が必要。
□EUでは監査法人の共同監査・ローテーションが提案されています。中堅事務所の育成も視野に入っています。
3.IFRSをめぐる昨今の動向
□米国も足踏み状態、要はEUと米国の会計覇権をめぐる争いです。IASBは原則基準だが、米国は業種展開をしており公認会計士がこれを基準として監査をしている。これを捨てるのか、というのが米国の本音。
米国の考え方に素晴らしい点もあるのだが、日本はIASBに組するほうが得策です。
米国は聞く耳を持たないがIASBは聞いてくれる、日本にサテライトオフィスも出来る。日本の熱は冷めているがIFRSはやらないとだめです、孤児になってしまいます。
□各論では収益基準がこれまでにIASBから2回試案が公表されています。基本的には日本の販売基準の出荷基準を見直ししなければならないわけですが、契約の識別・履行義務の識別・取引価格の決定など各ステップが悩ましい。日本なりの準備・対応が必要です。既にモデルは欧州の会社にあるのですから。
□上場企業への全部一括適用にはならないかも知れません。時価総額の大きい東証一部上場企業に限定される、とか。米国では時価総額の大きい順に適用しいずれは全部適用とするようです。
包括利益会計が導入され決算書が読みにくいという意見があるようです。日本の企業家からは為替や有価証券含み損益が反映されることに異論がありますが、海外の投資家は それも企業の経営力と見ています。 退職給付債務については未だ定かではないが、一括計上してもPLは遅延して計上する方法が取れないかなどASBJ(企業会計基準審議会)も苦慮しています。
26年3月末には適用になるので2年後くらいですね。準備を怠らないようにしなければなりません。
以上
