
( 2012年1月31日 )
DF監査役部会第7クール - 第4回研修会
監査役部会第7クールの第4回研修会が、次のとおり開催されました。

- 開催日時:平成24年1月16日(月)午後3時〜5時
- 開催場所:学士会館202号室
- テーマ:「重要経営判断事項への監査役の関与」
公開買付けの賛同表明等において独立役員に求められることとは - 講 師:佐藤総合法律事務所 弁護士 佐藤明夫 氏(写真右)
- 参加人員:約50名
【講演の概要】
今回は明快かつ歯切れの良い解説で定評のある佐藤先生の講演であると共に、テーマが独立役員の意見表明という、意思の反映責任を伴うものであるだけに興味深いものでした。監査役にとってはこれまでにない検討課題にまき込まれ、想定外のテーマや慣れない議論に加わる機会が増え、シビアな対応が求められます。その時、どのように対応すればよいのか、具体論が展開されました。
【講演要旨】
1.問題の所在及びその原因
□ 重要な経営判断事項に対する(独立性のある)監査役の意思の反映が求められ、監査役としても、単に「異議がない」だけでは足りなくなってきている。取締役、監査役の議決権の有無に関係なく、議論のプロセスにおいて、意思の反映が期待される。きっちり議論し、正しい答を模索し、なぜいいのか、なぜ悪いのか、積極的な意見表明は、特に次のような具体例において求められることが多い。
- 大規模増資における意見(東証・有価証券上場規程第432条)
第三者割当による募集株式等の割当を行う場合等。当該割当ての必要性及び相当性に関する意見を表明することが求められる。 - MBOにおける意見(経産省「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」)
社外役員にMBOの是非及び条件についての諮問等が求められる。 - 支配株主との重要な取引における意見(東証・有価証券上場規程第441条の2)
例えば、合併や自己株式の取得、事業の譲渡等に関して、第三者委員会や、支配株主と利害関係のない社外役員が、少数株主にとって不利益なものでないことを意見表明することが求められる。
以上の他、企業不祥事において組成される「調査委員会」への委員としての参加、買収防衛策の「独立委員会」への委員としての参加も考えられる。
□ ところで、「第三者委員会」について、次のような具体的な提言をしたい。
- 第三者委員会を作るべきか―作ったからといって、役員が免責されるわけではない。会社のことが、分かって十分議論することが大切。形ではなく中味こそが問題。
- 第三者委員会のメンバー―問題の重要性・深刻性が高ければ、独立性を高め、外部有識者を多く入れる。よく検討して、それなりの人を選ぶ。会社とステークホルダーの利益等を考えられる人も必要。
- 第三者委員会の運営―重要性、深刻性が高いものほど、きちっとした運営をする必要がある。設置を取締役会で決議し、運営規程を設け、複数回の開催は勿論、詳細な議事録や対象者に対する質問回答を書面で行うなど、仕組みをきちっとする。
□ それではなぜ、このように社外役員の意見表明が求められるようになったのか、その背景を考えてみる。
- 直接的背景
上場会社における少数株主保護の観点から、取締役会における意思決定プロセスを明確にすることの要請が高まっていることと、意思決定プロセスにおける役員の積極的役割も求められている。 - 間接的背景
- 株主の権利意識の拡大(株価低迷が原因。配当よこせ、会社は大丈夫だろうなといった主張や不信感につながる)
- 情報開示の徹底の要請(知りたいことを知らせろ、聞きたいことを聞かせろ、意思決定の過程を知りたい)
- 不祥事の頻発(会社の人達はアテにならない、不信感が増大する)
- 大株主、支配株主による少数株主を不利益にする取扱い事例の出現
- 証券市場に対する信頼回復の要請(情報開示、社外役員への期待)
□ 要するに、十分な議論がなされていないことによるリスクがある。
十分議論してプロセスを明快にしておかないと、また、「まあいいんじゃないか」と賛同すると、事案によっては、善管注意義務違反による損害賠償請求を受けるおそれもある。可能性は低いが、開示書類の虚偽記載となるおそれもある。
□ そうなると、社外役員のキャパオーバーになる可能性もある。そんなことを想定して、監査役になったわけではない。何でそんな難しいことをやらないといけないのか、報酬に見合っていないのではないか。といった意見も出てくる。特に弁護士、会計士など資格のある人は、議論において、納得しないケースが結構多くなる。
2.独立役員の意見形成に関して求められる議論(検討事項)
□ ちゃんと議論して、ちゃんと結論を出すことが大切であるとして、そのためにはどう議論を進めればよいのか。一般論としては、
- 必要性(その行為が会社において必要なのか。必要性の検証をする)
- 相当性(必要であるとして、手段が相当であるか。手段の相当性の検証をする)
を、理論的に議論の「抜け漏れがないように」、必要な情報を十分入手した上で、必要な手間をかけて、議論することが MUST である。
□ このことを前述した3つの具体例にあてはめて検証してみる。
- 大規模増資
資金調達の必要性があるのか。借入れ、社債発行、公募増資等ではいけないのか。スキームの選択は相当であるのか。発行条件の内容が相当であるのか等々。こういったことを時間をかけて、議論することが大切。 - MBO(非上場化、オーナーの100%子会社化)
なぜ必要なのか(企業価値の向上)、非上場化は少数株主の排除、他の選択肢で企業価値の向上はできないのか(相当性)。買付価格の妥当性等々。 - 支配株主との取引(合併、株式交換)
取引等の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、少数株主にとって不利益なものではないか等々。議論の内容が重要であり、通り一遍の議論ではダメ。
3.まとめ
昨今の経済情勢を背景とした、資本市場に対する社会の要請は大きく変化している。機関投資家といったプロの保護ではなく、少数株主の保護が求められ、取締役会の意思決定の適正性に対する要請が格段に増大している。
監査役も取締役会構成員として、積極的に議論に関与すると共に、エビデンスを確保し、議論の過程では、取締役も監査役もなく、積極的な発言をすべきである。
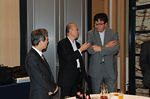 |
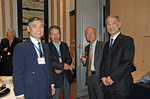 |
 |
| 研修会終了後の懇親会で談笑するみなさん | ||
以上 (本田記)
