
(11/01/25 )
監査役部会第6クール研修会第4回研修会
 監査役部会第6クール研修会の第4回が、次の通り開催されました。
監査役部会第6クール研修会の第4回が、次の通り開催されました。
- 開催日時:平成23年1月18日(水)15時〜17時
17時〜18時新年交歓会 - 場 所:学士会館320号室 参加者70名強
- テーマ:「企業統治と監査役の役割」
〜企業統治の捉え方から、監査役の役割と機能を考えてみませんか〜 - 講 師:千葉商科大学会計大学院 武見 浩充 教授
(会計ファイナンス研究科長)
【講演の概要】
時代の経済思想によって、企業統治のあり様は異なってくる。それを理解したうえで、始めて適切な監査を実施できる。監査業務と、経済社会の繋がりを再認識させる上で、有用な講演だった。
【講演の要旨】
監査役の役割は、監査機能を通じて、社会の信頼に応える良質な企業統治体制を確立することであり、そのためには適切・適宜な判断力が求められる。その判断力を涵養するには、先ず時代の経済思想を明確に認識する必要がある。
- 世界は、通貨・エネルギー・経済思想によって規定される。
<ポンド、石炭、重商主義、パックスブリタニカ>→<ドル、石油、資本主義、パックスアメリカーナ>がサブプライムショックを受けて、現在は<多極化、自然エネルギー、??主義、パックス??>の状態である。 - 時代の経済思想が明確でない限り、「自分はどのような主義(思想背景と言っても良い)で監査するのか?」を考える必要がある。
「応えるべき社会的信頼」は、どのような主義(思想)を取るかで当然に異なってくる。例えば、ハーバード大のサンデル教授は、「主義と社会正義」の3態様を示している。①ベンサム流功利主義(費用対効果、人間性の軽視)②ロールズ流自由主義(選択する自由、豊かさ、公平性などに囚われない)③アリストテレス流共同体主義(共通善の探求、和の重視)。
また、「時代の社会において正義とされる思想」=「主義」は、政治的自由度と経済的自由度の程度により異なる。前記の高低を前提にすれば、以下の4事象を想起できる。①政治的自由度高・経済的自由度高(リバタリズム、新古典派経済学)②政治的自由度高・経済的自由度低(リベラリズム、ケインズ経済学)③政治的自由度低・経済的自由度高(一般均衡理論、保守主義)④政治的自由度低・経済的自由度低(ゲーム理論、共同体主義) - そもそも、企業統治は多様な捉え方があり、その背景を理解しておく必要がある。 例えば、①経済学:失業の回避など資源の有効活用に関心、②ファイナンス:希少財である資本の有効利用、③法学:社会の安定のためのルール、④会計学:Recognize,Measure and Distributeに関心。
- Corporate Governance ,ERM, Compliance, Internal Controlを、上記と組み合わせて、理解する必要がある。
例えば資本主義を前提にERMを考えれば、成長とリスクテークのバランスという意味で、Internal Controlを捉えることができる。 - 監査綱領の中にある「会社の利益」とは何かを考えてみる。
「取締役の意思決定が会社の利益を第一に考えてなされているか」を、業務の適切性といった観点の監査する場合に、その時代の経済思想によって、例えば利益をステークホルダー間にどのように分配するかが異なってくる。日本株式会社は、資本主義の時代に利益の捉え方が重商主義的、さらに共同体維持的であり、その結果として'60年代から一貫して使用総資本事業利益率(資産収益率)は、低下している(注:日本の経済社会がそれを望んだ結果であり、誰を責めるものでもない)。 - Adoptionが想定されるIFRSを理解しておかねばならない。
「基礎の基礎」として、理解しておくべきことは、次のような事柄である。 - IFRSの目的は、資本取引を円滑にするために報告基準を統一することである。
- IFRSの基礎的概念が、現在の経営や財務諸表の見方に及ぼす影響が重要である。 (例えば、フローへの関心→ストックへの関心)
- 公正価値,資本の概念と負債の網羅性、開示への対応など理解しておくことが肝要(注:なぜ、そうなのかを投資家が納得するように説明する注記などが顕著に増加する)。
- IFRS導入に伴う企業の対応
・経営姿勢の変更を迫る可能性を有した制度改革と認識すべきである。
・会計システムの変更より、経営陣の意識改革を先行する必要が高い。
・当然に、インセンティブ基準も変化させる必要が生じる。
 |
 |
 |
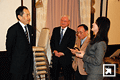 |
| 講演終了後の新年会で講師の武見教授と歓談する皆さん | |||
以上
