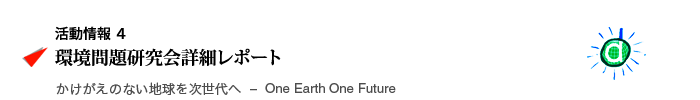
( 08/05/04 )
第8回環境問題ミニ勉強会
 |
講師の 能登谷正浩 氏 |
環境問題研究会の第8回となるミニ勉強会が4月15日学士会館で、約40人の会員が参加し開催されました。講師は地球環境と海洋資源保全のため海藻の利用を研究されている世界的な権威者能登谷正浩氏にお願いしました。「地球環境と水産資源保全のための海藻バイオ燃料の生産」というタイトルで、平素あまり関心をもたなかった「海藻」というテーマについてお話を伺いました。
[講演内容]
1.近未来社会における地球規模の危機
- 環境と水に関して、大気・環境水汚染、温暖化、砂漠化、酸性雨などに対する生態系・共生技術開発の必要性に迫られている
- 人口と食料問題については世界規模の人口増に加え、蛋白・穀物、漁獲資源減少などに対処する安全で健全な食糧自給が求められる
- エネルギー資源の需給不安定が進むなかで化石エネルギー依存から再生可能なエネルギーへの転換をはからねばならない
2.海藻が持つ主要な機能
海藻が持つ基本機能は光エネルギーを使って、無機物の水と二酸化炭素から有機物と酸素を生産することにある。この海藻を利用することにより次のような社会経済危機の克服に役立てることが可能である。
- 沿岸水の浄化、沿岸生物環境の保全、生物多様性保全など沿岸環境の保全
- 人口増、食糧危機について、水産生物資源の保全、沿岸養殖生産への寄与、安全食品と添加物の問題
- 大量のバイオマス生産、再生可能資源(天然のリサイクル資源)などエネルギー問題
3.巨大藻場でCO2吸収、バイオ燃料生産計画
- 将来的に温室効果ガスの排出削減目標を進めるためには、広大な面積を持つ日本の排他的経済水域内で海藻の持つ効果を最大限に利用することが近道。計画では日本海の大和堆に一万平方キロメーターの大規模なホンダワラの養殖場を建設し二酸化炭素を吸収する。構想では洋上に10キロ四方の巨大な魚網を100個浮かべてホンダワラなどの海藻を育てる。ホンダワラは成長が早く1年間で20メートルも育つものがある。複数の海藻を組み合わせて通年で育つように工夫すると、一つの魚網で年間27万トンの生産が可能。
- さらに船上にバイオ燃料生産工場を建設し、海藻を分解する酵素を利用したバイオリアクター(生物学的反応器)と呼ばれる特殊な装置で糖に分解し海上でバイオエタノールを生産する。ガソリンの年間消費量6000万キロリットルの3分の1に相当する2000万キロリットル生産することが可能。バイオ燃料は二酸化炭素から光合成 でつくられた炭化水素が原料なので、燃やしても元に戻るだけで二酸化炭素を増やさない。化石燃料の代りに使えばその分だけ二酸化炭素の排出を抑えることが出来る。
- プランクトンが豊富な藻場には魚などが集まり、産卵場所にもなるので水産資源の増殖にも役立つ。また大陸から日本海に流れ込む過剰な栄養を海藻が抑制し海洋環境の保全にも役立つ。
- 実現に向けての課題は、海流に流されないために魚網をどこに浮かべるか、巨大な人 工物が船舶の安全航行を妨害しないためにはどうすれば良いか、海洋法など国際法との関係調整、ホンダワラなどの特定海藻が大量に増え、太陽光を遮ることで生態系にどのような影響があるかなどを検討する必要がある。
- この計画発表は海外の反響が大きいが、日本発の技術として確立することが大切。
夢物語に終わらせないためにも、実現性を立証し明るい未来像を示していく。
以上