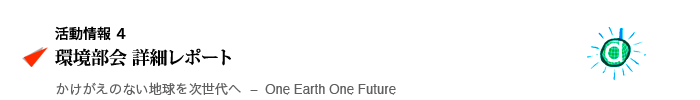
( 11/02/09 )
第4回DFエコ基礎講座
生物多様性保全(2)
 環境学習分科会では1月26日(財)日本自然保護協会村杉幸子氏(写真)を講師にお迎えし、2回目の生物多様性保全の基礎講座を日比谷公園内「緑と水の市民カレッジ講習室」で開催した。
環境学習分科会では1月26日(財)日本自然保護協会村杉幸子氏(写真)を講師にお迎えし、2回目の生物多様性保全の基礎講座を日比谷公園内「緑と水の市民カレッジ講習室」で開催した。
1回目が44名、2回目33名の方が参加され、併せて77名の方が「生物多様性保全の大切さ」を学ばれた。今回は「生物多様性、日本の現状と私たちの課題」を中心に解説がなされた。
以下、講演要旨を紹介いたします。
Ⅰ.日本は生物多様性が豊かな国だった
日本は、降水量が多く湿潤で、南北に長く、複雑な地形・地質で四季の変化に富んでいる。(生態系の多様性)又、海に囲まれた島国のため固有種も多く、いろいろな生き物(種類の多様性)がいて、種類が同じでも異なった特徴を持つ生物(遺伝子の多様性)が存在している。
Ⅱ.日本人の自然観とその変容
 自然を畏れ敬うという、日本人の感性は「森の民」に特徴的なもので古来より、巨木信仰や山や島を神に見立てる風習が存在した。そのような気持は、自分を自然に委ねる(自然共生型)という自然にとけこもうとする思想を生み、その意識している自然は狭いが、細やかな感性を持ち、桜に対する偏向に表れる様な変化を好む=朽ちることもよしとする傾向があり、古めかしさに落ち着きを感じたりする。(和歌・俳句・茶の湯・生け花)これに対して西洋人は、元来が牧畜民族であるから、意識する自然が広く、また、自然を征服して(変えて)生きていくという気分が強く(自然征服型)、その差は建物や庭園に顕著に表われているように「自然を隔てる」或いは「自然に逆らって人工的に造成」されたものである。
自然を畏れ敬うという、日本人の感性は「森の民」に特徴的なもので古来より、巨木信仰や山や島を神に見立てる風習が存在した。そのような気持は、自分を自然に委ねる(自然共生型)という自然にとけこもうとする思想を生み、その意識している自然は狭いが、細やかな感性を持ち、桜に対する偏向に表れる様な変化を好む=朽ちることもよしとする傾向があり、古めかしさに落ち着きを感じたりする。(和歌・俳句・茶の湯・生け花)これに対して西洋人は、元来が牧畜民族であるから、意識する自然が広く、また、自然を征服して(変えて)生きていくという気分が強く(自然征服型)、その差は建物や庭園に顕著に表われているように「自然を隔てる」或いは「自然に逆らって人工的に造成」されたものである。
Ⅲ.生物多様性の喪失は、なぜ起きたか?
このような「自然に委ねる」という日本人の自然観は、一方で「甘えの構造」(土居健郎著弘文堂選書)を生み、自然への管理意識の低さが環境破壊を招き、それが生物多様性の喪失につながった点は否めない。従い、今後は理性的な管理=持続可能な開発を行って、生物多様性の保全を図り、日本人として自然観の先祖返りをしていく必要がある。
Ⅳ.生物多様性保全のための私たちの役割
生活者としての私たちの生物多様性保全の意識度を、講師の設問(アンケート)を元に回答を解説頂き、認識を改めることができた。
(纏め環境学習分科会小川隆)
