2012/04/01(No122)
「ブナの植林」
牟田 忠弘
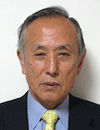 昨年の2月に自然環境保全分科会に入会し、上越の十日町市において2度ブナの植林を経験しました。
昨年の2月に自然環境保全分科会に入会し、上越の十日町市において2度ブナの植林を経験しました。
以前のブナ林についての私の知識は、洪水を防ぐ緑のダム、酸素を生産する天然の空気清浄機、野生動物の食糧の宝庫程度しかなく、どの木がブナの木か樹皮を見ただけでは判断がつかない程大変お粗末なものでした。
ブナの木の分布は、北限は北海道寿都郡、南限は鹿児島県肝属郡と広く分布しており、北海道は標高100から900m、本州は標高600から1600m、四国・九州は標高1,000から1,500mに見られ、19県31市町村が市町村の木に指定しているのは驚きでありました。
ブナの木は昭和32年から4年かけて実施された林野庁の「拡大造林計画」により、広範囲にわたり伐採されました。その後に植えられたのは花粉で話題の大量の杉の木でした。現在、各地でブナ林復活の取り組みが活発化しています。
当自然環境保全分科会が取り組んでいる十日町市の植林は、スキー場の一部コースをブナ林に戻すためのもので、現地の方々のご指導のもとに皆さん年齢を忘れて穴を掘り、植林を行っています。
雪深いこの地では垂直に植えると雪の重さで木が傷み枯れてしまうこともあるため、斜めに植えています。自然の実生から育った木の中にも、根元の方が斜めに曲がり、伸びてくるにしたがってまっすぐに成長していく様子を見ることが出来ます。
ブナの木の成長は極めて遅く、我々が植林した苗木が背丈1m、太さ1cm程度になるのに5年、一人前の木になるには20年も掛かるとのことでした。
当然ながら、成長した大きな木を我々が見ることは難しいと言わざるを得ません。それでも、後々の立派なブナ林を夢見て植林しています。■
むたただひろ ディレクトフォース会員 元日本無線

