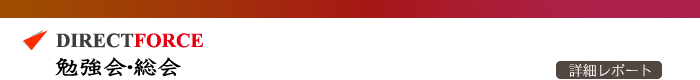
(11/12/19 )
一般社団法人 ディレクトフォース 12月勉強会
テーマ:「アラブの春、あるテロリストと独裁者の死」
 |
12月勉強会は、12月15日に学士会館で会員約100名参加のもと開催されました。今回は、国際政治学者で放送大学教授の高橋和夫氏を講師にお迎えし、「アラブの春、あるテロリストと独裁者の死」というテーマで講演いただきました。
高橋氏はわが国を代表する中東研究の一人で、湾岸戦争前にイラクのサッダーム・フセイン前大統領と面会した経験をお持ちの方です。講演いただいた内容は、ビンラーディン殺害とそれに関わるパキスタンの社会的・政治的構造およびチュニジアから始まった「アラブの春」ともいうべき中東の民主化運動についてです。
中東で急激に広がる民主化の動きが世界に衝撃を与える今、日本は何をなすべきかについて示唆に富むお話をしていただきました。概要は次のとおりです。
1.ビンラーディン殺害
アメリカ同時多発テロ事件の黒幕と言われたビンラーディンを今年5月1日にアメリカが殺害した。同事件発生から9年7ヶ月と20日後であった。殺害されたのはパキスタンの首都イスラマバードの郊外アボタバードであった。アボタバードは軍の街であり、士官学校が置かれ退役軍人が住む街である。ビンラーディンは、電話、メールの盗聴を避けるため連絡はすべて手書きでメッセンジャーを通じて行っていた。本人を見つけ出すのは至難であった。アメリカはメッセンジャーの行動を把握したことで居住場所を特定した。高い塀の豪邸の中に近所付き合いがない長身の男がいる。しかも電話、インターネット、衛星テレビがなく、ゴミは焼却して出すなどの怪しい家を2010年8月頃からCIA や無人偵察機により監視を続けていた。
5月1日の夜、特殊部隊がアフガニスタンから出撃し、ビンラーディンを殺害した。この作戦が事前にパキスタンに通告されなかったのは、重要である。この襲撃の凄さは、作戦遂行の模様が、報道によれば地上5000メートルを飛ぶ最新鋭の無人偵察機RT170によってホワイトハウスへ実況でテレビ中継されていたことである。この作戦の成功によりオバマ大統領の威信が上がった。オバマはアフガニスタンから軍を撤退させるアリバイを得たといえる。
2.パキスタンとはどのような国か
パキスタンはインドから分離するときイスラム教徒が多数派である国を作ろうとしたが、現実には2つの国からなっている。1つはイスラム教徒ではあるがリベラルで寛容なパキスタン、もう1つはイスラムを命とする過激なパキスタンである。そのパキスタンで今、ターレバン化と呼ばれる現象が進行している。つまり急進的なイスラムの影響力が増大している。この現象の背景には幾つかの要因がある。まずインドとの戦争がある。ヒンズー教徒が多数派の国インドと繰り返された戦争は、パキスタン人のイスラム教徒としての意識を強めた。第2にクウェートやサウジアラビアへ多くの人が出稼ぎに行き本場のイスラムに触れたこと、第3にアラビア半島からお金の流入とともに厳格なイスラムが入ってきた。そして第4に何よりも重要なことは、1979年から10年間ソ連がアフガニスタンを占領していた時期に、ソ連軍と戦うため世界中のイスラム過激派がパキスタンに集まってきたことである。その中にビンラーディンがいた。パキスタンはアフガニスタンへの前線基地であり、当然のこととしてイスラム急進派の影響を受け、ターレバン化が進んだ。
タ―レバン化は、パキスタンの国家運営を難しくしてきた。パキスタンは,Allah(神)Army(強い軍隊)America(アメリカの影響力)という3つのAのバランスによって国家が成り立っていると言われる。ターレバン化でアッラーが強くなることによって次第にアメリカとの同盟関係維持が難しくなってきた。アッラーとアメリカの衝突が軍隊で起こっている。社会の状況を反映して、軍隊には親アメリカ派とビンラーディンを追悼する派とがある。更にインドとの戦争の繰り返しで軍は強力になり国の中の軍となっている。しかも軍の中に統合情報局(ISI)があり、軍の中の軍となっている。ISIは国を動かすほどの力を持っており、ISIがビンラーディンを匿っていたのでないかと憶測されている。
アメリカは、パキスタンがアフガニスタン戦争の前線基地となっていること、自ら手を引けば中国の影響力が浸透すること、さらには核兵器保有国であり急進化を阻止しなければならないことからパキスタンを切るわけにいかない。その意味でパキスタンは3つのAに加えて Atomic Bomb を加えた4つのAから成り立っているといえる。パキスタンがこれからどこに向かって行くか重要な問題である。
3.アラブの春
1月にはチュニジアで市民のデモによりベンアリ政権が倒れ、2月にはエジプトのムバラク政権も倒れた。ビンラーディンのメッセージは、中東がアメリカに乗っ取られている。そのアメリカに協力するベンアリやムバラクを倒さねばならない。それを成し遂げるには殉教しかないというものであった。しかしチュニジアとエジプトでは、比較的平和的なデモで政権が倒れた。そう考えるとビンラーディンは既に時代遅れで、政治的にはすでに死んでいたといえる。その意味で5月のビンラーディン殺害は「あるテロリストの死」にしかすぎないかも知れない。
チュニジアの政変は、チュニジアの花がジャスミンであることからジャスミン革命と言われる。警察に抗議して焼身自殺した大学生の映像がネットに載った。これによって民衆の蜂起が始まり、政権が倒れた。デジタルの情報が増え、政府は情報の管理を仕切れなくなっていた。デモが大きくなると警察の力では抑えきれなくなり軍隊が出動したが、軍は民衆に発砲しなかった。そのため政権が倒れ革命が成就した。
エジプトにおいても同じことが起こった。人口激増で仕事がなく一般庶民の生活は基本的に良くならなかった。一方で国民の20%以上は1日2ドルで生活、他方で経済成長により恵まれた層がいた。貧富の格差拡大によってムバラク独裁に国民の不満は高まっていた。若者はツイッターやフェイスブックでデモを呼びかけた。アルジャジーラなどの衛星テレビが、これを報道しデモを拡大させた。これにより政権は崩壊した。政権崩壊後、軍が最高評議会を設け、民主化へのプロセス管理を行っている。エジプト国民8千万人がナイル川の両岸の国土の5%に張り付くように生活している。しかも増加している。どのような政権になろうとも、この人々を食べさせていくために厳しい選択が求められる。
4.革命のプロセス(ピラミッド崩し)
これまでの革命のプロセスを振り返ると、まずツイッター、フェイスブックなどにより小規模なデモが起こる。これをアルジャジーラなど衛星テレビが報道する。小規模デモが大規模デモに拡大する。警察では押さえきれなくなって軍隊が投入される。チュニジア、エジプトの場合、軍隊が発砲を拒否して政権が崩れた。ピラミッドのように、そびえ立っていた体制が倒れた。
何百万人のデモが直接に政治を動かした。これこそ「デモ・クラシー(デモによる民主主義)」といえる。現在のエジプトは、この直接民主主義を選挙による代議制民主主義へと、どのように制度的に着地させていくかとの問題に直面している。
5.リビアの問題(エジプトとリビアの距離)
エジプトとリビアの違いは、エジプトが国民の一体感の強さ(国民統合)があるのに対して、リビアは人口が少ないうえに伝統的な部族社会であり、一体感が薄くばらばらである。エジプトでは国民の一体感の強さにより、軍が国民に発砲しなかったのに対して、カダフィーは権力を守るために傭兵を使って国民を銃撃した。リビア人は自らの力でカダフィーの打倒を成し遂げようとしたが、政権の力が強かった。結局NATO軍が介入して政権が倒れた。問題はこれからである。カダフィーという共通の敵がいなくなったとき、これまで団結していた人たちが1つにまとまれるのかという課題がある。
6.次のドミノ
リビアの権力者の最後を見たシリア、イエメーン、バーレーンなどアラブ社会の人たちは、権力を手放したときにはこのような目に遭うのかと思ったであろう。その意味でそれぞれの人がリビアから教訓を得たと考えられる。1つは国連安保決議1973号によりNATOが介入したが、決議内容は「リビアの民間人の安全を確保するために」とあり、カダフィー殺害を認めたものではなかったがNATOは拡大解釈した。次にシリアを爆撃するような場面があるとしたら、ロシアが拒否権を発動して決議は成立しないであろう。
次のドミノはバーレーンであるが、バーレーンの場合もデモが起これば軍は発砲する。軍隊に外国出身者が多い。さらに国民の間の一体感が薄い。シーア派が多数派であるが、政権はスンニー派が握っている。選挙になれば当然シーア派が政権党になるので少数派が民主化を受け入れるはずがない。
シリアでは、親子世襲でアサド政権が1970年代から続いている。アサド大統領に対する小規模なデモが始まり、次第に大きくなり警察では押さえきれなくなって軍が出動しデモを銃撃している。すでに5000人の死者が出ている。シリアでも国民の一体感がうすいため軍が発砲する。多数派は国民の7割を占めるスンニー派であるが、1割のアラウイー派(シーアー派の一部)が軍を押え、権力を握っている。アラウイー派は民主化には絶対反対している。シリアの将来は先が見えない状況である。
中東の民主化運動を整理すれば、デモで政権があっさり倒れる国、リビア、バーレーン、シリアのように軍隊がデモに発砲する国、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、クエートといった豊かな富を防護壁にする産油国、トルコのように民主化のレベルを上げている国に分かれている。
7.中東を越えて
この変化が中東を越えて世界に広がるのか。注目の中国は、インターネットを管理する能力を持つことと経済成長が続いていることで失業者も少なく当面は大規模デモの発生は起こりにくいと思われる。更に1人子政策で少子高齢化社会へと進んでいる。起こるとすれば10年前であった。
民主主義であるはずのイギリスで起こった暴動は、職の無い人たちがツイッターで呼びかけ、欲しいと思うブランド物の店を襲う暴動になっている。イスラエルでは、経済成長しているのに若い人たちの生活が良くならず座り込みの抗議運動が始まっている。ウォールストリートの占拠があり、最近ではロシアの選挙が不正であったという抗議デモが起こっている。アラブの春が広がる方向は中国や北朝鮮ではなく、先進諸国であった。
8.日本は何をすべきか
日本はエジプトに65億円の血税をかけてオペラハウスを作ったが、1日2ドルで生活している人々のために使うべきでなかったかと思われる。
世界に例を見れば、ノルウエーは自国のNGO(非政府機関)にお金を渡し、NGOの活躍を通して国際協力をはかろうとしている。日本のODA(政府開発援助)は目減りしているが、日本の存在感を守るための1つの道はNGOを活用するODAであるかもしれない。日本でも若い人に仕事が無いのが大きな社会問題となっている。若い人は、やり甲斐のある仕事であれば安い給料でも海外に行っている。NGO活動に参加して海外に出ることは本人にとって良い経験になる。さらに日本人がODA対象国の現地にいることで存在感も守れる。何よりも素晴らしいのは、現地で苦労して帰ってくれば、世界と日本が良く見えるようになる。知恵を出しながら若い人たちのために仕事を見つけたいものである。
 |
 |
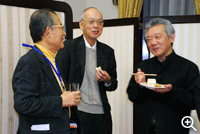 |
 |
講師紹介者の四方満氏と懇親会で高橋和夫氏と歓談するみなさん |
|
