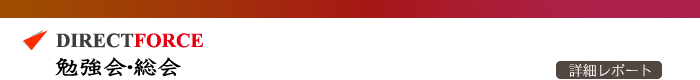
(11/10/26 )
一般社団法人 ディレクトフォース 10月勉強会
テーマ:「レアメタルが解ると世界が見えてくる」
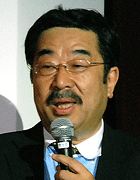 |
10月の勉強会は、日本で唯一のレアメタル専門商社アドバンスト・マテリアル・ジャパン(AMJ)の社長中村繁夫氏(写真右)を講師にお迎えし、「レアメタルが解ると世界が見えてくる」というテーマでお話いただきました。出席会員数は約90名でした。要点は下記のとおりです。
世界の人口増加に伴う資源需要の激増と資源は自国の工業力成長のために消費されるべきだとする資源ナショナリズムによって、資源をめぐる争奪戦は地球規模で起こっており予断を許さない状況にある。
日本がこれから歩むべき道は新エネルギーと環境分野における先端技術再構築であり、その技術を生かすにはレアメタル資源を安定的に確保し、有効活用をはかる必要があると説かれました。
これまで馴染みのなかったレアメタル資源のお話は斬新で貴重な勉強会となりました。詳細は次のとおりです。
1.レアメタルパニックはなぜ起こったか
世界の人口は70億人だが発展途上国の40〜50億人の需要が大爆発し、金融現象と資源ナショナリズムによるデジタル革命が拡大している。ここ10年から15年の大きなパラダイムシフトである。アフリカのルワンダ、コンゴやロシアの山奥あるいはブラジルのアマゾンにおいてすら携帯電話の普及がみられる。まさにデジタル革命である。ベトナムでは携帯電話が1500円で使用できる。サムスン、NG,ノキアなどがこのニーズに対応して大量生産している。こうしたことからレアメタルのパニックが起こる。同時に環境問題など資源開発に伴う副作用が発生する。次の10年は環境問題の10年になりそうである。
2.レアメタルの定義(レアメタル資源の地政学的リスク)
希少がゆえにレアメタル、レアアースと思い勝ちだが、①資源が沢山あってもそれを単体としてメタル化するのに技術的に困難な金属(チタン、シリコン、マグネシウム)、②資源的には豊富でも鉱石の品位が低く精錬コストが高い金属(パナジウム、スカンジウム)、③資源的に希少な金属で採掘と精錬が困難な金属(白金族金属、インジウム、カリウム、タンタル、ジスプロジウム)がレアメタル、レアアースといわれるものである。
レアメタルは地政学的に軍需的リスクがある。また市場では投機の対象となる。とくに戦略的市場操作リスクが恐ろしい。日本人にはマニキュレーション(操作)やスペキュレーション(投機)は馴染まないが、中国やアングロサクソン系の国はこれを平気で行う。これに対して日本が出来ることはリサイクル、リユース、省資源、代替資源の開発などであり、この知恵と技術で生きていかねばならない。またレアメタルには稀少性があると同時に資源の存在が偏在していることが地政学的リスクに関係してくる。これによりレアメタルの暴騰、暴落が生じやすくなる。
3.偏在するレアアースと日本の開発戦略
2008年のデータでは中国の希土類生産量は97%を占めタングステン75%、パナジウム33%は世界ナンバーワンである。アフリカもプラチナ77%、バナジウム38%で重要な資源偏在国となっている。このほかカナダのニッケルとコバルト、チリのリチウム、ブラジルのニオブなどがある。こうした状況の中で、日本の国家備蓄の方針は45日であるが、実際の資源備蓄は20日ぐらいにとどまる。
BRICsが経済的に豊かになり中産階級が増加し、希土類の放出をやめ逆に買い込み始めた。これがここ10年、20年の大きな変化である。日本の輸入は、トラディショナルなオーストラリア、カナダ、サウスアフリカからによるが、第3軸としてカザフスタン、モンゴル、コンゴ,チリ、ボリビア、キューバ、ベネゼーラがある。今後は地政学的に東南アジアのべトナム、マレーシア、ラオス、ミヤンマーなど中国周辺国家と手を結ぶ国家戦略が考えられる。日本のレアメタル開発の狙い目になってくる。
4.尖閣諸島とレアメタル、レアアース(何ゆえ中国は禁輸したのか)
2010年3月、温家宝首相がレアアース輸出の囲い込みを指示。日本はこの事実を全く承知していなかった。7月7日に中国は輸出枠を4割削減。8月末の日中ハイレベル経済対話でレアアース問題が決裂した。このとき中国はレアアースの重要性に気づく。
9月9日に起こった尖閣諸島問題により、9月23日に前触れなくレアアースを凍結した。船長釈放後も禁輸を続行、市況は高騰する。11月のアジア太平洋経済開発会議で電撃的に解決し、11月23日にようやく日本への輸出が再開された。輸出枠は前年比(前半)35%の削減。11年7月、市況は前年比10倍以上に暴騰した。8月以降市況は多少反落したが、中国側は鉱山を閉山。
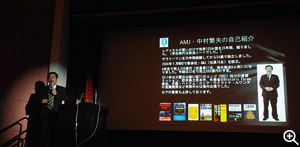 レアアースの中国の資源量は60%、生産量は92%でその後97%に。日本の輸入量は90%、迂回輸入を含めれば実質100%。日中の貿易バランス、中国がいかにコントロールしているかが分かると思う。レアースのうちで最大の生産量はセリウム、続いてランタンであるが、セリウムは10ドルが150ドルまで暴騰し、その後90ドルまで反落。セリウムは同様に10ドルが150ドルになったのが今では88ドルまで落ちている。このような異常な動きが昨年の状況であった。その他のレアアースも同様の動きをしており、中国の金融引き締めなどを受けて反落しているが、今後については不透明である。
レアアースの中国の資源量は60%、生産量は92%でその後97%に。日本の輸入量は90%、迂回輸入を含めれば実質100%。日中の貿易バランス、中国がいかにコントロールしているかが分かると思う。レアースのうちで最大の生産量はセリウム、続いてランタンであるが、セリウムは10ドルが150ドルまで暴騰し、その後90ドルまで反落。セリウムは同様に10ドルが150ドルになったのが今では88ドルまで落ちている。このような異常な動きが昨年の状況であった。その他のレアアースも同様の動きをしており、中国の金融引き締めなどを受けて反落しているが、今後については不透明である。
5.中国の資源政策
1980年代、鄧小平は先富論にもとづく改革・開放政策をとり、貿易政策では食糧輸入のために環境、品質を度外視したレアメタル、レアアースの飢餓輸出を行っていた。江沢民を経て2000年代、胡錦涛は和諾社会、国営企業改革を唱え資源輸出制限(資源ナショナリズム)を取る。2010年代に入ると胡錦涛・習近平は格差社会を是認し、国営企業が強くなり民営企業は後退する国進民退を進める。資源政策としては自国の資源を温存し、海外の資源を開発・輸入する新資源ナショナリズムを取り始めている。
6.アフリカの紛争メタル
コンフリクトミネラル(紛争メタル)問題は、アメリカの金融法が義務付けたトレーサービリティによる実質輸入禁止である。問題の本質は、人権問題と環境破壊を理由としているが、選挙を控えたアメリカ政治家の人気取り政策である。何でも採れる暗黒の大陸をめぐる中国と欧州宗主国との資源争奪戦にアメリカも参入したいと考えている。
1998年のコンゴの紛争(ザイール紛争)でアフリカ7カ国の全面戦争になった。2000年にはコルタンが10数倍に暴騰したが、その背景には死者250万人、難民200万人という事実がある。こうした歴史的な動きが生じたのは、旧ザイールのモブツ大統領を傀儡として利用したベルギー、アメリカの策略がある。モブツからカビラ大統領に変わり、ルワンダの影響を受けたツチ反政府軍による大虐殺が発生。94年ルワンダ紛争ではフツ族がツチ族を100日間で100万人を虐殺、これがコンゴ内戦へと飛び火し、コンゴのコルタンが反政府軍の手に。これに周辺国が介入した。その当時のルワンダのコルタンは国家予算と同額であった。その状況が今も続いている。コバルトもタンタルも日本のシェアー25%。供給不安が消えない。実質は中国やインドが裏ルートで輸入している。更にその裏の裏ではアメリカの企業が動いている実態がある。
7.産業の空洞化と資源・環境バブル
大震災以降の電力不足、超円高、資源問題、高い法人税が産業の空洞化を進展させる懸念がある。ただ産業の空洞化はまだ20%に過ぎない。1990年代の日米自動車摩擦の教訓を生かすべきである。
資源の枯渇が環境問題を深刻にするし、発展途上の資源国家は資源ナショナリズムに傾く。資源を材料に技術の争奪戦が始まる。いずれ資源・環境バブルの崩壊が始まると予測される。こうしたシナリオを考えると、1980年の石油ショック、2000年のITバブル、2009年の金融危機に続いて2014から15年頃には環境バブルが起こるのではないか。
資源不足は供給の減少と需要が増えることによるが、リスク回避のために日本の技術で代替材料、新規鉱床の開発をすればいいが政治的要素が絡み簡単ではない。
8.デジタル産業の市場規模と産業構造の問題点
レアメタル素材輸入が3.3兆円、電子材料6兆円程度の市場、電子デバイス47兆円、パソコン・自動車など付加価値の大きいセット機器141兆円の規模。レアメタル素材にはこれまであまり注目してこなかったが、これが10倍になれば33兆円の規模となる。
産業構造は資源産業、素材産業、部品産業、組立産業そして知的産業の5つの段階に分かれている。日本は組立産業に強く、資源産業は無視していた。ところが、組立産業が中国に移り、資源も中国にあることから、オセロゲームのように日本の産業が周りからプレッシャーを受ける構造になってきている。我々がなすべきことは国家を挙げてもっと資源産業に力を入れ、技術立国として知的産業を伸ばすことにある。
9.チタン産業
チタン生産は日本が強い分野で、2009年のデータによればスポンジチタンのシェアーが20%、あり中国に売却していた。今では中国のシェアーが33%で世界ナンバーワンとなっている。中国は自動車の生産量でアメリカを抜き、スポンジチタンの需要量で39%を占める。人口比で見れば中国の需要は更に伸びる可能性がある。
展伸財においても中国の需要が断然トップであったアメリカを抜いて37%のシェアーとなっている。中国は資源で強く、製品についても力をつけ強くなってきている。
10.環境経済の核となる環境レアメタル
原子力がなくなることはありえないが、流れとしては新エネルギーに移っていく。温室効果ガス削減についても、ハイブリッドカーからPHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)に移行していく中で、軽量化のためにチタン、マグネシウム、小型化のために希土類磁石、リチウム電池ならびに新電池開発のためにリチウム、コバルトが必要とされる。こうした時代の流れのなかで、環境レアメタルという概念が技術立国である日本の役割と考えられる。環境レアメタル分野では、社会インフラなどのベースメタル分野、エコハウスなどの構造材分野、ハイブリッドカー、新エネルギーなどの機能性材料分野、デジタル家電などの電子材料部門が重視される。
11.LME(ロンドン金属取引所)メタルの暴落とレアメタル市場
2000年7月から2011年10月の期間でみると、銅が暴落している。トレンドとして銅、ニッケル、亜鉛、鉛はピークアウトした感がある。ところがアンチモン、タングステンといったレアメタルは経済環境が悪化しているにも拘わらずまだ値上がりしている。中国のマニキュレーションによる。ロンドンの金属市場では、金融が悪くなるとコモディティが落ちるのは当たり前。その次は需給に左右されるが、その前に投機筋の問題がありそこで価格が乱高下する。最後に需給が影響する。その点から見ればメジャーメタルは市況の影響で暴落し、ピークアウトしているが、レアメタルは完全には需給が崩れているとはいえない。ただ半年ぐらいのタイムラグで暴落することが予見される。
12.日本を支える戦略分野
情報家電市場は96兆円、クリーンエネルギー市場が1兆円、省エネ・省電力・環境機器市場78兆円、環境保全市場5.3兆円の市場と言われている。このうち市場規模はまだ小さいが、今後景況に関係なくクリーンエネルギー、環境保全市場がグローバルに拡大する可能性がある。
エネルギー、環境問題にかかわる新規事業分野として考えられるのは、省エネ自動車、エコハウス、LED・蛍光灯、水素エネルギー燃料電池、太陽電池、地熱発電、風力・水力発電、原子力発電があるが、いずれもレアメタル資源を押さえておかなければ日本の技術力が生きないことになる。
13.日本が歩むべき道
今後は新エネルギーと環境問題の視点が重要視され、地球温暖化、省エネ、創エネへの取り組みが強化される。東日本の大震災で産業のパラダイムは変わり、産業の空洞化と国内産業強化の2極化が進む。空洞化は避けられないが、産業再構築のチャンスである。その中で新エネルギー分野、省エネ分野、電子材料、機能性材料など環境メタルの開発が経済の牽引力となる。資源価格は高騰し、世界の環境バブルが本格化するが、2015年までに環境バブル崩壊の可能性が高い。産業の空洞化は新生日本を国際化するチャンスでもある。今こそ資源産業、素材産業、部品産業、組立産業、知的産業を見直し新規に先端技術分野を再構築する時期に至っている。
柔軟な発想こそが日本がサバイバルできる道である。
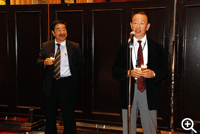 |
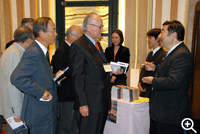 |
 |
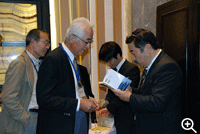 |
懇親会で乾杯の音頭を取る田中さん(左上=講師紹介者)と書籍販売会でのスナップ |
|
