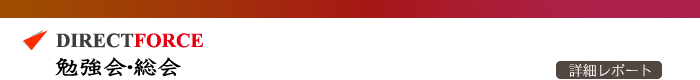
(11/10/11 )
一般社団法人 ディレクトフォース 9月勉強会
テーマ:「日本外交を考える」
 |
9月の勉強会は、9月14日(水)学士会館で行われた第20回会員総会終了後、記念講演として開催されました。テーマは「日本外交を考える」で、講師は元外務事務次官、早稲田大学日米研究機構日米研究所教授の谷内正太郎氏にお願いしました。
東日本大震災は単に自然災害の問題にとどまらず、国家として最重要課題である安全保障の問題を先送りしてきたことが問われている。日本が東アジアをはじめ国際社会で平和と安全に貢献する「責任ある大国として立ち直る」ために戦略的思考に基づく政治と外交を進め、立派なポジショニングにある「日本の国家と社会」を次世代に引き継ぐことが我々世代の責務であると説かれました。詳細は次の通りです。
1.最近の渡米で感じたこと
① 政治不信の広がり
アメリカで政治に対する不信が強くなっており、AP通信の世論調査によると、アメリカ国民の「アメリカ議会は良く仕事をしている」という評価は12%にとどまっている。
日本の場合は「国会を評価する」が3%、「政府が良くやっている」というのは6%でいずれも非常に低い。政治に対する両国民の信頼度が低いため、日米関係をどのように良くしていくかは大変難しい問題である。このような国民のフラストレーションは、日米のみならずヨーロッパ各国でも同様で、政治に対する不信が民主主義国家の間で広がっている。
3.11の大震災に日本人が一生懸命対応していることについて、日本人は凄いという評価がアメリカのみならず、全世界に広がっている。特にアメリカにおいては、自分のことは第二義的にして、家族、隣人、同僚、コミュニティ全体のことを考えて冷静に、秩序正しく行動していることは誠に素晴しいことだと称賛されている。反面、政府に関しては評価が低いというよりも、一体どうなっているのだと受け止められている。
② 東日本大震災と日米同盟が持つ意味
今回の東日本大震災で、自衛隊が陸・海・空の3自衛隊の統合部隊を組んで見事な指揮命令系統のもと統制ある行動をとったのは画期的なことである。米軍は2万6千人近くの兵と200機近くの航空機、20隻以上の空母を含む海軍艦艇を出して日本をバックアップしてくれた。自衛隊とのコーディネーションが非常に良く、他国から見ると日米同盟は凄いと受け止められた。日本人はすばらしいという評価とともに、抑止力と言う観点からは大きなデモンストレーション効果があった。
今回アメリカがどうしてあれだけのスケールと熱意で行動し支援してくれたか。自衛隊23万人のうち10万人が災害救助に当ったから周辺諸国から見れば日本の防衛は手薄になったと映ったに違いない。しかし米軍はいざというときには日本を全面的にバックアップするということをデモンストレートしたから、これら周辺国は日米同盟が健在であるのみならず強力なものであると受け止めたはずである。その意味で「トモダチ作戦」は成功したと言える。
③ 全世界から支援の申し出
今回、アフガニスタンや北朝鮮をも含む150カ国以上の国が日本に対して支援の申し出をしてくれた。日本は戦後の復興で経済力を付け積極的な経済協力を行い、かつて10年間世界一の経済援助ドナー国であった。支援の申し出は国際平和協力を行い、国際社会に貢献してきた日本の過去への評価と未来への期待が秘められたものではないだろうか。日本はこれを重く受け止め、これからのいき方に考慮を払うべきである。
④ 中国台頭にどのように対応するか
中国は東アジアでの覇権を狙って、対外的にアグレッシブで積極的な行動に出てくる。それにどのように対応するか。中国を取り囲む国々は民主的な国であり自由を大切にしているという国際環境を作り、中国がその環境の中で台頭するように持っていくことが重要である。中国が国際秩序に責任あるメンバーとして参加するようにすること、その意味で日米同盟は重要な役割を担う。東アジアの安定、秩序を守っていくため日米が協力することは1+1以上の力を持つことになる。
2.閉塞状況下での東日本大震災
① 安全保障を先送りしてきた
東日本大震災は世の中全体が閉塞状況にあり、縮み志向、内向き志向が充満するなかで起った。
阪神淡路大震災の直後に、福岡修猷館高校の先生小柳陽太郎さんが「大本は一つ、それは国家の非常事態の発生を想定することさえ怠り、強いてそれを先送りしようとする人生態度、現代日本の体質そのものである。この度の震災はまさにかかる国をあげての惰眠から目覚めしめんとする天の怒りである」と書いておられる。遺憾ながらこの警告を生かせず、これまで国家としてゆるがせにしてはいけないことを先送りしてきた。今回の大震災で提起されていることは、単なる自然災害の問題ではなく国家安全保障の問題である。安全保障とは、国民の生命と広い意味での財産を外国からの侵略や自然の災害から守ることであり、これを先送りしてきたことが問われている。
② 危機管理が全くなかった
管政権下では全く危機管理が出来なかった。阪神淡路大震災に比べても危機管理がなってなかったといえる。
③ プロの役割と責任
テレビに出てきた原子力の専門家といわれる人たちの説明が不明瞭で理解できなかった。技術やサイエンスの世界でも理論と実践の間にギャップがあるという。しかしプロであれば素人である国民にきちんと説明をして理解させる責任を果たすべきである。日本社会の中でプロの自覚がどれくらいあるのか曖昧だが、その最たるものが政治家で、国民に対する責任意識が明らかに希薄である。
④ エネルギー政策
脱原発を単純に唱えるだけでいいのか。日本が国際社会で責任を果たし、積極的な役割を担っていくうえで自分たちだけ安全であれば良いという姿勢は許されない。原発をなくせばエネルギーコストは上がるし、環境問題にも影響する。国民の生活水準は今より下がるし、製造業は日本ではやっていけなくなる。エネルギー政策は100年、200年先を見て原発問題を現実的に考える必要がある。
今日本が直面している問題は、「このまま坂道をずり落ちていく」のか、「責任ある大国として立ち直る」のかの選択である。我々の世代がやるべきことは、立派なポジショニングにある「日本の国家と社会」を次の世代に引き渡すことである。
3.日本外交の基本姿勢-吉田元総理の教訓(「回想10年」)から
① 外交感覚の必要性
 |
明治以降の優れた政治家の1人、吉田元総理は日本外交の基本姿勢について「回想10年」のなかで4つの重要なことを述べている。そのひとつ、外交感覚の必要性について次のように書いている。「ディプロマッチク・センスのない国民は必ず凋落する」「殷艦遠からず。ドイツ帝国にあり」(エドワード・ハウス大佐の満州事変直後の発言。海洋国家の日本が大陸に進出しても上手くいかない。ドイツ帝国の失敗を繰り返してはならないという意)。
② 戦略的思考の重要性
「1国の外交には、その地理的条件とその数百年の歴史より来る自然の繋がりがあるものである」(「回想10年」)。
戦略的思考にもとづく外交は、タテ軸(歴史軸)とヨコ軸(地政学)で考えることが必要。タテ軸(歴史軸)は、幕末・明治以降の日本外交はどのようなものであったかその歴史の流れ、とりわけ国民は外交に何を求めてきたのか、ヨコ軸では今の国際社会におけるパワー・バランスはどのようになっているかを考える。
このタテ軸とヨコ軸を把握して、外交政策を組み立てていくことになるが、日本は相対的な国力が低下しており、外交に使える資源・手段が限られている。頭を使って国益を追求する外交が求められる。戦略的思考は目的と手段と同時に、「プロセス・経過・段取り」がどうなるかを考えることが大切。民主党政権によるこれまでの政治は、この「プロセス・経過・段取り」の検討が欠けている。
③ 一切の前提は安全保障
吉田ドクトリンは軽武装、経済重視、日米安保の3つの路線を示すものといわれる。吉田元総理はなかでも安全保障が一切の前提になる大事なことと指摘する。これがなければ民主政治の円満な運営も、国民経済の望ましい拡大もすべて空念仏に終わるという。
④ 日米同盟の重要性
吉田元総理は「日本外交の基調を対米親善に置くべき大原則は、明治以来の日本外交の大道」とする。
4.戦略的思考に基づく外交
① タテ軸(歴史軸)
タテ軸で自覚しておく必要があることは、幕末、明治の頃は欧米の植民地主義・帝国主義がアジアに押し寄せた時期で、日本は危機感を持ち必死に自主独立を達成しようとした。「自立への衝動」があった。戦後は日米同盟をめぐってアメリカとの距離感をどう持つかというのが自主独立の問題となる。ここで注意しなければならないのは「甘えの構造」である。困ったときにはアメリカが何とかしてくれると考えるのではなく、アメリカが日本をかけがえのない同盟国であるという状況作りに意識的に努力することが大事である。
また現実主義の立場に立つと、国際相互依存体制のなかで相対的自立がどの程度確保できるかを考えざるを得ない。同盟を結ぶことが自主独立を妨げるものではない。それと日米同盟は自らの選択でえらんだものである。ただし日米同盟を必要とするなら、現在の日米安保条約を双務的で相互性を持ったもの、活動範囲を極東に限らずアジア・太平洋に広げるものへと改定すること。そして国際平和協力、PKOにおいて日米が協力しうるシステムにしていくことが必要と考えられる。
② ヨコ軸(地政学、地理学)
地政学に「大陸国家」と「海洋国家」という概念がある。中国は本来大陸国家であるが、海洋へ進出し「聖域」の拡大を狙っている。南シナ海には、大陸国家的発想である「核心的利益」があるとしてこれを支配下、影響下に置きたいと考え、更に第1、第2列島線を設定、太平洋折半論を持ち出してインド洋を含むシーレーン確保に動こうとしている。また「真珠の首飾り」という、ミヤンマー、バングラディシュ、スリランカ、パキスタンといった国々に海軍基地を借りてベースにする考えを持っている。
これに対応するためには日米同盟によらざるをえず、日本はアメリカのシーレーン防衛能力を補完するよう努めなければならない。大事なことはシーレーン防衛を中国も日米と協力して行うよう引き込んでいくこと。中国が平和的国家として台頭するその環境は、安定した民主主義国が存在するアジアであるようにもっていくこと、そのために民主主義国による対話、協力、協調が大事である。そして中国にはっきり言うべきことは、大陸国家的発想である「面的アプローチ」を海洋に当てはめることを止め、海洋国家の論理を守るべきことである。
③ 新しいパワー・バランス
アメリカの経済的再生はなかなか難しい状況で、その国際的地位も相対的に低下している。
BRICsの台頭など国際社会の構造は多極化へ進んでいる。
ただし、イデオロギーと違って自由、人権、法の支配など普遍的な価値は大事な意味を持つ。普遍的な価値についてはアメリカやヨーロッパが先進国であり、アジアは経済の中心へと移っているが、価値、理念の部分では国際社会全体の中で打ち出すべきものはない。
来年は各国首脳が交代する可能性があり、パワー・バランスがどのように変わっていくか、リーダーシップの問題も出てくるだろう。
5.中国といかに付き合っていくのか
アメリカにとっても日本にとっても21世紀の最大の課題は中国であろう。中国がこのまま右肩上がりで成長していくかは疑問のあるところ。5年ないし10年の間には2〜3%の低成長に移っていくものと考えられる。アメリカを抜いて世界一の経済国になるという展望は描いていない。最大の理由はやがて中国の人口が減っていくことにある。
中国の求心力は1979年以降継続してきた平均8〜9%台の経済成長であり、これを指導してきたのは中国共産党。一方、遠心力は格差、矛盾、腐敗などであり、経済成長が減速してくると求心力が衰え、遠心力を押さえきれなくなる。そうなると国民の関心を日本に向けてくる可能性がある。これに対して日本はいざとなれば毅然とした対抗手段を取ることを示す必要がある。
中国は中華思想による国際秩序観に立ち、一方西欧型の国際秩序観は主権国家併存、国家平等である。この相違する国際秩序観による衝突は生じないであろうが、普遍的価値を共有する国々がそれぞれ発展し、ネットワークを作って協力、協調して中国もそこに参加した方が得と思わせることが大事である。そうした国際環境を作っていくことである。何とか中国が民主主義諸国の仲間入りをして、平和と安全な国際環境のなかで共に生きるようにもって行かねばならない。
日本は資源・手段が限られているが、知恵を絞って戦略的外交でやっていかねばならない。中国とは戦略的互恵関係の共同声明があり、この精神を呼びかける余地も沢山ある。
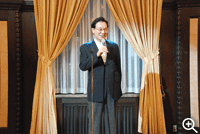 |
 |
 |
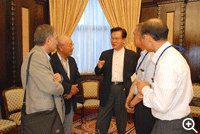 |
講演後の懇親会での谷内正太郎氏を囲み歓談する皆さん |
|
