
( 11/01/14 )
一般社団法人 ディレクトフォース 1月勉強会
テーマ:「目からウロコ!人生全般に役立つ筆跡心理学」
 |
1月の勉強会は、1月11日に学士会館で会員約110人が参加して開催されました。
今回は、DF会員で日本筆跡心理学協会会長、一般社団法人日本筆跡鑑定人協会理事長の根本寛氏に講師をお願いし、「目からウロコ!人生全般に役立つ筆跡心理学」というテーマでお話いただきました。根本氏は世間を震撼させた神戸の連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)をはじめ多くの事件関係者の筆跡鑑定をされています。そのご経験と長年の研究にもとづく多数の著書発行やテレビ出演などでご活躍中です。
今回のお話の要旨は、「文字を書くという行動は日常行動と同じく脳によってコントロールされており、筆跡にはその人の行動パターンや性格、深層心理などが表れている。それを理解し、文字の書き方を意識して変えることによって行動パターンや性格を変えていくことができるので、今より良い人生や運勢にすることが可能になる」というものです。会員からは、もっと早くお話を聞いていればよかったという感想が出る勉強会でした。
詳細は次のとおりです。
[Ⅰ] 筆跡心理学(Glaphology)とは
1.筆跡心理学とは
筆跡心理学とは「グラフォロジー」と呼ばれ、欧米では130年以上の歴史を持ち、学問として認められている。フランス、ドイツ、イタリアなどで盛んである。特にフランスでは、筆跡診断士(グラフォログ)は、弁護士などと肩を並べるレベルの高い国家資格であり、企業の採用、昇進などの人事査定、大学の進路指導、一般の諸々のアドバイスなどにおいて活躍している。
2.筆跡心理学の発展分野
次のような多くの分野で発展している。
- 性格判断を中心にした「性格学的グラフォロジー」。日本ではこの分野が中心。
- ユングやクレッチマーなど心理学者による類型学と筆跡の関係を研究する「類型学的グラフォロジー」
- 遺言書や契約書などの書き手を特定する「筆跡鑑定」の分野である「司法的グラフォロジー」
- 大脳の働きや、腕や手を動かす動作を研究する「生理学的グラフォロジー」
- 神経症や精神病と筆跡の関係を研究する「医学的グラフォロジー」。アメリカにおいて盛んといわれる。
3.日本の筆跡心理学の推移
日本では慶應義塾大学の槙田名誉教授や東北福祉大学の黒田教授などの研究があるが、あまり普及していない。日本における筆跡心理学の構築は「仮説」、「検証」によるもので、仮説を立て、それを検証した事例を統計学的に集め、70パターンぐらいに整理して1つの説にしたもの。
[Ⅱ] 筆跡と性格や深層心理との関係
1. なぜ文字から人の性格が分かるのか
文字を書くことも行動の一環であるから、そこに行動傾向がある。何気なく書いた文字にも性格が表れている。したがって行動傾向に表れた性格を読み解く方法を理解すればいい。右利きの人が左手で書いても文字に同じクセがでるから、類似している字を見つけて精査すれば鑑定が出来る。
2.筆跡鑑定
日本の普通の筆跡鑑定は、字形と運筆(筆順、筆勢など)の二つによる。私は精密鑑定を売りにしているが、これは筆跡心理学をプラスしたもの。日本の鑑定技術を高めるものと考えている。
3.人にはスコトーマ(心理的盲点)がある
人間は錯覚に陥りやすく、モノが一面的にしか見えないことがある。人間は心理的に盲点を持っているものだ。ジョハリの窓理論では、4つの窓があるという。自分も他人もわかる「オープンな領域」、自分だけ知っている「秘密の領域」、他人にはわかっているのに自分ではわからない「盲目の領域」、自分にも他人にもわからない「未知の領域」の4つであり、盲目の領域を出来るだけ減らしていくことが大切である。自己理解が深まれば他社理解も深まり、人生のすべての基礎になる人間理解力が向上し、人生にプラスとなる。
4. 筆跡と性格の関係を知ることのメリット
リーダーは「部下指導」や「適材適所」に役立てることができるし、営業マンは見込み客を理解し効果的な行動をとることが出来るようになる。母親は子供を理解して、子供から信頼される。
5. 性格を変える
性格をより望ましい方向に変えることに筆跡心理学を利用することが出来る。
性格は三重構造と考えるのが妥当。中心にあるのは遺伝的な要素である「気質」で、その周辺には3歳ごろまでに作られる「性質」がある。この2つは大人になってから変えたいと思っても変えようがない。けれども、粘りやリーダシップあるいは社交性などといった社会生活を営むうえで重要な「社会的性格」は、行動傾向といえる。これが外周を取り囲んでいる。
行動傾向は一種の行動習慣であり、時間をかければ変えていける。我々の人生は過去の行動の集積によるものであり、その集積が将来を作るから、行動を上手く変えられれば良い方向に向かうことになる。そこで、行動傾向を変えるのに筆跡を利用すればいい。同じ文字を繰り返しくりかえし書くことで変化させることが可能である。
[Ⅲ] あなたの性格を調べてみよう
1.生真面目型か融通型か
例えば「口」というような四角形の文字を書くときに、左上の接筆部をきちんと閉じ、右上の転折部を角ばらせて書く人は、生真面目、几帳面なタイプ。技術系に向く。小学校で習った通りの書き方を大人になってもしっかり守っていることから融通性が足りないともいえる。
一方、接筆部が少し開き、転折部を丸く書く人は、自由が欲しいという深層心理から少しルーズな書き方になっている。このような人は融通性があり、変化対応力がある。事業で成功するタイプ。そして下の接筆部がキチンと閉じていればお金が貯まる人である。
2.リーダー気質か協調型か
自分の考え方や行動は自分で決めたい、人に命令されるより命令する立場に立ちたいという深層心理をもつリーダー気質の人は、「大」や「神」の文字を書くとき、横線の上に縦線が長く突出した形になる。文字の全長3分の1以上突出していたらリーダー気質といえる。
4分の1以下なら協調型で、このタイプは人の上に立つのは苦手であり、余り目立ちたくない、皆と一緒の方が安心できる人といえる。一般的には典型的なリーダー気質が20%、協調型30%、中間型50%程度の分布になっている。
3.包容力があるか無いか
包容力の有無は、「様」のような「偏」と「つくり」のある文字を見るとわかる。
「偏」と「つくり」の間の空間(開空間かいくうかん)が広い人は包容力のあるひと。
逆にこの空間が狭い、ほとんど空間がない書き方の人は包容力が乏しいタイプで、自分のやり方や自分の説にこだわり人の意見をなかなか受け入れない頑固職人型といえる。しかし努力すれば名人芸といわれる分野を開拓する力を持っている。
4.粘り強いタイプか軽快型か
困難な壁を突破する粘り強さをもっているかどうかは、「子」という文字のハネの強さで見ることができる。ハネをしっかり強く書いているということは、何事も最後まで力を抜かないという行動傾向を示している。こういう人は目標達成に向け粘り強く取り組む人で責任感が強い。
一方、ハネの弱い人は、ある程度のところまでいけば次に移る。切り替えが早い、飲み込みや行動は素早い傾向がある。
5.目立ちたがり屋か、入れ込み型か
「神」という文字の左払いを長く伸ばすのは「格好良く見せたい」という深層心理を反映している。大舞台や大試合に強い人は左の払いを長く伸ばす傾向があり、元ジャイアンツ監督長嶋茂雄、シドニーオリンピック女子マラソン優勝の高橋尚子がこの書き方をしている。
「様」の最後の右払いを長く伸ばす傾向がある人は、熱中・入れ込み気性。何か始めたらなかなか止められない。ずるずるとのめり込むタイプ。女優の吉永小百合は左払い、右払いとも長く伸ばす書き方をしているが、良いところを見せたい、主役にのめりこんでいくという環境に合っている。
6.才気煥発型か執着型か
「様」の文字で横線を左に突出させる書き方をする人は、何か人より一歩先を行きたいという深層心理を反映している。頭の回転が早く、才気煥発型の人が多い。聖徳太子や大石内蔵助がこのような書き方をしている。
「神」「中」の縦線が下まで長く伸びるのは、何事にも良い結果を出そうという素晴しい深層心理の反映と見る。
[Ⅳ] 運命を悪化させる、書いてはいけない文字
運命を悪化させる文字がある。一つは「右傾文字」。「門」「岡」「国」などの文字で、右に傾いた文字のこと。日本の文字は左に進むが、右に傾くと非常に不安定な感じを与え、運命を悪くする文字といわれる。次に、「下狭型」文字。同じ文字であっても下が狭くなる字形のことで、芸術的感性はあるが、尻すぼみの傾向がある。このような書き方をする人は深層心理でこのような不安定なものを求めていると考えられる。それはいつか現実のものになりやすいので、意識して「弘法型」に書くことにより運勢を改善したほうがいい。
異常接筆というのがある。本来交差しない線が交差する書き方の「交差文字」。勝新太郎の文字がこれにあたる。この書き手の人は、普通の人が尻込みするようなことでも平気でやれる性格を持ち、気性が荒いという特徴がある。「刃物運」という文字の書き方は、本来交差しない線が軽く交差するもので、この書き手は、やや気が強く細かなことにもうるさいタイプ。白黒をはっきりさせたい傾向がある。刃物の使い方が上手いという傾向を持っている。
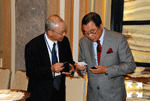 |
 |
 |
| 講演後の懇親会で、講師の根本寛氏を囲み歓談する皆さん | ||
