
( 10/12/08 )
一般社団法人 ディレクトフォース 11月勉強会
テーマ:「再生医療―ヒト脂肪由来幹細胞治療」
 |
11月の勉強会は、11月17日学士会館で会員90名余りが参加して開催されました。今回の講師は元九州大学大学院教授の柏木征三郎氏にお願いしました。同氏は現在、国立病院機構九州医療センター名誉院長、NPO九州医療システム研究機構理事長で、九州大学と提携して「再生医療」という新しい治療法の研究を続けておられます。
人間の失われた機能回復に脂肪由来の幹細胞を利用する新しい治療法で、ヒトへの負荷が小さく、リスクも軽減された画期的な方法です。受講した会員はその治療法が一日も早く確立されることを願う、興味深い内容の勉強会でした。詳細は次のとおりです。
1.再生医療とは
病気やけがなどで失われた身体の組織、細胞、器官の再生を行う治療のこと。例えば皮膚は幹細胞が分化して出来たものであるが、皮膚の細胞を増殖しシート状にして火傷の跡に貼り付けるのが再生医療である。
ヒトの脂肪組織の中に良質の幹細胞があることが分かっている。我々の治療研究は、このヒト脂肪由来間葉系幹細胞(体性幹細胞)を使い、SEEMS(シームス社)の培養技術により再生医療を行うことにある。幹細胞を使った再生医療にはこのほかES細胞、iPS細胞によるものがある。
2.「分化」する幹細胞
ヒトの身体は約60兆個の細胞から出来ているが、その中に色々な細胞のもとになる能力を持った細胞が少しだけあり、これを「幹細胞」と呼ぶ。
一つの幹細胞は細胞分裂によって多くの細胞に分かれ、身体の組織や器官を形作る様々な細胞へと変化を遂げる。これを「分化」と呼んでいる。幹細胞は自己複製を行うことが出来るだけでなく、「分化」によって目的に応じた細胞に変化する能力を持っている。
3.幹細胞の種類
幹細胞には体性幹細胞のほかES細胞、iPS細胞がある。
ES細胞は受精卵から生まれた胚盤胞で、あらゆる組織に分化する可能性があり、ひとつの細胞株を無限に培養し続けることが可能。但し、受精卵の滅失を伴うので倫理的な問題がある。他家移植を基本とするから拒絶反応への対策が求められるのと、細胞培養の際に異種細胞や血清を用いることが必要という課題がある。また移植した再生組織に奇形腫を形成しやすいリスクがあるのと人為的に分化させた細胞を実用化する分野が限られている。
iPS細胞は、成人の体細胞に2〜4個の遺伝子を入れて培養し、ES細胞とほぼ同質の細胞を作成する。体細胞を幹細胞へと「初期化」をする画期的な手法であるが、本来その人が持っている遺伝子と異なる遺伝子を持った細胞を体内に戻すことのリスクが未解明であるのと、作成された細胞が悪性腫瘍化する可能性が指摘されている。そのため創薬、臨床応用はこれからの研究を待たねばならない。
4.体性幹細胞
病気や怪我などで身体の一部が損傷を受けたときに活躍してくれるのが「体性幹細胞」。普段は身体の奥底で眠っているが、壊れて働けなくなった細胞に自らを変身させ、その細胞に置き換わったり、働き手の細胞が足りないと判断すると必要な数だけ自分を分裂させて細胞の数を増やし、身体の機能を修復する。身体の組織にはそれぞれ個別の体性幹細胞があるが、中でも「間葉系幹細胞」は分化能が高いことが知られている。神経細胞、肝細胞、腱細胞などへの分化も確認されている。我々が治療研究に使っているヒトの脂肪由来幹細胞は、間葉系幹細胞に属する。
5.脂肪由来間葉系幹細胞の優位性
骨髄由来の造血幹細胞は骨髄移植に使われている。ほとんどが血液細胞となるため間葉系幹細胞として使える量が限られる。末梢血由来の幹細胞は50%が臓器細胞、50%が血液細胞となるが、取り出すのが難しく研究を断念した。
これに対して、脂肪由来の幹細胞は、取得が容易で培養が簡単。1回で100万個から500万個の取得が可能で5%が血液細胞、95%が臓器細胞となる。現在、幹細胞では脂肪由来が一番とされている。
6.間葉系幹細胞による治療の仕組み
脂肪由来間葉系幹細胞による治療は、静脈ないし局所に投与して行う。その効果として我々が重要視しているのは「免疫調整」、そして色々な細胞になる「分化」、「血管新生」である。
治療として「静注」するが、体内に放出された幹細胞が自動的に再生を必要としている場所を見つけて移動し(ホーミング)、成着・拡大(増殖)し、目的の組織に変化する。再生の効果が出るのに3、4ヶ月かかる。
一番大事なことは、間葉系幹細胞が投与されると最初に肺にトラップされて、生理活性物質を出すこと。抗炎症物質を大量に出すので、動脈硬化(一種の炎症)にも効果がある。幹細胞成長因子や血管内皮細胞増殖因子などを出すが、いずれも血管新生を促すから加齢による機能低下を抑制するのに役立つ。骨髄幹細胞を使った脳梗塞治療例が発表されているが、同じ理論によるもの。ただ骨髄幹細胞の採取は困難を伴うから、脂肪由来間葉系幹細胞治療の方が優れている。
難病とされるCOPD(たばこ病)や脳血管障害に有効であり、更にアンチエージングに良いと考えている。マウスの実験で、劇症肝炎を起こしたマウスにヒトの脂肪由来幹細胞を投与すると、肝細胞を再生していることが確認されている。
7.シームスの再生医療の流れ
シームス社が研究開発した幹細胞の培養技術を使っている。脂肪吸引により脂肪組織を採取して、細胞調整施設(CPC)で幹細胞を培養。この技術に多額のお金がかかっており、安価にはできない。そして3〜4週間かけて培養した幹細胞を医師が静脈ないしは局所に投与して治療を行う。
8.幹細胞治療の有効性
世界での脂肪由来間葉系幹細胞の治療実験例は様々ある。どの疾患に一番有効か検討しているが、今のところ肺疾患、そしてアンチエージングに有効と考えている。
主要死因として悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎が4大死因であり、悪性新生物、肺炎は免疫低下によるもので、心疾患と脳血管疾患は動脈硬化による。
血管の老化は血管内皮細胞に始まり、血管のしなやかさの低下を来たし、次第に器質的変化にいたる。脂肪由来間葉系幹細胞は血管内皮細胞増殖因子を多量に出し、血管新生することから動脈硬化に有効なのではないかと考えられるが、そのエビデンスは未確認。
免疫機能は加齢とともに低下するが、神経・内分泌機能の低下、ストレスに対する抵抗力の低下、高齢者のQOL(quality of life)の低下をもたらす。がん患者は健常者に比して免疫スコアーが落ちていることが分かる。
エビデンスにもとづきアンチエージングに効果があるとされているのは、カロリー制限と赤ワイン成分(レスペラトロール)の2つだけである。
これ以外に幹細胞治療がアンチエージングに有効と考えられることから、自らこれを試している。
手足の指の冷感が取れ、疲労感がなくなるなど数値に基づくものではないが、その有効性を実感している。治療症例では白髪の減少、視力回復、基礎体温の上昇、疲労感減少、皮膚のつや、
五十肩改善、ソフトクラーク消失、血圧低下、喘息・咳発作の改善、COPD(たばこ病)、顔面神経麻痺、髄膜炎後遺症による握力低下の改善などと良い結果が出ており副作用は全くない。
9.今後の問題点
- どの疾患に有効かの見極め
- 難病やアンチエージングに投与する量と投与間隔
- 顔面などへの局所投与
- 自分が必要とする時に使えるバンキング
- 料金がもう少し安くならないか
などの問題点がある。
 |
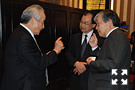 |
 |
 |
| 講演後の懇親会で、講師の柏木征三郎氏を囲み歓談が行われた | |||
