
( 10/11/04 )
一般社団法人ディレクトフォース10月勉強会
テーマ:「地域主権の近未来図」
 |
10月の勉強会は、10月21日学士会館で会員約130人が参加して開催されました。講師は増田寛也氏にお願いしました。同氏は岩手県知事時代に改革派知事の代表格として知られ、安倍内閣、福田内閣では総務大臣として地方再生に取り組まれた方です。
今回、「地域主権の近未来図」というテーマでお話いただきました。地方分権(地域主権)には住民自治の強化が求められる。そして地方分権はステップであり、目指すところは地方の活性化、社会福祉の向上にあると説かれました。詳細は次のとおりです。
1.地方自治の原則
- 補完性、近接性の原理
EUのヨーロッパ自治憲章などから導き出される考え方で、端的には自助、共助、公助と理解できる。自助は自分であるいは家族が協力し合って物事を解決することであり、すべての基本となる。家族で解決できないことを補完的に地域で助け合うのが共助、そして税金を使って自治体や国が主体となるのが公助でこれは最後になる。日本の場合、公助は三層性で基礎自治体の市町村、広域自治体の都道府県そして国。「Nearisbetter.」が近接性の原理で、まず身近な市町村、これを都道府県が補完し、最後に国が更に補完する。役割分担をこのように考えるのが地方自治の原則である。
具体例としてあげれば「子育て支援」がある。この理念は賛成できるが、政策の選択の仕方が的外れである。1万3千円を全国一律に支給したが、その前の段階で、地域ごとに共助の仕組みがあるのだから子育てについてもこれを活用し、やり尽した後に国がセーフティーネットとして機能するのが本来の姿である。財源についても地方負担を求めるのであれば、もっと自治体の工夫を生かしていくべきと考えられる。
廃棄物処理は市町村の役割として税金で賄われてきたがごみの増加で限界に来ている。基本に戻って自助として各家庭に分別を依頼し、分別収集が始まった。色々な政策について自助、ないしは共助の仕組みをもっと活用することを考えたら良いのではないだろうか。 - 首長と議会による二元代表制
国政も地方政治も代議制であるが、違いは地方では住民が首長と議会議員を別々に選び、首長と議会が互いに対立し、抑制均衡し合う仕組みになっていること。両者が話し合いを尽くして良い結論を得ることが二元代表制の狙い。しかし、首長が予算提案権を独占することから議会が首長に擦り寄って、対立がないのが現状である。そのため首長提案の条例、議案の98%が無修正で可決されている。 - 直接民主制と住民自治 国会議員は一旦選ばれると任期まで交代することはないが、自治体の首長や議員については、ハードルは高いもののリコール制度があり、住民が不適任と判断すれば任期途中でも首長や議員を辞めさせることができる直接民主制の仕組みになっている。地方自治がうまく機能するためには住民が権利の上に眠っていることは許されない。最後は住民が問題に主体的に加わっていかないと住民自治はうまくいかない。
2.地域での動き
- 首長と議会の対立の激化(二元代表制の根幹)
議会が本来の機能を発揮し、改革を志向するために首長との間で対立が生じることは好ましいことである。住民からすれば、政策的な対立で時間をかけ議論を深めるのなら良いが、住民不在の感情的な対立に過ぎないものは首長、議会どちらも責めを負うべきである。名古屋市や阿具根市における首長と議会の対立は、首長の政治手法に問題がある反面、議会が機関として求められる機能を果たしていないことに問題の根源がある。議会の会派あるいは議員が広く住民の意見を聴くことを怠っているし、議案への対応について説明責任を果たしていないのが実情である。議会は政策条例を提案することが出来るのだから、大きな政策的なことを行うことが可能である。議会が始まる前に議論すべきことを話し合い、議会が終わったら会派を越えて住民への説明をきちんとすべきである。 - 代議制の再評価
リコールはハードルが高いし住民も躊躇する。リコールの前に、個別の政策について住民投票を行うなど代議制を修正して、住民による直接民主制的な要素を入れても良いのでないか。地方自治法を改正して、常設型住民投票条例を自治体に備え、重要な案件はそれにかけたらと思う。ただ住民投票の結果に拘束されるのは好ましくないので参考にする程度で始めればいい。
3.地方分権(地域主権)に欠けている視点
- 住民自治の視点
住民自治を強化する視点はこれまでの地域主権改革には欠けていた。首長の自由度を高めることや議会の機能を強化しようというのが中心であった。今回総務大臣に就任した片山前鳥取知事は住民自治を強化する考えを示しているので地域主権改革の考え方が修正されるであろう。
地方分権改革推進委員会の「地方分権改革推進に当っての基本的な考え方」に示されている「地方政府の確立を目指して自治財政権、自治立法権を有する完全自治体を目指す取り組み」が地方分権改革といえる。地方政府の確立には行政権の分権だけでなく立法権の分権が不可決であり、条例制定権の拡大をはかることが自治立法権を確立していくことに繋がる。 - 議会(特に国会)改革の視点
日本では法律ないしは法律の委任を受けた省・政令で物事がきめ細かく規律される。国会の仕事をもっと地方議会に移すことが地方分権のポイントとなる。国会議員は地方に任せることに抵抗するであろうが、国会の審議は国が本来果たすべき安全保障とか外交など真に国が行うべきことに絞り、多くを地方議会に任せることが大事である。
地方分権改革のためには国会がその権能を地方に移す自己改革が必要となる。
4.地方分権(地域主権)改革の方向
- 直接民主制的要素の強化(住民投票条例等)
地域にとって重要な問題については住民の意向を問う自治でないと地域主権はうまく機能しない。代議制が原点ではあるが、選ばれた議員に緊張感を持たせるためにも直接民主制的要素を強化する必要がある。 - 住民自治の強化(コミュニティの重視)
自助、共助、公助を基本として、そのなかでコミュニティの機能を含めた住民自治力を強化していくことが大事である。 - 「地方自治は民主主義の学校である」
イギリスのブライスが「地方自治は民主主義の学校である」と言っているが、1人ひとりから成り立っている民主主義は地方のなかできちんと貫徹されねばならない。地方自治の姿を見ればその地域の民主主義のレベルが分かる。
5.今後の課題
- 二元代表制のあり方
首長と議会は互いに抑制均衡の関係でなければならないが、日本では歴史的経緯があり首長の方が強い。最大の理由は首長が予算に伴う議案の提出権を独占することにある。
アメリカの連邦議会では予算を含めすべて議員提案で決まる。年初に大統領が提出する予算教書は参考資料にすぎない。その根底には「代表(議会)なくして課税なし」の考えがある。
二元代表制で議会が機能不全の状態といわれるが、議会にあまり権限がないことが関係する。議会の召集権は首長にあるが、議会に臨時議会の召集権を与えることを考えても良いのではないか。
また議会に予算提案権がないことも問題であり、財源明示して予算提案する制度を設けることが考えられる。 - 地域経済の活性化、グローバル化対応
地方分権することが地域経済の活性化に結びつき、グローバル化にプラスに働く政策があればいいが現実には難しい。一つの県で対応することはなかなか出来ないので広域で協力し合い、企業にどのような寄与が出来るか考える必要がある。岩手県知事時代に物づくりを支える人材育成の仕組みを作り、企業に評価された。
地域経済を活性化させるために自治体でアイディアを出していくこと。地方分権とか地方自治はあくまでも手段であり、本来の狙いは地方の経済をどれだけ活性化させるか、社会福祉をいかに向上させるかにある。
6、道州制について
- 都道府県合併か道州制か
民主党は住民自治に関心が強く、第二次菅内閣は地域主権改革の推進について、「ひも付き補助金」の一括交付金化に着手すると触れている。ただ、道州制については距離がある。
全国知事会は市町村合併には積極的であるが、道州制には伝統的に反対の立場をとる。時代の変化に伴い知事の中にも賛成論者が増えつつあるが、政権のスタンスが道州制に積極的でないし、相当の力技が必要になるので今のところ進みづらい。
都道府県合併は今でもできる。しかし国の姿は変わらない。道州制は都道府県が合併でブロック化して、国は小さくなる。中央省庁でやっている仕事のかなりの部分が道州政府に移ることが都道府県合併との大きな違いで、中央省庁の解体、再編を含めたものが道州制である。 - メリット、デメリット
メリットとしては、47の都道府県に区分けされた経済規模をスケール拡大して考えた方が経済合理性にかなっている。また国の出先機関は都道府県と同じような仕事をしているから、この二重行政を整理すれば効率が良くなり、税金の無駄遣いの排除にもつながる。さらに、道州制になれば今まで都道府県でやっていたことは、もっと身近な市町村がやることになるし、中央省庁で決めていたことが道州で決められるようになる。住民に近いところで物事が決まるのが大きなメリットである。
デメリットは周辺部が衰えるのでないかという懸念、あるいは道州知事が強力な権限を持つことになり議会がこれを抑えらず、民主的統制が効かなくなるのではないかということ。法律で任期制限をして枠をはめるなど、道州制導入具体化に際して工夫していくべきことである。
道州制によって地域の特色を出し、その単位で中国とも貿易を行い、経済をまわしていくことをしないとやっていけなくなる。環境問題、ごみの不法投棄対策、観光振興なども広域で対応することが求められる。社会福祉や社会保障分野を、とりわけ介護保険、医療保険などを市町村で支えるのは無理になってきているので、道州単位で取り組んでいくことが重要になってきている。シユミレーションを行いどのような姿になるか青写真を示すことが大事である。
今後30年間で人口は急速に減少する見込みだが、三大都市圏と地方圏の人口格差は拡大していく。日本のGDPは2050年には世界第8位に転落し、経済大国の地位を失う恐れがある。こうした状況のなかで地方をどうするか考えたとき、地方で出来ることは地方に任せることが重要になってくる。これまで地方分権については、権限や金を地方に移すことばかりが議論されてきた。首長や議員は住民から選ばれたものであり、住民に責任を持てる体制にしなければならない。地方が果たすべき役割と国が本来的に対応すべき役割分担を考えていく必要がある。
 |
 |
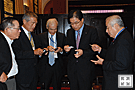 |
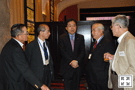 |
| 講演終了後増田寛也氏を囲んで懇談する皆さん | |||
