
( 10/10/06 )
一般社団法人ディレクトフォース9月勉強会
テーマ:「民主党代表選とその帰結」
 |
9月9日(木)学士会館で、一般社団法人ディレクトフォースの第18回会員総会が開かれ、会員約200名が出席しました。
総会終了後、元東京大学総長、現在学習院大学教授で政治学の分野において第一人者の佐々木毅氏をお迎えし、「民主党代表選とその帰結」というテーマで基調講演をお願いしました。
国民が総選挙によって政権を託す政党を選択し、その代表が首相候補に選出されるのと違って、今回の代表選は政権政党の都合によるもので、その結果によって首相が決まる意義について色々な視点でお話いただきました。民主党を二分する熾烈な代表選となっているが、その結果如何にかかわらず、課題が山積する状況において後始末が重要と解説されました。詳細は次のとおり。
1.小沢さんの立候補はミステリアス
多くの人は8月20日ごろまで小沢さんの立候補はありえないと考えていた。その意味で小沢さんが立候補したことはミステリアスと受け止められている。一つには検察審査会が起訴について検討していること(だから立候補したという説もあるが)、もうひとつは菅政権がどれぐらいもつのかという見通しについて、難しい境遇に置かれている政権であるからいずれ行き詰るだろうと見る政治家が多く、ここで好んで代表戦に出ることもないという見方である。
立候補しなくとも次の選挙ということを考えるといずれ小沢さんの出番を考えざるを得ない客観情勢にあるというのも一つの見解である。あるいは小沢さんに68歳で後がないという思いがあったのかもしれない。
2.国民世論と党内世論とのギャップ
マスコミが報道する国民世論と民主党内世論にはギャップがある。ギャップがあるから政党という組織に意味があるともいえる。しかしギャップが大きすぎると無理な政権を作ることになり、先は短い。小沢さんが勝つことになれば、彼の得意技は選挙といえるので、選挙が近いと予想する人が多いのも今回の代表選の特徴的なこと。参議院選挙が終わり次の衆議院選挙に向けて小沢さんの気分はスイッチオンになったところもあるだろう。菅さんはあと3年やって衆参両院ダブル選挙と言っており、スケジュール観の違いが2人の間にある。
3.政治と金の問題
政治と金の問題についてさしたる具体的提案がない。政治と金の問題に関しては、いまや日本は先進国といえない状況に至っている。政治資金の問題でいえるのは、政党が組織経営の面で極めて劣悪であること、ここに問題の根源がある。党が政治資金を管理できない問題が付きまとう。透明性が低く、個別的なチェックが出来ない状況。修正申告で済む人、大きな問題になる人などそこには取り扱いのルールがない。小沢さんがこの問題を代表している。
4.マニフェストの枠内にとどまる論議
政策論議が大事ということになってきたが、この代表選の特徴的なことは昨年の衆議院選挙のマニフェストが枠になっていること。小沢さんは、現政権はマニフェスト不徹底、政治主導が出来ていないと批判してマニフェストへの原点回帰を主張する。一方菅さんはマニフェストの柔軟な修正に言及している。 マニフェストに基づく昨年の総選挙が今の政権のベースになっており、そのベースを変えようとすれば総選挙を行う必要がある。したがって総選挙をしないで言える話の内容は限られてくる。 政権政党内での代表選であるから、政策論争といっても両者の主張はいずれもマニフェストをどう解釈し適用するかというマニフェスト管理の問題にとどまる。当然のこととして両者の政策に際立った違いや新味が出てこない。もし争点があるとしたら、その枠をどう理解するかの説得性がどちらによりあるのかということである。
5.激戦の後どうなるか
激戦であり、票の奪い合いであるから終わったあと大きな出来事が起こるのではないかという見方があるが、そもそもコップの中の狭い話であるから大事になりえないといえる。 挙党態勢であるとか人事の問題はどちらが勝っても起こることが確実である。ただ、野党は崩れやすいといえるが、与党で政権運営に責任を持っている政党が大分裂することは珍しいこと。 菅さんが勝ったときには小規模な分裂が起こるかもしれない、小沢さんが勝ったときには何も起こらないだろうという解説もある。後始末は簡単ではないが政党政治が大爆発を起こすようなことについては慎重に見ておくべきだ。
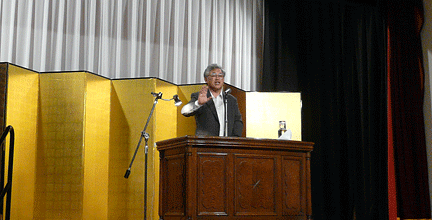
6.与党の公的責任
小泉政権以降政権の寿命が短くなってきた。同じ政権内だから大した違いがないと思うかもしれないが、ミクロ的には誠に厄介な問題で人の入れ替え作業が多く無駄とロスが発生する。
与党の場合は総選挙で首相候補者として出した人が少なくとも数年間政権を担当するというのが諸外国では常識である。日本のこれまでの短期政権は党内事情優先によるものだが、政権を担当するとは公的責任があるということであり、党内事情よりも公的責任を優先すべきであるというのが国民の視点であろう。公的なものと内部的なものとのバランスが崩れてしまうのは、政権政党としての資格の問題に関ってくる。
統治行為をしてその政策がまずかったとか厳しい批判を受けて政権の座を降りることは、好ましいことではないが、これは一つの帰結である。しかしそこまでいかないうちに滑降してしまう。これでは財政赤字や社会保障制度の改革といった大きな問題の解決に果たして取り組めるのか疑問である。政権がきちんと作動する時間というファクターが、パフォーマンス(統治)に大きい影響を与えていることを政治家は本当に理解しているのだろうか。
8.日本政治の構造的問題
円高は根本的に考えるべき大きなテーマ。日本の政治はこれを突き詰めて考えたことがない。 経済構造、外交関係など色々根本的に考え直したり、見直したりすべき時期であることに間違いない。その意味で課題は山積し、今までになかった難しい問題をじっくり考えて処理しなければならないのに、入れ替えが激しく、ねじれまで生じている。日本の政治は構造的に無理な状況に置かれており、一体どうなるのかなという風に見受けられる。
9.政権運営のスタイルと問題点
小沢さんに対しては剛腕ないしストロングマンへの願望、あるいは閉塞感打破への期待感がある。しかし小沢さんがテレビに出るようになりイメージが修正されつつある。彼はマニフェストを含め色んな枠の中に入ったという感じを受ける。その意味で、小沢さんがびっくりするようなことをすると期待するには懐疑的な感じがする。また小沢さんが勝ったときには誰が幹事長になり、誰が政策を担当するのか。任せられずに自らやるのか。誰が小沢さんの意を受けて政権を動かすのか想像することが難しい。
菅さんはねじれ問題に対応するため与野党の協議を進めるというが、話し合い路線を進めるエネルギーが足りない。与党がシナリオを作り、方向性を決めイニシャティブをとらないと話し合いにならない。何を突破口として政権の浮揚を図ろうとしているのか。自民党がこれまでやってきた公共工事、構造改革と違った第3の道として雇用重視といっているが、インパクトのある具体的なものにしないとアピールしない。戦後やってきた政策体系はもはや使えなくなった。相当の準備をし、スピードを上げて新しいストーリーを作り出さなければならない。
10.最後はトップの手作り
民主党政権の2人の総理を見てきて、情報の入り方のバランスが取れていたのかという疑問と政権交代を実現しようとするなら執念を持ってもっと勉強しておくべきだったのではないかと問題を感じる。 経営と同じく政治においても最後のトップのところは手作りである。その人が何をどのように考えるかの話を抜きにしてコトは進まない。すなわちその人がポテンシャルにどんなものを自分の中にもっているのかを抜きにして話は出来ない。その意味で今の日本には、とことん考え抜くリーダーがかってないほど必要になっている。
11.政党を変える
一つのアイディアとして、手持ちの資産である金や人の能力をもっと有効に活用するべきである。色んなところにストックがあるが、政治、行政、社会あらゆるところで縦割りになっており、それぞれがテリトリーを強固にして、互いに無関心でばらばらのためストックの無駄が多く、効率が悪い。新しいコンビネーションを作る組織を見つけ出し、これを政治家と結びつける作業を行わないと政治家の無知と政治の貧困を解消できない。
これまでの政党モデルはすでに破産しており、政党自体が変わることが必要。政治資金は政党を変え、縦割り組織を是正していく上で良い手がかりになると思う。もう一つは社会もいま少し新しい動きをして多くの接点が出来るように変わっていかなければならない。
12.後始末が大事
日本では、20世紀がやり残した課題を21世紀が全部引き受けている。特に少子高齢化、環境の問題しかり。経済的な活力も含めてどういうニューバランスを作るのか問われているが、20世紀後半に作ったモデルだけではもはややっていけない。働き方、定年、生き方を変えるなどチャレンジングな課題が沢山あるような気がする。
代表選は政党の組織にとって大きなイベントであり、これをとおして政党の組織が変わるきっかけとなり成熟していくことを期待する。勝敗の結果はともかく、後始末をどうするのか目配りすべき段階となる。
 |
 |
 |
 |
| 児玉事務局長の乾杯で懇親会が始まり、講師の佐々木毅氏囲み歓談が行われた(写真クリック拡大) | |||
