
( 10/08/28 )
8月勉強会(2010/08/06 金)
テーマ:「サクセスフルエイジングへの挑戦」
 |
今回の講師は、京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学の吉川敏一教授(写真)にお願いし、「サクセスフルエイジングへの挑戦」というテーマでお話いただきました。
吉川教授はフリーラジカル研究の世界的権威者です。研究を進めておられる老化のメカニズムとサクセスフルエイジングにどのように取り組めばよいかという内容で、ディレクトフォース会員にとって極めて関心の高いお話を解説していただきました。詳細は次のとおりです。
1.はじめに
研究テーマはいかに病気を予防し、それを実践するかである。そのために食事や運動による生活習慣の改善が必要ということが分かっている。食事については、食品のもつ機能を上手く利用すればよく、機能性を高める農作物の開発研究も行っている。
適切な食事や運動により骨、筋肉を丈夫にし、頭をクリアーに保って病気を予防することが大事で、これががん予防にもつながる。
今、消化器内科でがんの患者が増えている。いかにがんの患者を少なくするかが課題であり、がん発症の原因も分かってきているので、がん発生抑制のための啓蒙活動を行っている。
ここにご出席の皆さんの年齢から判断して、皆さん方は1日に5000個ぐらいのがんが発生していると思われる。中には6000個、7000個の人がいるかもしれない。これを自分の力で殺している。がんになっても大きくしない力もある。この力をパワーアップして発生を抑え、もし発生しても大きくなるスピードを抑えることである。
がんが増えているのは長生きするようになったからではなく、すべての世代で増えている。がんが発生しやすい生活をしているためである。
現在、猿の段階まで研究が進んででいるが、カロリー制限すれば霊長類(猿)の寿命を延長し、生活習慣病を予防することが分かってきた。2009年「サイエンス」に発表された研究論文によれば、自由摂食を20年間続けた猿(人間で言えば60〜70歳)と30%のカロリー制限を続けてきた猿のグループとでは、毛並み、尻尾、顔そして目などに違いがあり、カロリー制限してきた猿はたるみがなく鋭さを保っている。見た目が若いだけでなく、死亡率や年齢関連疾患である糖尿病、がん、高血圧、脳の萎縮にも差が認められ、カロリー制限を受けた猿のグループでは8割ぐらいがこうした疾患を持っていない。
これまでの老化の研究は、我々の現在の状態が正常で、ここからいかに老化を止め、若さを保つかというものであったが、「サイエンス」にこの論文が出てから、今の我々は歳を取りすぎている、本来はもっと若いはずである。カロリー制限をすれば若さが保たれるのであれば、研究すれば制限しなくても若さを保てるのではないかという考え方に変わってきた。
2.エイジングの原因
エイジングの原因はいくつもある。その例として
- 酸化ストレス
酸化による体内の錆びであり、これが原因で起こる脳卒中への対処としてラジカットという錆び止めの薬が使用される。カロリー制限をすれば錆びを抑えることができる。 - ホルモンレベルの低下
加齢によって成長ホルモンの分泌が減少し、筋肉に衰えが出る。生体によって分泌のリズムがあり、これが狂うとホルモンレベルの低下をもたらす。運動と睡眠、朝になったら光を浴びるリズミカルな生活により分泌がよくなる。 - 免疫機能の低下
活性酸素やホルモンレベルの低下によっても免疫機能は低下するが、歳を取るにしたがってリンパ球の力が落ちてくることにより監視機能が鈍くなる。これを防ぐ方法として適度な運動、ストレス回避、温泉などで体温を上げる、笑うことなどがある。 - 遺伝子変異
紫外線、宇宙線を浴びるとか毒性食品の飲食などによるものでやむをえない面があるが、それを工夫してできるだけ避ける努力が要る。
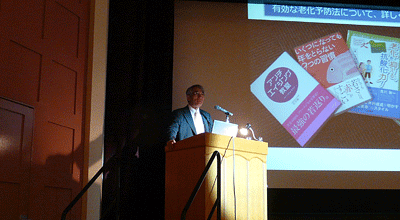
3.健康寿命の延伸
加齢に伴う身体機能の衰えの曲線は人それぞれに異なる。機能低下は止められないが出来るだけ緩やかにする研究をしている。
健康寿命延伸対策として必要なことは、3大死因といわれる悪性新生物(がん)、動脈硬化性の疾患、脳卒中の予防対策ということになる。色々な遺伝子の研究によりその原因が解明されてきた。
その先は再生医療としてips細胞で置き換えることになるが、実用化にはあと数年の研究を待たねばならない。
悪性新生物(がん)と動脈硬化性疾患は異なる症患群であるが、共通の基盤病態が存在する可能性がある。糖尿病が動脈硬化の原因になりやすいのと同様に、肥満が心筋梗塞を起こしやすいことも知られている。ところが最近、糖尿病、肥満、脂質異常ががんの原因となることが分かってきた。
肥満はがんによる死亡の危険因子であり、相対危険度は肝臓 4.52、すい臓 2.61、胃 1.94、食道 1.91、大腸 1.84、胆のう 1.76などと肥満によるがん死のリスクが非常に高い。以上はすべて消化器であり、消化器のがん予防について肥満の問題を考えなければならない。
糖尿病の死因も肝臓がん、肺がん、すい臓がん、胃がんを合わせると22.2%ととなり、トップの虚血性心疾患、2番目の脳血管障害の合計を上回り、糖尿病ががんになる原因といえる。
以上のような疫学的事実から判断して、「肥満」「メタボリックシンドローム」対策が予防医学的に重要であり、アンチエージングにつながる期待が高いといえる。
4.長寿遺伝子
カロリー制限するとインスリンシグナルを抑制し、体に悪い影響を及ぼすインスリン分泌が少なくて済むようになる。また初めて発見された長寿遺伝子「サーチュイン」を活性化させ、長寿に関る遺伝子群を発現し、維持させて長寿になることが解明されている。
5.なぜ太るのか
脂肪蓄積の機能として、飢餓・食糧不足の時代は体脂肪の蓄積は飢餓に耐え生き延びるためのものであった。現代の飽食の時代では体脂肪の蓄積は過剰エネルギーの状態にあり、これが肥満の大きな原因になっている。
また交通手段の発達により、運動量が減っていること、食生活の変化、不規則でストレスのたまる社会で過食になるなどの環境因子も影響する。
同じ太っていても、皮下脂肪が多いタイプはそれほど危険ではないが、内臓脂肪が多いタイプでは生活習慣病、動脈硬化、心筋梗塞などのリスクが高い。内臓脂肪蓄積は高インスリン血症を起こし高血圧、動脈硬化などと色々な病気を引き起こすことになる。
6.運動で予防・改善できる生活習慣病
運動することはインスリン抵抗性を改善し、血糖値上昇を抑制することから糖尿病対策になるとされてきたが、加えて骨格筋の脂質代謝亢進による血清中性脂肪低下、骨格筋のエネルギー亢進による体脂肪減少によって肥満を改善。更に血圧上昇抑制による高血圧の改善や免疫能向上、抗酸化能力向上による細胞のがん化抑制によって大腸がん発症抑制につながる。
運動習慣のない場合は、ある場合にくらべ総死亡率で相対危険度が1.32である。個別の生活習慣病でみて、冠動脈疾患 2,20、高血圧症 1.30、糖尿病 1.43など、運動しない場合の相対危険度は高い。
運動療法がウエストサイズ、内臓脂肪に及ぼす3ヶ月の実験をしているが成果が出ている。内臓脂肪がたまっている場合、3ヶ月の運動療法によって、動脈がやわらかくなっていることが動脈の硬化度評価で分かる。脳血管障害、心臓の血管障害が起こりにくくなっており運動療法は有効といえる。運動は大腸がんを予防することも分かっている。筋肉が出す物質(蛋白質)が予防に役立っている。
自覚的運動強度の目安は、「楽である」から「ややきつい」の中間くらい。60〜70歳だと心拍数が120程度になるのが適当である。一歩でも多く歩く健康ウオーキングや自宅で出来る筋力トレーニング、階段利用などの工夫によって運動量を増やす。色の着いた野菜などの食品を食べ、運動と食事でバランスをとりながら無理なく内臓脂肪を減らすことが生活習慣病を予防し、サクセスフルエイジングに役立つことになる。
 |
 |
 |
 |
| 佐藤和恵さん(左=講師のご紹介者)の乾杯で懇親会が始まった。今回は出身地別にテーブルを囲み懇談(写真クリック拡大) | |||
