
( 10/09/15 )
7月勉強会(2010/07/13 火)
テーマ:「一票の格差と違憲立法審査権」
 |
| 泉 徳治氏(クリック拡大) |
一般社団法人ディレクトフォースの7月勉強会は、7月13日に学士会館で約120人の会員参加のもと開催されました。今回の講師は元最高裁判所判事、現在はTMI総合法律事務所で弁護士をされている泉徳治氏にお願いし、「一票の格差と違憲立法審査権」というテーマでお話いただきました。
参議院議員選挙が終わったばかりの時期だけに、私たちが持つ一票の格差をあらためて実感するお話を分かり易く解説いただきました。さらに最近クローズアップされている再審の問題について、冤罪が起こりうる背景と冤罪を起こさないために現在検討されている取り組みについても説明していただき、会場からは本質を突く鋭い質問が出るなど民主主義や法治国家としてあるべき姿を考える貴重な勉強会となりました。詳細は次のとおりです。
1.一票の格差
今月11日に参議院議員選挙が行われ、神奈川県の千葉景子法務大臣が落選したが、得票数は69万6千票。私の郷里である福井県で当選した人の得票数21万2千票の3倍以上の得票数がありながら、神奈川では4番目となり落選した。福井県では3人の立候補者の得票合計が41万5千票で、千葉さん1人の得票数にも及ばない。今回、得票数が全国最低の当選者は高知県の候補者で13万7千票であった。これは何かおかしいのでないかという疑問が生じる。
参議院選挙区選出議員の場合、鳥取では49万2千人の有権者で1人の議員を選出することができるが、東京都では208万7千人の有権者でやっと1人の議員を選出することができる。東京都の有権者の一票の価値は、鳥取県のそれの0.23である。一票の価値に4.23倍の格差がある。東京都の有権者は、鳥取県との比較でいえば、実質0.23票しか与えられていない。衆議院小選挙区選出議員の投票についても一票の価値に2.30倍の格差がある。都道府県ごとの議員の定数あるいは選挙区の数(以下併せて「定数」という。)を人口に比例して是正し、一票の価値を平等にする必要がある。これが定数是正の問題である。
今回の選挙で各政党とも「国会議員の定数削減」を掲げていたが、定数削減は有権者を引き付ける有効なキャッチフレーズとなる。一方、定数是正の問題は、地方部で定員削減を招くことになるので、政党や議員が消極的であり、地味な問題であるためマスコミもあまり取り上げない。国会が自ら積極的には取り組もうとはしない埋もれた問題になっている。
2.公職選挙法と違憲立法審査権
国会議員の定数は、公職選挙法で定められ、人口に比例して配分され、10年ごとの国政調査の結果に基づき改正されることになっている。昭和25年に公職選挙法ができたときには人口に比例した配分であったが、その後人口が都市部に移動していった結果、現在のような格差が生じることになった。国政調査の結果に基づき配分の見直しをしなければならないのに、自分たちの議席が奪われることにもなるため、国会が是正を怠っているという状況にある。
憲法14条は、国民は法の下に平等であって「政治的関係」において差別されないとし、44条は、選挙人の資格を差別してはならないとしている。しかし、公職選挙法は、国民の持つ一票の価値に差別を設けている。現行の公職選挙法が憲法に違反するか否かを誰が判断するのかであるが、憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を、最高裁を頂点とする裁判所に与えている。これが違憲立法審査権である。
違憲立法審査権の事例として、婚外子の相続分を嫡出子の2分の1と定める民法の規定は憲法の平等原則に反しないかが、近く大法廷で審議されることになっている。また、最近の最高裁判決では、北海道砂川市が市有地を町内会に無料で貸与し、町内会がそこに神社を設けているという問題で、特定の宗教への地方公共団体の肩入れになるとして、憲法違反とされた。愛媛県知事が県費で靖国神社に玉串を奉納したことを違憲とした判決もある。
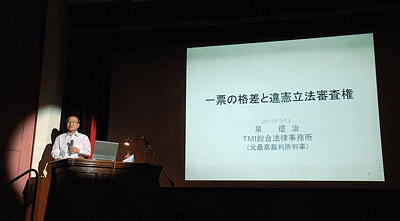
3.衆議院議員小選挙区選挙における格差
衆議院議員選挙区画定審議会設置法は、小選挙区に関してはまず各都道府県に1を配当し、残り253(300−47)を人口に比例して各都道府県に配当する、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口の最大格差が2以上にならないことを基本とする、行政区画・地勢・交通等の事情を総合的に考慮して合理的に画定する、と定めている。
人口にかかわりなく各都道府県にまず1を配当するとしているため、一票の価値の最大格差が1対2.304となり、格差2倍以上の選挙区が49にのぼる。平成17年の国政調査の人口に比例して配分を行えば、10の都道府県で合計19増加し、19の県で19減少し、最大格差は1対1.638に縮小する。ちなみに、東京は今の25にプラス5、神奈川はプラス3の定数となる。東京都は、選出議員が5人も足りないのである。
これまでの最高裁判決は、最大格差が3倍以上を違憲とし、3倍未満を合憲としている。平成17年9月11日の衆議院小選挙区選挙では、人口の最大格差が1対2.064に達し、42%の人口で小選挙区選出議員の過半数151人を選出することが可能となっていた。しかし、最高裁は、これを合憲とした。判決理由として、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が他の政策と調和的に考慮、実現すべきものであり、人口の都市集中、これに伴う過疎化の現象に配慮してこれを選挙区割りや議員定数の配分にどのように反映させるかという点も、国会が考慮することのできる要素であるとする。判決理由としては疑問の残るところである。政策的目的を投票価値に反映させるべきではない。
平成21年8月30日の衆議院議員選挙では最大格差が1対2.203となり、9つの選挙無効訴訟が高裁に提起されたが、この格差を違憲とする判決が7件、合憲とする判決が2件出た。この程度の格差の場合、最高裁は長年合憲としてきたが、高裁では違憲判決が主流派となった。本年末にも予想される最高裁判決がどのように判断するのか、興味が持たれる。
4.参議院選挙区選挙における格差
各都道府県の定数の配分を、公職選挙法発足当時のように人口比例にすると、現行6人の神奈川は8人となる。半数ずつの改選だから今回4人の定数であった筈で、千葉景子さんは当選していたことになる。同じく東京が2人、大阪が4人足りないというのが現状である。
ただ、半数改選の関係で各県に最低2人を配分する現在の枠組みを残す限り、人口比例によっても最大格差は1対4.86になり、なかなかうまくいかないが、議員の過半数を選出できる人口が現行の約33%から約40%に上がる効果がある。国会はこの改正すら怠っている。
参議院議員の数は242人と少なく、しかも3年ごとに半数の改選であるから、各都道府県を一つの選挙区として最低2人の定数配分を行うことに無理がある。各県に配分するのではなく、県をまとめたブロックで選挙を行うことが必要と考えられる。
これまでの参議院議員選挙に関する最高裁の判決は、最大格差が6倍以上は違憲、6倍未満は合憲としている。しかし、最高裁も、平成19年7月29日の参議院選挙区選挙について、最大格差1対4.84が直ちに違憲であるとまではいえないとしたものの、投票価値の平等という観点からは、この定数配分規定の下でもなお大きな不平等が存する状態であり、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれると述べている。国会は、これを受けて今回の参議院選挙後に検討するとしている。国会は、各都道府県を選挙区とする枠組みの見直しを含めて検討することになっており、今後どのような案が出てくるか興味のあるところである。
5.経済界の主張
経済界は、日経連や経済同友会をはじめとして、一票の格差是正を民主主義の基本的な課題として捉えている。そして、国会が制度改革に向けた具体的行動を取り、国民一人ひとりの意思が平等に政治に反映される仕組みを早急に実現することを求めている。
理由として、企業はグローバルな経済活動を行っており、貿易自由化、規制緩和を求める。また、法人税が韓国などで25%なのに対し日本は40%と、世界で競争を行っていく上で厳しい状況に置かれている。いびつな選挙制度では日本の制度改革、規制緩和が進まないという苛立ちがある。
国と地方で835兆円の借金を抱え、本年度予算の歳入は税収よりも国債発行の方が多いという財政破綻寸前の危機的状況にあればこそ、国民一人ひとりの意思が平等に反映されるよう、一票の価値を等しくする必要がある。
6.再審と冤罪
- 最近、足利事件、布川事件など相次いでの再審が話題になっている。何故このような冤罪が生じるのか。
犯罪の容疑者は、逮捕で3日、勾留で10日、必要なら更に10日の勾留延長で合計23日間拘束される。原則として警察の留置施設に入れられ、朝から夜まで取調べを受ける。取調べの状況は外部には分からない。このことが自白を引き出す有力な手段になっている。自白が犯罪捜査、治安維持にとって重要なことは事実であるが、逆に、やっていないことを自白させる危険性を持った制度ともいえる。しかし、これを簡単に廃止することはできないのが日本の現状である。
最近の事例では厚労省局長の虚偽公文書作成で、局長は勾留中に自白せず、公判でも否認を貫いている。自白しないで頑張ったことにより、保釈も認められず逮捕・勾留が165日にも及んだ。日本の刑事裁判の問題点といえる。
- 何か対応策があるだろうか。
警察の留置施設を廃止して法務省管轄の拘置所を増設することが提案されているが、物理的な問題や、取り調べる警察側からの反対があり、進んでいない。
また、取調べの可視化を図るために録音・録画することが提案されている。これについても、取調べに不都合という反対がある。どういう条件でなら可視化を実現できるか、議論の接点を探っている段階である。
取調べには必ず弁護人が立会いをするという提言に対しては、可視化より更に強い反対がある。
被疑者の人権を重視するとともに、犯罪摘発・治安維持という警察・検察側の要請にも対応するため、刑事免責、司法取引、有罪答弁、通信傍受、防犯カメラ等の代替制度による証拠収集を検討することも必要である。
足利事件のようなことは決してあってはならないことだが、逮捕・勾留・警察留置・取調べという制度の上に司法警察が成り立っているため、冤罪の危険がどうしても付きまとう。それを防ぐために、被疑者の段階で国選弁護人を付けることが最近制度化した。また、弁護人が被疑者にノートを持たせ、取調べの状況を記録させて、弁護側の有力な武器とする工夫もなされている。
取調時間を制限することは、警察・検察も受け入れ可能であり、警察自身も、取調べを1人の刑事に任せるのでなく取調監督官を置くこと提言している。
裁判官も、冤罪を防ぐために、過去の冤罪事例を検証するとともに、慣れの気持ちを捨て絶えず新鮮な眼で事件に向き合うように努めなければならない。
 |
 |
 |
 |
| 講演終了後の懇親会で講師の泉徳治氏を囲んで歓談する皆さん (写真クリック拡大) | |||
