
( 10/05/19 )
5月勉強会(2010/05/12)
テーマ:「今様の学生へのメッセージ」
 |
一般社団法人ディレクトフォースの5月勉強会は、5月12日学士会館で会員約100人が参加して開催されました。講師はベインキャピタル・ジャパン副会長、経済同友会幹事(教育問題ご担当)としてご活躍中の山中信義氏(写真)をお迎えして「今様の学生へのメッセージ」というテーマでご講演いただきました。
世界における日本の地位低下の現状を多面的な視点で指摘され、今後は個と知の時代になるから高い目標を持ち、その実現に粘り強く努力を重ね自分の「味」、自分の「におい」を発信できるようにならなければ生き残れないと、学生に語る切り口でお話いただきました。詳細は次のとおりです。
1.10年区切りの人生目標を持つ~自己紹介から
小さいときから夢を持つことが大事であり、その夢を達成するためには時間がかかるから道筋をつけ忍耐強く努力することが必要となる。自分は小学生のときからものづくりに興味を持ち、ものづくりのオムロンに就職したのち、GE,エマソンへと転職した。10年区切りの人生目標をもち、20代は何でも経験・勉強、30代で自分のスタイルを確立する、40代は成果を出す正念場、50代で組織のトップになり経営を担うことを目指し、60代には社会へのお返しとして日本企業の国際化を現場で支援することにした。これまで大体このスパンに沿って歩んできた。
20代のときに上司から言われた「常にその場で最善を尽くせば道は自ずとと開かれる」という一言で救われ、その後も色々な場面で迷ったときにこの言葉が力になっている。自分が信じる哲学や信仰を持てれば幸福になると学生に話している。
2.自分が発信する「個性」を持て
40年間の海外との仕事で感じたことは、日本、日本の文化、日本人が素晴しいことであり、日本はやはり大好きである。反面、日本人として恥ずかしいと思ったところは、自分の考えを主張しないから顔が見えない、大きな夢や目標、ワクワクする行動や思考がない、みんな同じで個性がないということ。
学生には、自分自身が発信する「個性」すなわち自分の「味」、自分の「におい」を持ち、それを出せることが自分の生甲斐になるはずといっている。
3.グローバリゼーションの現実とその意義
インドの中間層は約5,000万人、彼らの平均年収は日本の標準世帯年収の約3分の1である。
彼ら世帯数の半数は使用人を持ち、車を所有する世帯数の1割はお抱え運転手をもっている。
世界銀行の予測では、これら新中間層は東アジアを中心に急増し、2030年には12億人に達する。これが意味することは、彼らが経済の主役になり、世界規模の低価格革命を起こすということで、これによりホワイトカラーの給与の水準が下に引っ張られ、デフレの状況をもたらすから、これまでのように日本が成長するという時代ではなくなるということ。
2006年の米国では上位0,1%の所得層が全体収入の8%を独占した。この割合は過去20年間で約5ポイント増え、格差が拡大している。これは過激な競争に耐えうる独創的な知に富が集中すること、自分自身の「味」をポジティブに発信しない限り活躍できないことを意味する。
米国FRB元副議長アラン・ブラインダーは25年後には、平均的なコンピュータープログラマーよりも大工の方が収入は多くなっているだろうと予測する。世界の誰かに代替される職業、産業、人材は厳しいという。自分の個の確立を急いで欲しい。

4.世界における日本の位置
①日米の産業構造比較
アメリカは90年代に医療福祉サービス業329万人、プロフェッショナルサービス業243万人、情報サービス業310万人の雇用を創出したのに対して、日本における雇用構造は1995年から2005年までの間に一次産業100万人、製造業300万人、流通40万人が減少、サービス業が180万人の増で差し引き260万人の雇用が減少し、空洞化を生じた。この間に900万人、実に就業人口の7人に一人が異産業間で移動する大変化があった。その結果として、日本は活気があり成長する国になったかというと、ご存知のような状況で、残念でならない。
②日本の競争力
2005年21位、2008年22位アジアにおいても8位に転落。経済の基礎となる人、物、金の観点からみると
- 人:観光訪問先として日本は33位、アジアにおいても11位。WEFの観光魅力度という点では世界134カ国のうち131番目。留学生の分野では、大学のランクは東大が19位で留学生を惹き付ける魅力がなくなってきているといえる。
- 物:1980年には日本の3港が世界のトップ20港に入っていたが、2004年にはアジアから6港が入ったのに日本は東京1港に転落した。EDI(電子ドキュメント)で通関処理を行うのが世界で当たり前の時代になっているのに、依然として書面処理を続けるソフト面の無頓着さや受付時間を制約するなど仕組みや制度が疲労しているためで、物も日本を素通りするようになってしまった。
- 金:FDI(直接海外投資)で見ると、海外の投資家が日本に直接投資する額は日本のGDPの1.1%で、米国28%、英国32%、韓国11%に比べて日本は世界で最低クラスの投資魅力度といえる。逆に日本からは30兆円近くが国外に投資されており、他国が対内、対外ほぼバランスしているのに日本では1対5の出超となっている。
IMFの予測では、2030年には日本は経常収支が赤字になるといわれている。海外からの投資がなく、経常収支が赤字になれば日本経済は行き詰ることになる。
世界のなかでの日本の将来は、このままでは極めて危惧される。世界の視点で日本を正しく理解しなければならない。
③国際競争力低下の意味を考える
学生は国際競争力の低下は自分たちの生活に関係ないと考えている。しかし日本が国際競争力を落とし金が稼げなくなれば食糧輸入ができず、日本の食料自給率は39%に落ち込んでいることから夕食だけしか食べられないことになる。それで、彼らはようやく、意味が理解できる。
学生向けに言っていることは、①食べられることに感謝し、食べ残しをしないこと。年間食糧廃棄量は1940万トンで年間食糧輸入量の3分の1になる。これは途上国なら0.5億人分の食糧であり、世界の食糧援助量の3倍以上。②自分に何が出来るかを問い、行動に移すこと。国や会社、社会のせいにせず、当事者意識を持って自分が変革者たれ。③時事問題に真剣な好奇心を示すこと。本質を見極め、自分の立ち位置を見つける。政治的には投票で1票の権利を行使し、義務を果たすことなどと訴えている。
④日本の技術立国は心もとない
拡大する技術開発費(量的)の差で日本は地番沈下し、途上国の追い上げもある。学力の国際比較では、2000年から2006年にかけて科学リテラシーは2位から6位に、読解力は8位から15位に、数学リテラシーは1位から10位に低下し人的資源の質の低下が問題を複雑化させている。
理科離れから回帰する、危機感を共有し、もっと真剣に勉学に励むことが大事である。
⑤人的資源の脆弱性
将来自分の会社を作りたいという意欲を持つ若者が他国と比べ低い。若者に元気がない。やりたいことはいくら困難があっても挑戦してほしい。
学生には、簡単なことから始めよう、グローバルな視点を持ち、夢・目標を持って強烈な個を確立する、失敗を恐れず前向きに進め、実体験を通して本物になれ、成功するまで諦めるなとメッセージを送っている。
また、社会常識を磨いて人とのつながりを大事にする、自分自身の意見をもち臆することなく発表するコミュニケーション能力を身につける、過去の成功の方程式に頼ることなく自分の将来をグローバルな世界の中で見つけよと教えている。
5.企業が望む人材
①企業が求めているのはグローバル対応できる人間力のある人材
 今後は個と知の時代であり、多様化された社会・市場のなかで激烈な生存競争するのがこれからの世界である。勝てるのはごく僅かで、決め手は個としての知恵であり、それが生み出す価値となる。すなわち他人には出来ず、自分だけが出来る究極の差別化が生み出す価値である。
今後は個と知の時代であり、多様化された社会・市場のなかで激烈な生存競争するのがこれからの世界である。勝てるのはごく僅かで、決め手は個としての知恵であり、それが生み出す価値となる。すなわち他人には出来ず、自分だけが出来る究極の差別化が生み出す価値である。
求められる人材の型が変革してきており、与えられた問題に教えられた模範解答をする金太郎飴型優等生から、自ら判断し問題解決できる問題解決型の多様性人間で、これらが君たちに期待されていることだと認識するよう学生に求めている。
②経済同友会の調査
企業の新卒採用基準は面接の結果を圧倒的に重視し、続いて筆記試験の結果、適正検査の結果で出身校のウエイトはごく僅かなものとなっている。企業が採用試験で見るものは77%が熱意、意欲で、続いて50%近くが行動力、協調性となっている。
短時間の面接で本当に分かるのかという疑問があるが、虚像は見抜ける。熱意、意欲は懸命の実体験と実績がないと伝わらないし、自分の意思で最良の選択をする実体験がないと行動力が見えない。協調性とは安易な妥協を意味するのでなく、個性のぶつかり合いの中でのハーモニー、総合力を言う。論理的思考力と問題解決力は、本質を見抜く洞察力、実体験の中で育てた直感力が大切になる。学生にはこうした力をつけてもらいたいといっている。
6.今後活躍・成功するための人間力
①ポジティブ思考
物事には必ず楽観と悲観の両面があるが、ハーフフルで考えて、「出来ない」から「出来る」へと発想転換をはかる。こういう考え方が出来るか否かによって人生が大きく変わる。
②高い目標
何をしたいか夢を持とう。現在乗っかっている現実をきっちり認識しながら、将来何になりたいかぼんやりとでも考えを持つ。そこで現実と夢とのギャップをどのようにつめていくかの考え方をしよう。分からなければ好きなこと、得意なことに集中する。他人に負けない自分の強みを持てば自信が出来る。大事なことである。
③「没」個性から「活」個性
これからは個と知の時代。グローバルな世界はオーケストラと同じであり、他人が出来ないことができるプロの自分を確立し、みんなとプロの技で共生をはかる。決して、無国籍化ではなく、今まで以上に日本人であることが、世界で活躍する原動力となる。
④まず行動
70%でスタートし、120%の情熱でやり遂げる。思うだけでは何も変わらないから目標を細切れにし、120%の努力と情熱を持ってたえず70点を確認しPDCサイクルをまわしながら軌道修正して進む。
⑤ディズニーの名言
北京オリンピック女子ソフトボールで金メダルを取った上野選手がインタビューで述べた言葉、「最後は気持ちの強い人間が勝てることを知ったのが自分にとって最も価値ある金メダル」に感動する。ウオルト・ディズニーも「成功する者は共通して Curiosity(何事にも知的好奇心、強い関心をもつて)、Consistency(しつこく同じことを何回でも)、Continuity(成功するまで継続する)の3Cを持つ」と言っており、これが成功する者のゴールデンルールである。
是非、以上の哲学で、自分の個性を最大限に活かせ、社会に貢献でき、自分自身の人生を全うすることが重要だと、学生に声を枯らして訴えているのが現状です。本日はご清聴、どうも有難うございました。
 |
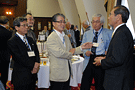 |
 |
 |
| 懇談会で講師の山中氏を囲んで歓談する皆さん (写真クリック拡大) | |||
