
( 19/05/29 )
4月勉強会(2010/04/14)
テーマ:「最近の経済金融情勢―アジアの中の日本」
 |
一般社団法人ディレクトフォースの4月勉強会は、4月14日学士会館で会員約140人が出席して開催されました。
今回は、講師に経済学者で元大和総研常務理事、日本銀行政策委員会審議委員として活躍された田谷禎三氏(写真)をお迎えし、テーマは「最近の経済金融情勢―アジアの中の日本」でした。金融危機後の世界経済ならびに日本経済の現状と展望について、幅広いデータにもとづき簡明に解説していただきました。日本は、経済規模拡大を続ける東アジアへの輸出ウエイトが高まるなど比較的恵まれた輸出環境にありながら未だ経済回復の足取りが重いのは、個人消費の大半が依存する雇用者所得が下がり、消費が減退しているためと指摘されました。詳細は次のとおりです。
1.金融危機の現状
①主要金融資産にかかわる評価損
英国中央銀行の推計では、欧米における主要なデット証券の評価損にかかわる損失額は昨年3月半ばの4.1兆ドルから12月時点では0.4ドルまで減少し、住宅担保証券を中心とした今回の金融危機は収束過程に入ったといえる。ただ、大きな不良債権を無理して処理してきた金融機関は積極的な貸出し行動をとらないから、世界経済の見通しは慎重にならざるを得ない。
②銀行の資本、評価損
IMFによる昨年10月の分析と4月時点とを比べると、各国、各地域ともリスクに対する必要資本調達金額が下方修正されている。ただ、ユーロ・エリアの銀行は米国の銀行に比べまだ相当の増資を必要としている。相対的には大陸欧州諸国の銀行による損失の認識が遅れており、暫くは積極的な貸出し、信用創造はしないであろうから欧州の経済回復にはまだ時間が掛かる。
③金融規制の動き
最近の金融危機と関連した日米英の中央銀行のバランスシートの拡大は、第2次世界大戦時にも匹敵する。日本の不良債権問題や一昨年以来の英米の金融危機がいかに大きな出来事であったか歴史的視点からも理解することができる。
同じことを繰り返さないために、大きくなりすぎてつぶせない金融機関の出現にどう対応するかが問題となる。バブルを繰り返す共通項は、実態に合わない低金利が長く続き、その間金融機関が融資に積極的になる、大勢が将来に楽観的になることである。これには中央銀行にも責任があり、米国でいま、金融機関規制監督体制改革の焦点となっている。
これとは別の問題として、国際金融機関が国際的活動を行う上でルールとして一定以上の資本金をもつべきとされている。バーゼル銀行監督委員会は、資本の質そのものの向上を図ることが重要であるとした規制案を10年末までに策定し、12年末からの実施を目指している。
日本の金融機関に関していえば、欧米の金融機関が内部留保の積み増しと増資によって自己資本比率の引き上げを図ってきたのに対して、日本の銀行の対応が遅れている。

2.世界経済の現状と展望
①世界経済の見通し
国際機関による世界経済の見通しは昨年4月以降上方修正されてきた。ただ、先進諸国の景気回復は緩慢である。一方、エマージング途上国は比較的順調な回復を遂げつつある。社会インフラ整備など内需の基調が強く、バランス・シート調整問題がない中で財政刺激策がとられ、先進諸国からの資本流入が起こっていることが背景にある。対中輸出がけん引役となって東南アジアの成長率はかなり高い。先進国の中では日米に比べて欧州諸国の動きが鈍い傾向が続きそうである。
②米国の経済成長
米国の実質GDP成長率は、昨年マイナス2.4%であったが、第3四半期からプラスに転じており、今後とも緩やかなプラス成長が見込まれている。ポイントは71.1%のウエイトを占める個人消費の動向にかかる。
住宅価格は底入れしたように見えるが、財政金融政策の効果によるところがあり今後とも回復を続けるかどうかは不透明。米国経済に対する景況感は、非農業雇用者の変化幅に多分に左右されてきているが、この減少幅は徐々に小さくなっており最近プラスに転じた。ただ、このまま増加していくかどうかは慎重に見極めたほうが良い。
個人貯蓄率は1980年頃から資産価格の上昇に伴って減少を続けてきた。金融危機によって資産価格が一挙に下落したことにより、貯蓄率は上がり始めている。裏を返せば消費が低迷しているともいえる。
米国は現在ほとんどゼロ金利となっている。金融機関のバランスシートが相当痛んでいることと、1930年代の長期化した景気後退は早すぎる緩和策放棄に原因があった経験から、金融財政政策として緩和策からの早期脱却には慎重になると考えられる。
このように住宅価格が下げ止まり、非農業雇用者がプラスに転じ、消費志向の強い米国人が貯蓄にそれほど熱心にならないと考えれば、米国経済は緩やかに成長するとの見方もありうる。
③欧州の経済状況
欧州の経済情勢は日米に比べて厳しく、経済成長はゼロの状況である。それは次のような理由による。
- 欧州の銀行は米国銀行に比べて損失の認識が遅れているし、対応も遅れている。従って前向きの資金供給をする態勢にはなく、信用創造機能が弱まっている。
- 欧州においてもドイツなど一部を除いて住宅バブルとその崩壊が存在した。崩壊は米国に遅れて発生したから調整も遅れている。
- 欧州にとっては、日本における東アジア、米国にとっての中南米に相当するのが中東欧諸国であり、有望な市場であった。中東欧諸国は大量の資金流入による資本収支の黒字に依存して経済規模を拡大してきたが、国際金融市場の影響で短期的にはそうした状況を修正する必要に迫られ、厳しい経済調整を強いられている。
- 欧州諸国も財政政策発動の余地は限られてきており、ギリシャ支援は負担となる。
④中国の経済成長
中国は政治的安定を維持するために、経済成長を続けなければならない。ところが拡大ペースは08年末まで輸出が足を引っ張り急落した。そこで08年11月に、2年間で4兆元(GDP30兆元の13%)の景気支援策を発表。公共投資を増やした効果により、09年に入り景気が回復する。
中国の経済成長は主として内需特に設備投資の伸びによる。問題は日本と同様に、消費の経済成長への寄与は小さい。消費が伸びない理由は企業が利益をあげても設備投資に再投資し、所得、賃金が上がらないからである。
中国の金融政策は金利によってではなく、銀行融資を直接コントロールする窓口指導によって行われてきた。08年11月中央銀行による窓口指導が廃止され銀行融資は急増、マネーサプライの伸び率も高まった。経済成長率の目標を達成するためにとられたこの金融財政緩和措置の副産物として資産価格の上昇をもたらしたが、日本で起こったバブルとの相違点は、バブルの認識がある、2桁近い経済成長力があるなかでの物価上昇であること。従って日本のようにバブル崩壊、その後停滞でなく、バブル崩壊、バブル崩壊を繰り返しながら成長していくであろう。
中国の輸出構造として、対米国、対EUで大幅黒字、対日本、対韓国、対台湾で赤字となっている。ただ日本、NIEs、ASEANから輸入し、欧米へ完成品を輸出する側面がある。欧米向け輸出が本格的に回復するまで中国の経済成長力の加速は期待しにくい。
3.日本経済の現状と今後の展望
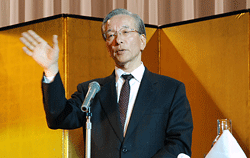 ①日本のGDP
①日本のGDP
2002年から2008年まで輸出が引っ張って2%程度の成長を続けてきた。しかし消費は1%程度しか増加しなかった。原因は、雇用者の数は伸びたものの賃金が全く上がらなかったことにあり、ここに日本経済の問題点がある。
②売上、経常利益
昨年10-12月期の売上高は前年比3.1%減であるが、経常利益は102.2%増であった。経常利益の回復要因は、売上減少のマイナスに対して変動費の削減と人件費の継続的引き下げがプラス寄与していることにある。労働分配率は昨年第2四半期以降下落し、90年代に入って以来の平均値に回帰してきたので雇用調整圧力は徐々に緩和していくと考えられる。
③設備投資動向とキャッシュ・フロー
昨年以来、キャッシュ・フローが回復する中で設備投資の減少が続いてきた。設備投資額が減価償却費を下回り、設備ストックの削減が進んだ。昨年12月の日銀「短観」によれば設備投資の底入れは近いと思われる。一方フリーキャッシュ・フローの処分については大企業、中小企業とも共通して内部留保に向けており、今後この内部留保がどのように使われるかによって日本経済は大きく変わってくる。
④日本の輸出構造
日本の輸出構造として、輸出金額、相対的シェアにおける東アジアの重要性は、米国あるいはドイツにとっての東アジアの重要性より大幅に上回っている。最近の10年で見ると対米輸出はほとんど増えていないが、NIEs、ASEANとの貿易が拡大、特に中国に対する輸出の伸びが突出している。
⑤日本の歳出と税収
財政赤字が拡大している。日本政府の債務残高はOECD諸国の中で最悪となっている。問題は歳出よりも歳入にある。歳入40兆円のうち所得税15兆円、法人税10兆円、消費税10兆円であり、消費税の増税と歳出削減で健全化をはかるしかない。これが出来ないのは危機感がないからで、その原因は国債発行残高が増えてきたにもかかわらず過去の高金利国債を低金利で借り替えてきたことにより利払い費が下がってきたことにある。金利の上昇がきっかけとなるまでは財政再建の動きが出ないのではないか。
⑥デフレ傾向と賃金
日本の消費者物価指数は90年代中頃からマイナス傾向にある。日本と欧米の物価変化率の差は主としてサービス価格の動きから来る。そしてサービス価格の動向は賃金の動きによって説明できる。他の主要国と違って日本の単位労働コストは継続的に下がっている。賃金が生産性の伸びを下回っているからで、この動きは日本企業が90年代半ばから債務の返済を続けたことにより賃金の引き上げが抑制されたからではないかと考えられる。企業の過剰債務返済は2007年頃に終わったはずだが、外からのショックで元に戻ってしまった。
ただ、企業によっては定昇を認めようという動きがあるように、デフレ脱却のメカニズムが働きかけている兆候がみえる。
⑦質問に答えて ー国債価格暴落はありうるか、そのシナリオはー
米国やドイツの長期金利が、低金利から高金利グループに入っていった変化の時期は、経常収支が赤字化した時期即ち純資本輸入国になった時期と一致する。
日本の経常収支が赤字化するかといえば、経常収支、国際収支のアンバランスは国内貯蓄が減少することから起こる現象であるから、ありうるといえる。政府、家計の貯蓄バランスはこれから悪化し続ける。企業がこれをカバーするだけの貯蓄を供給することは出来ない。貯蓄が十分か否かの観点から言えば経常収支の赤字化はありうる。このとき金利が上昇することになり、国債価格は下落する。
 |
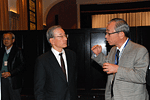 |
| 懇談会で講師の田谷氏を囲んで歓談する皆さん (写真クリック拡大) | |
