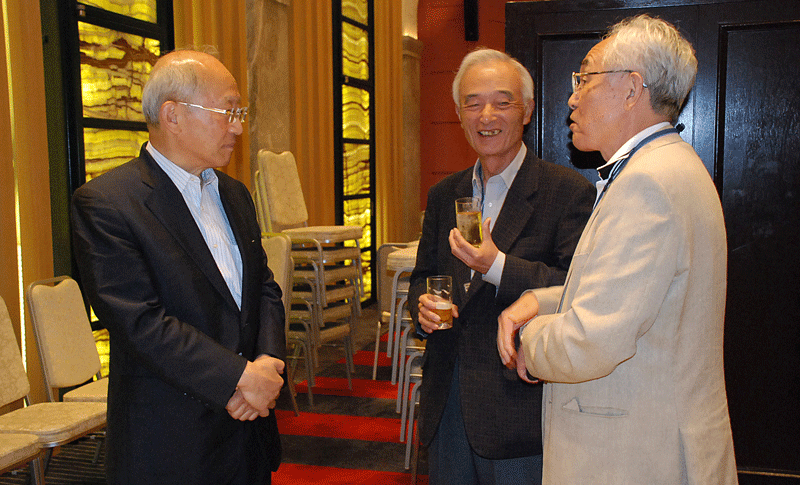(2013年6月26日 )
一般社団法人 ディレクトフォース 6月 講演・交流会
テーマ:「戦略とは戦わずして勝つこと」
 一般社団法人ディレトフォースの6月講演・交流会は、6月12日学士会館において会員約80人が参加して開催されました。今回はカルビー株式会社前代表取締役社長の中田康雄氏を講師にお迎えし、「戦略とは戦わずして勝つこと」というテーマで講演いただきました。
一般社団法人ディレトフォースの6月講演・交流会は、6月12日学士会館において会員約80人が参加して開催されました。今回はカルビー株式会社前代表取締役社長の中田康雄氏を講師にお迎えし、「戦略とは戦わずして勝つこと」というテーマで講演いただきました。
中田氏は卓越した手腕で同社を東証一部に上場させ、株価を上場時の4倍にするなどカルビー社の企業価値を高めることに多大な貢献をされた方です。創業家以外から初となる社長に就任されました。商品開発と鮮度保証、営業改革の推進などたゆまない経営イノベーションを続け、業界で確固たる地位を築いてこられました。退社後は、経営コンサルタントとしてご活躍になり、若き経営者やビジネスパーソンの教育に力を入れておられます。
今回のお話では、カルビー社の経営戦略を紐解かれ、実践されたオリジナルの戦略をお聞きすることができました。詳細は以下のとおりです。
1.良い戦略とは
カルビーが成長してきた戦略、方法論を紐解きながら良い戦略の意味ないしは価値をご説明したい。戦略とは「戦わずして勝つこと」であり、その要諦は圧倒的優位を築き、他と差をつけることにある。いわば省エネ的ビジネスモデルともいえる。良い戦略の条件は、一見非常識と思われることにチャレンジすることである。業界はそれを冷やかに見て追随してこない。しかし非常識とみられることが最も合理的な構図を持っているものである。
2.2012年度の連結決算
売上高1,794億円、営業利益158億円で利益率はまだ10%に届いていない。10%達成が当面の目標である。流動資産、固定資産がほぼ半々、75%が自己資本であり財務的には良い形になっている。今後はキャッシュフローをどのように攻めに使うか、着眼点が大事になっている。食品業界では中堅ではあるが、グローバル企業へと変身を図ろうとしている。
3.カルビー成長の軌跡
成長イメージの起点は1965年「かっぱえびせん」の発売で、スナックカテゴリーのマーケットを作り、会社の成長をけん引する中核商品となった。ちょうど量販店が台頭してきたときで販売網の拡充やマーケットの拡大にうまく乗ることができ、食文化のイノベーションがここから始まった。
「かっぱえびせん」発売から10年が経ち成熟期に入ったとき、新発売した「ポテトチップス」が金鉱を掘り当て成長の新しいけん引役となる。これが10年の踊場に達したとき、コーンフレークを発売し、シリアルフーズ分野に参入。アメリカを中心に共稼ぎ、ダブルインカムの家庭の手軽な朝食という食文化が前提にあった。ただ日本では、朝食が豊かで大きくは伸びなかった。しかしその後、女性の社会進出という環境変化により、マーケットが広がりイノベーションを起こした。10年の成長期を経たところでポテト系スナックをアレンジ。10年後にさらにポテト系スナックを開発したが、これが現在成長中。
このように商品のロングライフ維持を図りながら、10年ごとに新しい柱となる商品を提案し、確実に成長させてきたことが大きな特長といえる。
4.2009年に大きな山
アメリカのペプシコ社とスナックフ-ズ事業で競合していたが、資本提携により戦略的アライアンスを組むことにした。ペプシコ社がカルビー社の資本の20%を取得、カルビー社はペプシコ社の日本法人を100%子会社とすることにした。これを契機にカルビーは上場を果たす。子会社買収により、カルビーに欠けていたカテゴリーであるコーンを原料としたスナックを手にしてグローバル展開の方向性を定めることができた。4兆円の売り上げを持ち、世界的流通網を備えたペプシコ社とのアライアンスはグローバル展開の可能性をもたらすものであった。
5.戦略ストーリーの作り方
一橋大学大学院教授の楠木建さんが「ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件」という本格的経営書を著しておられる。骨子は次の3つである。
- 実現すべき「コンセプト」をはっきりとイメージする
優れたコンセプトを構想するためには、誰に、何を、なぜをはっきりさせる。 - ひとたびコンセプトが確定したら、あらゆる打ち手を明確な因果論理でつなぐ
「なぜ」はストーリーを動かすエンジンである。すなわち、なぜ個別の構成要素が齟齬なく連動し、全体として事業を駆動するのか。なぜある打ち手が次のうち手を可能にするのかを明確にする。 - クリティカル・コア キラー・パス(サッカーでいう決定打)を埋め込む
それだけでは一見して不合理だけれど、ストーリー全体の文脈に位置付けると強力な合理性を持っている打ち手を見つける。
この戦略的ストーリーの作り方を具体例でいくつか検証する。
6.戦略ストーリーの構成要素(スターバックスの例)
スターバックスのコンセプトは家庭や会社と違った「第3の場所」であり、癒し、憩の場所であること。そのためのクリティカル・コア(キラー・パス)は多店舗化を狙うフランチャイズ方式ではなく、ある意味で非常識の「直営方式」である。このキラー・パスにより店舗の雰囲気、出店と立地、スタッフ、メニューなどの構成要素(パス)において創業者のこだわりによる独自性を維持し、コンセプトに沿った店舗をつくりだしている。その結果競争優位(シュート)をもたらし、お客の支持を得てお客が喜んでお金を払うWTP(Willingness to Pay)効果が増大することによって最終的に長期利益というゴールを得ている。
7.サウスウエスト航空の戦略ストーリー
 アメリカで近距離に集中し成功した航空会社の例である。サウスウエスト航空は、「長距離バスの利便性と低価格を飛行機で実現する」ことをコンセプトとした。そのためのクリティカル・コア(キラー・パス)は、ある意味で非常識ともいえる「ハブ空港を使わない小規模空港間の直行便」であった。コンセプトの「利便性」は、ハブ空港を経由しないことであり、「低価格」は徹底した効率化の追求であった。低下価格実現の最たるものは駐機時間の短縮であり、15分ターンとそのための定時運行であった。そこで打ち手としたのが、乗り継ぎ荷物サービスをしない、乗り継ぎを前提としないフライトスケジュール、チーム編成によるフライトごとのオペレーションであり、現場への権限移譲による自由裁量に基づく意思決定とチーム単位の評価・報酬システムであった。コンセプト実現と低い人件費により持続的利益を実現している。
アメリカで近距離に集中し成功した航空会社の例である。サウスウエスト航空は、「長距離バスの利便性と低価格を飛行機で実現する」ことをコンセプトとした。そのためのクリティカル・コア(キラー・パス)は、ある意味で非常識ともいえる「ハブ空港を使わない小規模空港間の直行便」であった。コンセプトの「利便性」は、ハブ空港を経由しないことであり、「低価格」は徹底した効率化の追求であった。低下価格実現の最たるものは駐機時間の短縮であり、15分ターンとそのための定時運行であった。そこで打ち手としたのが、乗り継ぎ荷物サービスをしない、乗り継ぎを前提としないフライトスケジュール、チーム編成によるフライトごとのオペレーションであり、現場への権限移譲による自由裁量に基づく意思決定とチーム単位の評価・報酬システムであった。コンセプト実現と低い人件費により持続的利益を実現している。
8. 青山フラワーマーケットの戦略的ストーリー
首都圏を中心に小規模店舗での花の販売をビジネスモデルとするパークコーポレーションの例である。コンセプトは、「日常気軽に花を買うことができる、花のある生活」。そのクリティカル・コア(キラー・パス)は、非常識ではあるが合理的ともいえる「冷蔵ケースを使わない」こと。在庫を持たず、鮮度劣化が見えるから小さい店舗スペースを使って2〜3日で売り切りロスを圧倒的に抑える。これで低コスト、低価格を実現した。
もう一つのクリティカル・コア(キラー・パス)は、「ビジネスの目的を社員の成長」として店長の裁量余地を最大化すること。店長は顧客視点で環境や顧客にあわせた品揃えをし、リピーター増加につなげた。こうしてWTP(Willingness to Pay)効果増大を実現した。
9.カルビーの鮮度保証戦略
カルビーの事業戦略の一つとして、「スナックは生鮮食品である」というコンセプトのもとに、おいしさと安全性を保証するためお客様へのリードタイムを短くする鮮度保証を取り上げた。クリティカル・コア(キラー・パス)は「パッケージに日付表示」とした。ポテトチップス発売間もない1970年代後半のことで、その当時加工食品の日付表示は未だ行われていなかった。流通業界を中心に、製品が古いと分かれば売れなくなると反対意見があったがあえて挑戦した。日付表示はその後徐々に浸透していったものの、2000年には賞味期限表示に変更する法制定があった。賞味期限表示では、鮮度表示を後退させるものと考え、日付表示と賞味期限表示をパッケージ正面に併記することを続け、打ち手を次々に展開した。
鮮度状況把握のためには測定が必要で、そのためにモニタリングの仕組みを作り、定点観測を始めた。全国6000店以上のスーパーマーケットで競合商品を含め、鮮度が手に取るようにわかるようになる。鮮度維持をはかるため、流通スピードが落ちることがないよう流通を巻き込んだ在庫圧縮などのプロセス改善を行った。鮮度が落ちるのは商品力が足りないと受け止めて商品の改善・改廃を進め、より魅力的な商品を提案した。コンセプトをしっかり伝える訴求広告と店頭プロモーションにより生鮮食品なみの鮮度を保つことで顧客の満足を得て継続的売上を確保することができた。
鮮度管理継続により、商品の開発・改善に力を入れ、サプライチェーンを巻き込み、店頭におけるプロモーションの質的向上をはかるようになる。鮮度は企業の総合力、ビジネスの品質を表すものと捉えられるようになっている。
10.製品のライフサイクルのイノベーション
商品の衰退を食い止め、いかにライフサイクルを延長させるか。これが新しい商品の積み上げ、市場創造、マーケット拡大につながる。このコンセプトは「ファッション商品」で、わくわくするような商品を次々と提案することにある。これによって既存商品が見直され関心を惹くことでロングライフとなる。キラー・パスは、「意図的なカニバリ商品の提案」である。打ち手として、期間、地域、チャネル限定の商品開発、ポテト品種、製法、味付けの多様化であり、そこから販促の多様化を生み出す。ファッション商品として販促費の削減につながり、売り上げと利益の継続的拡大をもたらすことになる。
11.原料に関する戦略
ポテトの質と量をいかに保証するかがキーファクターであり、そのコンセプトは「農業で商品と品質を作り込む」である。それを実現するキラー・パスは「生産者との直取引による契約栽培」で、原料の量、価格、品質を確保しようとするもの。当時は農協を通すことが常識で直取引は非常識であった。ここでもイノベーションを起こした。価格は個別の評価により決める、品質は消費者起点の規格設定による、品種改良・開発は基準を明確にして良し悪しによって価格を決め品質インセンティブを設定することに。栽培アドバイス、フィールド管理を行い、農家に協力して品質保証を展開した。それと同時にカルビーが在庫リスクを引き受けた。全量を買い取り、貯蔵庫への投資を行い温度、湿度、酸素を管理し計画的貯蔵をするようになった。同時に貯蔵技術の革新によりパレットごと管理が可能となり、お客様に生産者情報を提供できるようになった。これらの打ち手によって、長期的継続的利益改善がはかれることになった。
以上のように鮮度管理、ライフサイクルの拡大、原料の品質保証の3つがカルビーの成長戦略である。
以上
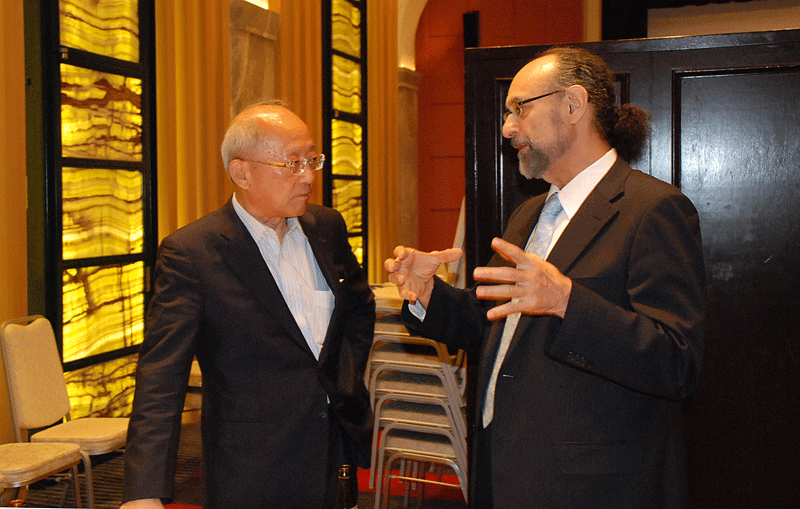
|
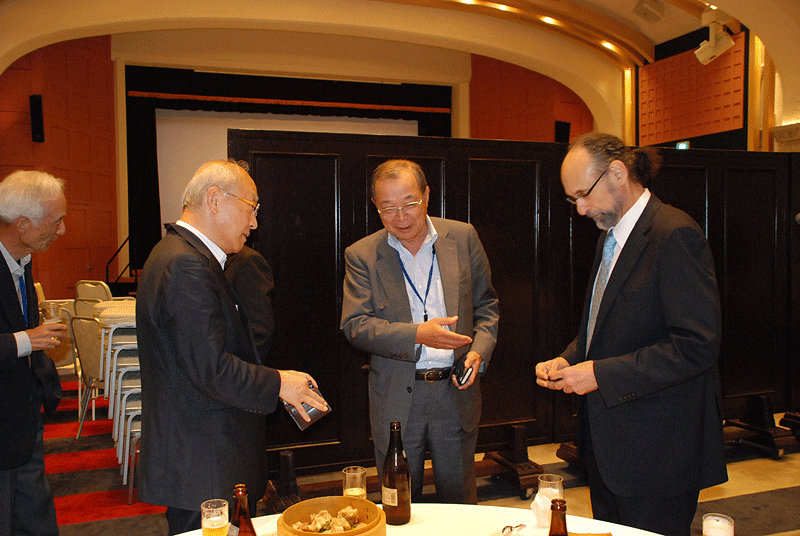
|
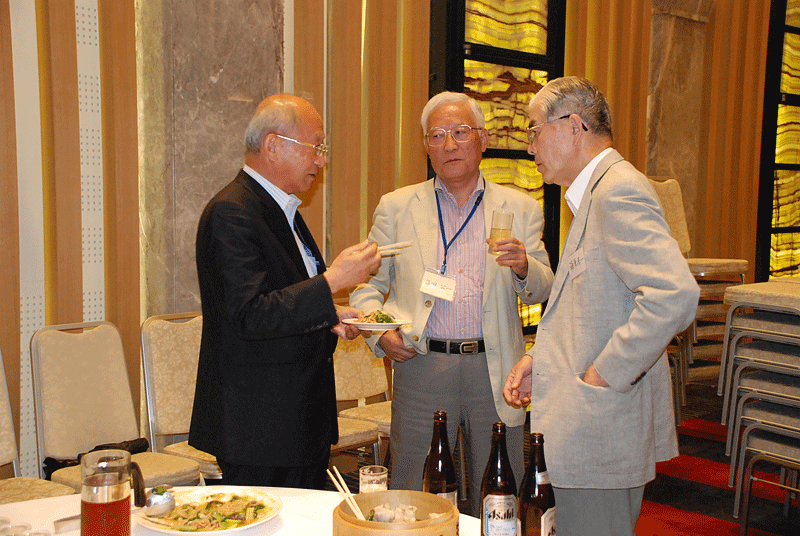
|