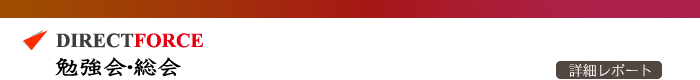
(2013年1月8日 )
一般社団法人 ディレクトフォース 12月勉強会
テーマ:「長寿社会を生きる」

一般社団法人ディレクトフォースの12月勉強会は、12月18日学士会館で会員約100名が参加して開催されました。
今回は東京大学高齢社会総合研究機構特任教授の秋山弘子氏を講師にお迎えし、「長寿社会を生きる」というテーマでご講演いただきました。秋山氏は社会心理学がご専門ですが、高齢社会の課題を生活者として、高齢者の視点で考えるジェロントロジー(老年学)の第一人者でもあります。高齢者の心身の健康と経済、加齢に伴う人間関係の変化を20数年にわたる全国高齢者調査を基に研究されてこられました。近年は首都圏と地方の2都市で長寿社会のまちづくりという社会実験に取り組み、超高齢社会におけるより良い生活のあり方を追求しておられます。
人生90年といわれる時代に入り、これまでとは違った社会システムの構築が求められる今、長寿を生きるためにどのように考え、なにをなすべきか大変興味深いお話を伺うことが出来ました。詳細は次のとおりです。
1.日本人の平均寿命
日本人の平均寿命は男性79歳、女性86歳となり、人生90年時代といわれるようになった。古い人生区分は第1期子ども、第2期大人、第3期老人であったが、20世紀後半の寿命革命によって第3期は前期高齢者、第4期が後期高齢者という新しい人生区分がなされるようになった。第3期と第4期の線引きは明確ではないが、75歳が目途といわれている。第4期は寿命革命によってもたらされた新しいライフステージで、まもなく人口の20%を占めるようになる。第4期の後期高齢者はいわば新人類であり、科学的データにもとづく理解がこれからの課題となる。
2.超高齢社会の課題
- 個人の課題 人生90年の設計
われわれは人生50年ないし60年の生き方は知っている。それは、20歳ぐらいまでに教育を終え、就職し結婚そして定年まで働く。定年後の余生はそれほど長くないというワンパターンの生き方であった。長寿化して人生90年となれば、自分の価値観や能力に従って自由に設計していくことが出来る様になる。2つ以上のキャリアを経験する多毛作人生も可能であり、多様な人生設計ができる。若いうちに情報を集めて、自分の人生の締めくくり方を人生設計の中に入れておくのも良い。しかし言うは易いが実行することは難しく、人生90年の設計が個人の課題となる。
- 社会の課題 社会のインフラの作り直し
長寿化と出生率低下により人口に占める高齢者の割合が大きくなっている。1950年には65歳以上は5%以下であった。現在は24%であるが、2030年には30%が高齢者、20%は75歳以上の後期高齢者となる。ところが現在の社会のインフラに関しては、建物、交通などのハードならびに医療、介護、教育、雇用などソフトは人口構成がピラミッド型の時に出来たものである。高齢者が増え、後期高齢者が社会の20%を占めるようになったときには社会のニーズに対応できるものではなくなる。これからは社会のインフラが大きな課題となる。
- 産業の課題
社会のシステムやインフラの建て直しをはかり、新規に構築すれば新しい産業を創成することが出来る。アジアでは中国、インド、インドネシアなどにおいて速いスピードで高齢化が進む。日本と違って、経済成長を遂げた後に高齢化するのではなく、経済成長と高齢化が併行して進んでいく。しかしこれらの国々は高齢化の波が押し寄せることを理解しながらも経済成長を優先せざるを得ず、社会政策は後回しになる。それだけに高齢化トップランナーの日本を注視している。長寿社会における新しい生き方、それを支える社会のインフラをいかに構築し、産業化させ輸出していくかが日本の産業界の課題である
3.ジェロントロジー
ジェロントロジー(老年学、加齢学)は、人の生活のあらゆる側面、社会の主要なシステムや制度、様々な産業と深く結びつく課題解決型の学際的な学問である。
- ジェロントロジーの歴史(1) 人の寿命をどこまで延ばせるか
当初は寿命をどこまで延ばせるか研究するため、加齢による生理的老化の原因解明あるいは成人病(生活習慣病)の克服を研究するバイオメディカル(老年医学)が進められてきた。1970年、80年になると人口の高齢化が社会制度、経済、医療機構などに影響を及ぼし始める。その負担を社会学、経済学、心理学などの分野で制度的、財源的な側面から研究するようになり社会科学の分野でも高齢社会の研究が盛んに行われるようになった。
- ジェロントロジーの歴史(2) 生活の質の追求
2000年近くになると日本だけでなく先進国で平均寿命が急速に伸び始めた。ここで老年学の研究は人の寿命をどこまで延ばせるかという量の課題から高齢期をいかに健康で豊かにに過ごすかという質の問題に大きくシフトした。疾病や障害など高齢期のネガティブな側面に焦点をあてた研究から、高齢者のうち80%以上を占めるといわれる健常者の生活の質(Quality of Life)をいかに向上させるかという高齢期の可能性に焦点をあてた研究に転換する。その理念はサクセスフル・エイジングである。そのために医学、看護学、生物学などだけでなく、経済学、心理学、社会学等あらゆる領域の学問が加わる学際的学問としてのジェロントロジーが生まれた。
- サクセスフル・エイジング
1987年、科学雑誌「サイエンス」にジョン・ロウとロバート・カーンがサクセスフル・エイジングを論文に発表。サクセスフル・エイジングの要件として、病気や障害がなく、高い身体・認知機能を維持しながら社会との繋がりを持ち、社会に貢献する「人生への積極的な関与」を提唱した。大きな反響があり、多くの支援を得て10年後には科学的検証にもとづくサクセスフル・エイジングのハウツー本を出版。これにより米国ではサクセスフル・エイジングが国民的運動となり、人々のライフスタイルを変えるのに貢献した。
4.高齢期の可能性
人間の能力の変化は多次元で多方向である。20歳ごろをピークに人間の認知能力は低下していくといわれてきたが決してそうではない。短期記憶能力や使わない能力は加齢によって衰えるが、日常問題解決能力や言語能力は衰えることなく向上している。60歳を例にとれば低下している能力もあるし、発達している能力もある。その意味で多方向性を持っている。大事なことは人生の各段階で自分が持っている能力を最大限に活用して生きることである。
5.高齢者人口の高齢化
年齢を4区分して人口の年齢構成の推移を見ると、これから18年先の2030年には約3分の1が高齢者(65歳以上)、20%が75歳以上になる。人生第3期前期高齢者の絶対数、比率はほとんど変らないが、第4期の後期高齢者人口は1000万人増えて倍になり、人口構成比が20%になる。
そして高齢化するのは東京をはじめとする首都圏並びに大阪、愛知など主要都市の人口。これまで高齢化は農村部の問題とされてきたが、それは1960年、70年の高度成長期に若者が都市部に進出したことによる。この時期移住した団塊の世代がこれから高齢化していく。20年後には高齢者の13%から15%が認知症を患うといわれる。また半数近い人が1人暮らしをしている社会になるだろうと推定されている。予測されるこうした社会では今のインフラではとても対応できない。
高齢者の友人、近所の人、親戚との対面接触は、女性と違って男性は次第に回数が減少してきている。個人の心構えに訴えるだけでは解決できない。社会の仕組みの中に人のつながりを増やし維持する仕掛けをどのように埋め込んでいくかを考えなければならない。
6.加齢による生活の変化 全国高齢者パネル調査から
全国の住民基本台帳から60歳以上の住民約6000人を無作為に抽出して、全国高齢者パネル調査を1987年から20年間継続してこれまで7回実施してきた。高齢者の生活における3つの要因である健康、経済、社会関係が加齢によってどのように変化していくかを同一人について追跡調査していくもの。このうち機能的健康は、世界的に自立の指標とされるADL(自分で風呂に入れるなど)、IADL(日用品の買い物をするなど)によって測定している。 この結果日本人について分かることは、男性については3つのパターンがあること。約20%は70代になる前に死亡する。これは生活習慣病によると考えられる。10%強は80歳、90歳になっても元気に過ごしている。残り大半の70%は70代半ばぐらいまでは1人暮らしが出来る程度に自立しているが、その後は少しずつ自立度が落ちていく。女性は10%強が70代前に亡くなるか重度の介護を必要とするようになる。残り90%近くは70代初め頃から男性よりもっと緩やかに自立度を失っていく。
7.今、なにをなすべきか
人口動態の流れ、生活における自立化の低下などのデータに基づいて今なにをなすべきか。3つの課題が考えられる。
- 自立期間(健康寿命)の延長
男女合わせた全体の80%は70代半ばまでは元気だが、それ以降自立度が下がっていく。75歳以上の人口がこれから1000万人増えて人口の20%を占めるようになると、これらの人が自立度を失っていくことは大きな問題である。自立度が落ち始める年齢を少しでも上げること、元気で働こうと思ったら80歳ぐらいまで働けるように仕組みを変えていくことが必要となる。
- 住み慣れたところで日常生活の継続を支える生活環境の整備
80歳ぐらいまで健康寿命を延ばしても、全員がピンピンコロリとはいかない。ある程度虚弱期間を経て亡くなることが普通と考えられる。したがって、体が弱くなっても安心して快適に生活できる環境を整備していくことが課題となる。
- 人の繋がりづくり
人の繋がりの希薄化が深刻な問題。いかに人のつながりを作り、維持していく仕掛けを社会に埋め込んでいくかが課題となる
8.長寿社会のまちづくり コミュニティで社会実験
東京大学高齢社会総合研究機構では、新しいインフラ作りを目指して長寿社会のニーズに対応するまちづくりの社会実験を2つのコミュニティで行っている。医療・介護の問題、住宅とか移動手段の問題、退職してもまだ元気がある人たちに社会の支え手になってもらう仕組みづくり、あるいはICTをいかに上手く張り巡らし活用するかなどの課題を考えるプロジェクトをいくつか立ち上げた。社会実験なので、個人の体の健康、認知能力あるいは社会との繋がりなど、個人のQOL(Quality of Life)がどのように変化したか、街が住みやすいまちになったのか、資本をどれだけ投入して地域の税収がどれだけ上がったか、医療や介護の費用がどれだけ抑制できたか、地域の経済がどれぐらい活性化したかなどコストの面からも評価を進めている。
フィールドとしては首都圏のごく平均的なまちと地方のごく平均的なまちを選び、千葉県の柏市と福井市の2箇所で社会実験を実施している。大学だけでは出来ないので産業界、自治体、市民と連携して進めている。うまくいけばモデルを作り、それを参考にして全国に展開してもらうよう提言、情報発信していくことにしている。
コミュニティにおける社会実験の実例 柏市豊四季団地
- 豊四季団地を選んだ理由
柏市は東京都のベッドタウンで、高度成長期の住宅難のとき開発された。現在40万人の都市。 常磐線柏駅から徒歩20分ぐらいの所に豊四季団地というUR(都市再生機構)が開発した団地がある。建物が老朽化、住民も40%近くが高齢化している。2030年の日本の高齢化率に匹敵することと、4期にわたり建物立替工事が進められ、住宅問題に関与できることから選定した。 - 健康を考えた医療・介護システム
新しい建物は10階ないし14階建て、エレベーター付バリアフリー、床暖房の高層団地となる。空き地が出来るので、そこを利用して長寿社会対応の仕組みを埋め込んでいこうとしている。例えば健康問題に関連する医療・介護に対応するため、まちの中心に24時間対応の在宅ケアの拠点を作る。かかりつけ医師を配置し、24時間対応の訪問看護や介護のステーション、訪問リハビリ、訪問歯科の拠点とする。 - コミュニティ食堂の設置
コミュニティ食堂を設け、高齢者の働き場とすると同時に、2030年には半数を占めると予測されている1人暮らしの高齢者や忙しい若い人たちの食を支え、コミュニティのダイニングルームとして人の絆づくりの場となることを目的とする。 - セカンドライフの就労の場を創出
東京の典型的なベッドタウンである柏市には毎年4000名の市民が定年退職して戻ってくる。60代で定年を迎えた人は、元気で知識や技術があり職場のネットワークを持っている。何かをやりたいと思うが、何をやったらいいか分からない人がほとんど。終日、家でテレビを観て時々散歩にいくような生活をしていると、筋肉も脳も衰えていく。そこで健康長寿の延伸を目指して、セカンドライフの就労プロジェクトに取り組んでいる。歩いて、あるいは自転車で行ける距離に働く場をいろいろ創っている。どのような仕事場を創れるかは、そのまちにどのような資源があるかによるが、柏の場合、休耕地を利用した都市型農業事業、団地敷地内を利用したミニ野菜工場事業、団地屋上農園事業そしてコミュニティ食堂、移動販売・配食サービス、保育・子育て支援事業、生活支援・生活充実事業を進めている。安定した雇用を保証するためには、採算を取って事業を運営していくことが重要なので、事業主は原則として企業にお願いしている。このプロジェクトに参加している事業主は長寿社会のニーズに応える新しいビジネスモデルの開発を試みようとしている。 - セカンドライフの新しい働き方
事業の担い手と就労者が協働し、セカンドライフにふさわしい働き方の開発・普及を担う「オフィスセブン」を設立。事業統括組織としてジョブマッチング、スケジューリングなどを行い、ワークシェアリングを徹底する。市民を対象とした「就労セミナー」を開催し、すでに約400名が終了している。またフレキシブルな働き方を支援するためIT関連企業の協力を得てクラウドコンピューターシステムを用いたソフトの開発を行っている。 - セカンドライフ就労の効果測定
政策の提言をするため、高齢者本人と地域社会の両者への複線的な効果を測定・検証している。就労前と就労後6ヶ月、1年の身体機能・認知機能・社会との繋がりなどを科学的に計測することを続けている。 ・地域における循環型住宅 多くの後期高齢者が望むことは、住み慣れた所で普通の生活が出来ること。人生90年時代には住み慣れた所でステージのニーズに応じて住み替えていくことが必要ではないかと考え、地域における循環型住宅の実験を行っている。 - ICTを活用して安心と繋がりを
在宅医療システムの拠点を設けること、様々なレベルにおける移動手段のニーズに対応できるシステム作り、健康管理・遠隔医療・安心システム・コミュニケーションなど様々な場面でICTを活用することの埋め込みを進めている。 - マルチ・ステークホールダーの協働
このプロジェクトは大学だけではとても行えるものではなく、大学、自治体の柏市役所、関心を寄せている産業界、市民などマルチ・ステークホールダーが、このようなまちを作りたいという夢を共有してそれぞれの立場から協力し合いながら進めている。
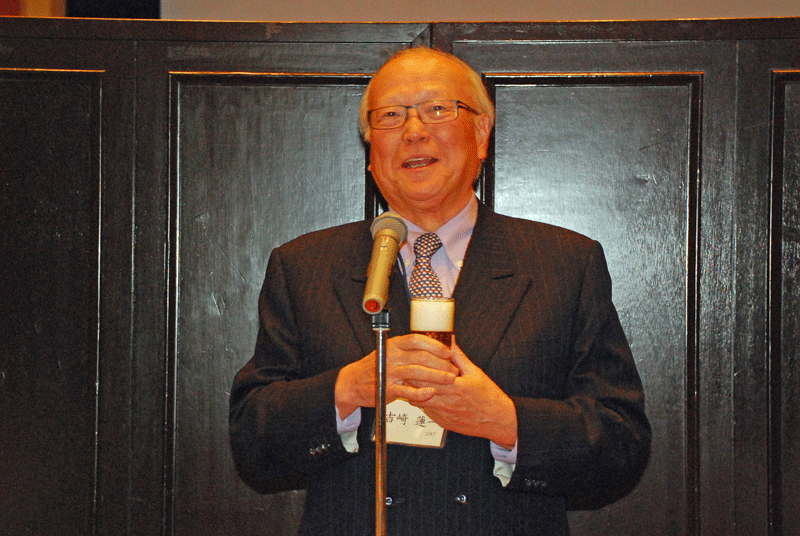 |
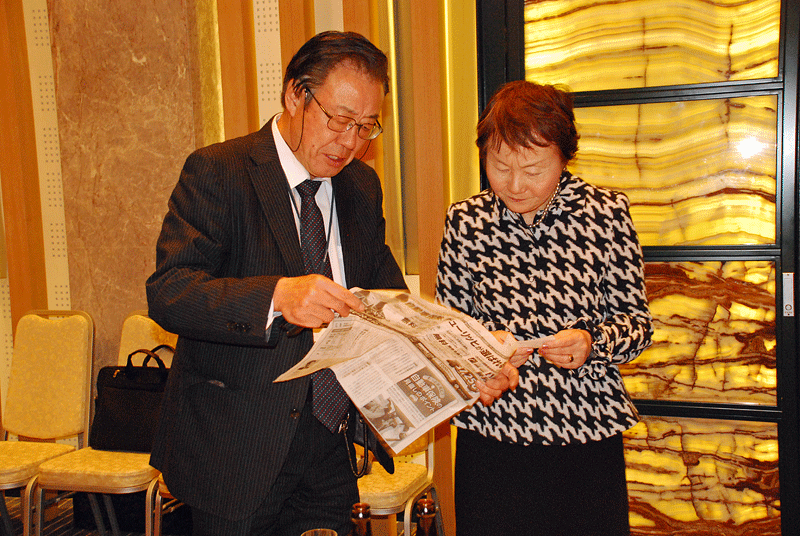 |
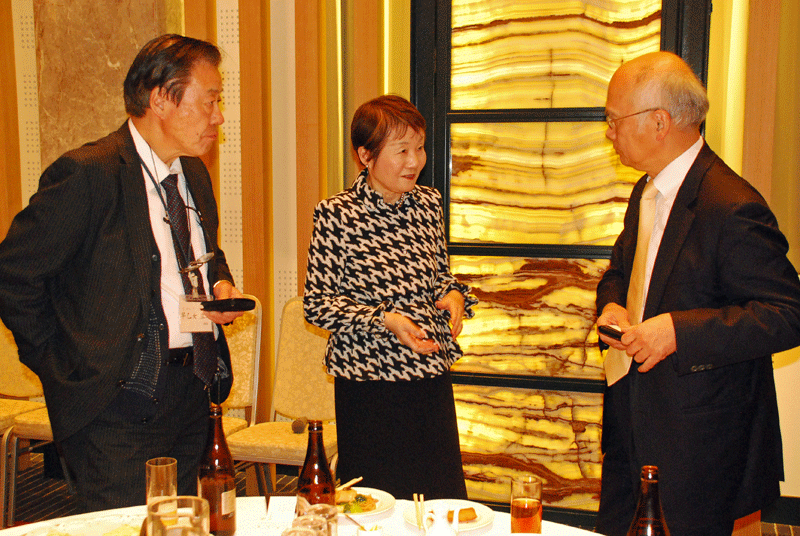 |
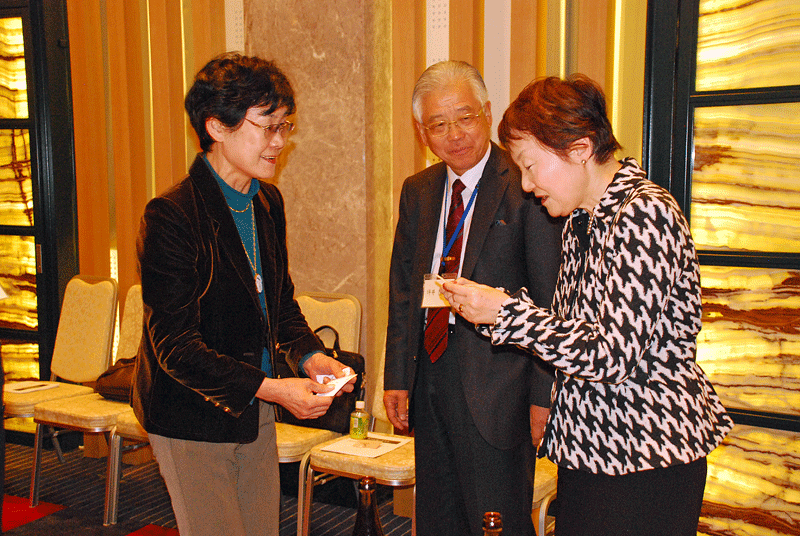 |
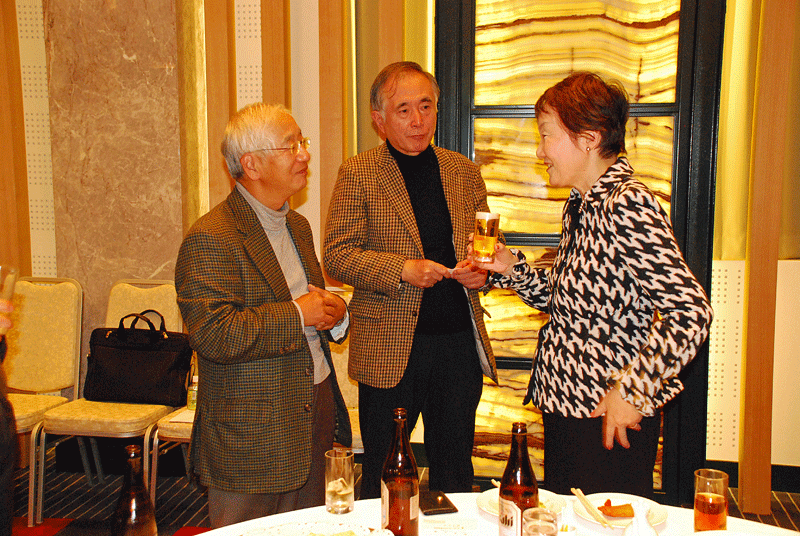 |
DF会員吉崎蓮一氏(秋山先生の紹介者)の乾杯挨拶と先生を囲んで歓談するみなさん |
||||
