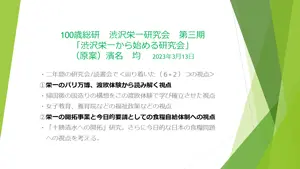渋沢栄一研究分科会 今年度実績と次年度展望
今年度(2022年9月から2023年8月)の実績を中心に、来年度(2023年9月~)への展望を纏めました。
実践
第1期(2021年3月~2022年2月)
研究方法としては渋沢栄一に対する情報レベルをある程度均一にするために、城山三郎の小説『雄気堂々』の読書会形式を採用した。ディスカッション中心の研究会を指向するためにA、B(各8名)の二つのグループを形成して行った。
研究会の内容は発表者のテーマによっても若干の色合いの違いはあったものの、渋沢栄一の足跡にも配慮しながら、各メンバーが一番関心を持った小説「雄気堂々」の中の渋沢栄一の行動に対して、「あなたならどうする?」をテーマにディスカッションを行った。
発表の時間は20分程度で残りの時間90分程度は全員がコメントや自分の考えを披露するというスタイルを執った。
いわば渋沢栄一の「追体験」をしながら各メンバーのそれぞれの人生の自省を行いつつ、主体性のかかわりを問う形式のものであった。研究会座長(リーダー)の隠れたテーマは、学問と行動の一致を目指す陽明学的な態度であった。
第1期に於いては、発表は全てのメンバーに行ってもらった。
第2期(2022年3月~2022年12月)
研究方法は、第1期に引き続き読書会形式を採用した。共通テキストとしては『現代語訳 論語と算盤』を採用した。第1章から第10章まであるが、それぞれの章を発表者のメンバーが選択して、その紹介と自分の考え方を披露してもらった。発表時間は30分以内として、ディスカッションの時間は80分以上を割り当てるという形式であった。
メンバーの中には独自の渋沢栄一の研究を行っている人もいて、その発表という時もあった。第1期同様にA、Bの二つのグループを形成して行った。
第2期の特徴は、渋沢栄一の足跡を調べることよりも、『論語と算盤』(渋沢栄一の講演録の内容・要素が大半である)で主張されている「渋沢栄一の思想やその時代背景」に対する意見交換に重心が移っていった。
世間一般的な渋沢栄一の足跡中心の研究ではなく第1期に引き続き、100歳総研(DF)独自の研究会のスタイルになっていった時期と言える。
第3期:今期(2023年1月~2023年8月)
第1期及び第2期の流れを加速すべく、「渋沢栄一から始める研究会」を新たなスローガンとして掲げている。第1期と第2期の研究発表とディスカッションから出てきた課題を、リーダー(研究会座長)の濱名が纏めてみました。
二年間の研究会/読書会で、<辿り着いた(6+2)つの視点>として纏めています。詳詳細は別紙の(PPT)を参照してください。
但し上記8つのテーマへの研究の取組は一朝一夕にはできないことから、会合形式の研究会としましては第2期の渋沢栄一の思想・哲学が表現されている「論語と算盤」を題材とした読書会形式を引き続き採用しています。各メンバー独自の「渋沢栄一から始める研究会」に資する発表も当然ながら継続・歓迎しています。A、Bグループ分けは当初の目的を達成しましたので廃止して、研究会は一つのグループとしました。
従って各メンバー個人の自己研鑽が中心(前提)となる、上記8つのテーマ絡みの研鑽・研究をお願いしているところです。8月からの来期(第4期)での研究成果の発表へ繋がればと期待しています。
来期の展望
今期に掲げた「渋沢栄一から始める研究会」をサブテーマとした、ディスカッション形式の(会合)研究会を引き続き行っていく。『論語と算盤』の共通テキストは継続します。
それと同時に今期に掲げた8つに分類したのテーマについて、各メンバーが取り組むべき自己研鑽とし、中間発表も含めていずれの時期での発表も期待しています。
例えばメンバーである前DF代表理事の真瀬宏司さんは、「江戸時代の平和な暮らしと江戸集中の人口増大に於ける日本の未来への発見」(真瀬さんからのメールより拝借)を真瀬さん自身の研究テーマに掲げています。これは渋沢翁が尊敬する徳川家康が創設し、江戸260年の平和(パックストクガワーナ)を築き上げたモノに対する、壮大な研究テーマと言い得ると思います。「渋沢栄一から始める研究(会)」のど真ん中のひとつとも言えます。
そしてそれは渋沢栄一が後世の我々に託した「想い」を、少しでも実現していきたいという、本研究会の趣旨にも合致するものと思います。各メンバーの興味と研究へのトライは8つのカテゴリーのどこかにプロットできるはずですので、お互いに応援を送りながらの1年間にしていきたいと思います。