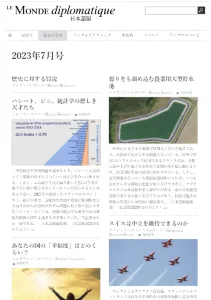『Le Monde diplomatique(ル・モンド・ディプロマティーク)』というフランスの月刊紙(通称Diplo:ディプロ)があります。「立ち止まって考える」(on s’arrête, on réfléchit)をモットーに、世界中の出来事を報じています。1954年に、日刊紙『ル・モンド』を発行しているル・モンド社によって創刊されたのでその名を冠していますが、記事も執筆者・編集部も『ル・モンド』とは関係がありません。株主は、ル・モンド社(51%)とディプロの従業員組織と購読者友の会(合計49%)で、独立性を確保するのにふさわしい構成になっています。当初は外交専門誌として作られた経緯から『ディプロマティーク』と称していますが、今や広く一般読者向けの、「世界を読む」ための国際評論紙です。世界各地の政治、経済、社会、文化、芸術、環境などの問題に主流メディアが報じないような視点から光を当てています。商業広告に拠らず専ら紙媒体の販売とデジタル版を含めた定期購読料で運営される「独立メディア」として、権力に対して厳しい監視の眼をむける視点、鋭い分析、情報内容の厳格さには定評があります。
https://www.monde-diplomatique.fr/2023/07/から紙面をご覧下さい。
もっと充実させたい「日本語版」
このフランス語版本紙『ディプロ』のほかに国際版のネットワークがあり、私が翻訳メンバーになっている『ディプロ日本語版』もその一つです。https://jp.mondediplo.com/ からサイトをご覧ください。トップページ上部の「ディプロについてhttps://jp.mondediplo.com/apropos」には国際版ネットワークについて簡単な説明があります。「ディプロ日本語版」は有料サイトなので購読者でない方は記事の書き出しの部分にしかアクセスできませんが、どんな記事が掲載されているかイメージがわかると思います。Diplo社とのライセンス契約に基づいて、毎月6~8件の翻訳記事を掲載しています。20本を超える本紙『ディプロ』の記事のうち、「日本語版」ではまだ一部しか翻訳できていません。組織の役員をはじめ翻訳者全員がボランティアで運営しています。翻訳チームには私のようにリタイアして比較的自由に時間を割ける者も若干名いますが、多くは現役で仕事を持っている人たちで、その合間に翻訳に参加してくれています。購読者を増やして財政的な余裕を得て翻訳チームの陣容を拡充し、より多くの記事を翻訳できることを目指しています。
月額500円で購読できます(半年プランや1年プランもあります)。まずは、月額プランでお試しいただくことをお勧めします。
日進月歩の翻訳プロセス
私が5年前に翻訳チームに参加した頃は、翻訳者が原稿をワードに落として、チェック担当者にメールで届けて、コメントをメールで貰い、修正を加えるという手間のかかるやり方をとっていました。しかしその後、「グーグル・ドキュメント」ソフトを使って、ここに原稿をアップロードしてファイルにアクセスできる人を指名すれば、その画面上にいつでもコメントを書き込めて、他のメンバーもその画面をリアルタイムで共有できます。翻訳/チェック/修正のプロセスが格段にスムースになりました。
また、月に一度、誰がどの記事を翻訳しチェックを担当するかを決める編集会議は、従来は都内で場を開いて行っていたので遠方の人たちは参加できませんでした。しかしこれも、コロナ禍以降はZoomのミーティングになったので遠隔地の人や海外在住の人たち(パリ、ブリュッセル、ニューヨーク)もリアルタイムで参加できるようになりました。
もう一つ、大いに恩恵に浴しているのがインターネットの検索機能です。世界各地の記事なので、地名・人名の読み方、事件や出来事の経緯・背景など知らないことがたくさんあります。「日本語版」は早くも1996年に発足していますが、インターネット検索が今ほど便利ではなかっただろうと思うと、先人たちの苦労が偲ばれます。辞書一つをとっても、もうさすがに紙の辞書は使いませんが、電子辞書でも各分野の最新の専門用語や口語表現は載っていません。ここでも、インターネット検索の世話になるわけです。
AIが翻訳する日
間違いなく今後は、AIによる翻訳機能の活用が登場してきます。「翻訳」の起案はAIに任せて、人間は「チェック」「コメント」にもっと時間を割くことができる日が来れば、もっとたくさんの翻訳記事をタイムリーにお届けできるようになります。
複眼の大切さ
未だに不思議なことは、何年経験しても自分一人では翻訳が完結しないことです。相当に自信のある原稿も、チェッカーから少なからぬ指摘を受けるのが常で、しかもそのチェッカーは翻訳技能の高い人とは限りません。翻訳者は気がつかないことも、第三者が見れば間違いや表現のまずさが見つかるのです。思い込みとは恐ろしいものです。チェッカーの指摘を踏まえた修正原稿を、今度は翻訳チーム全員の眼に晒す「公開コメント」のプロセスでも、やはり、いくつも指摘を受けます。さらに、最終的に組織役員による審査の段階でも指摘が出ます。さすがにこの段階では間違いの指摘というより、表現上のニュアンスを巡るものがほとんどですが。とにかく、「独りよがり」は本人の知らないところで生じるものだと思い知らされます。いい勉強になります。
最後に
重ねて、プロモーションをさせていただきます。月額500円で購読できます(半年プランや1年プランもあります)ので、まずは購読をしてみてください。そのうえで、お気付きのことなどございましたら、なんなりとお知らせいただけるとありがたいです。
しょうの ゆういち (1134)
(理科実験グループ)
(元東京三菱銀行)