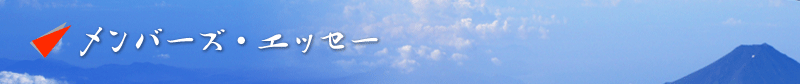
- メンバーズ・エッセー
- 「目 次」
2016/07/16(No225)
酵母の不思議
市川誠一郎

欧米人のみならず、私ども日本人を含め、アジア人にとっては、発酵は日常生活とは関連が深い。特に発酵食品については、古来、漬物や味噌、醤油は保存食や調味料として生活必需品としてなじみが深い。とりわけ、醸造酒類は発酵なくして成立しない古くからの致酔飲料である。発酵には乳酸菌、酢酸菌、酵母や麹菌が関係しているが、私の経験してきた職務はこのうちの酵母を利用したアルコール発酵である。基本的には、糖➡エチルアルコール+炭酸ガスであるが、この反応は酸素のない条件で酵母がエネルギーであるATPを生成する連鎖酵素反応である。
本来ならば酸素の存在下で糖を分解した方が大きいエネルギーを生むことができるが、酸素のない状態でも生存するためのエネルギー獲得方法を産み出したのだろう。ところで、ヒトの個体は約60兆個の細胞で構成され、個々の細胞には32000個の遺伝子があるが、酵母は5〜10μの単細胞ながら、実に12000個もあるようだ。これはワイン酵母とパン酵母が合体してできた細胞で、実際には6000個なのだが、細胞の合体によって2倍になったようで、いろいろな条件に適応できる能力を備えているようだ。実際、通常の発酵条件とは異なる条件でも必要とするエネルギーを生産する遺伝子を発現させることができる「万能性」を持っている。
アルコール発酵で生成するエタノールはこれを利用するヒトにとっては妙薬であるが、実はこれは酵母が利用した残渣でもある。つまり、我々は酵母の老廃物を有難く戴いていることになる。酵母は子孫を残すためには増殖しなければならないが、この際にはアミノ酸が必要となってくる。酵母が糖類を含む液体に接してもいきなり発酵が開始されるわけではなく、まず酸素によるステロール合成とアミノ酸を取り込んだ増殖が始まり、十分な増殖を経てのちに発酵が始まる。ビール醸造工程では酸素は大敵だが、この増殖の初期のみ酸素は重要である。酒類の原料には、穀類が多いが、これには糖類の基であるでんぷんやアミノ酸の原料であるたんぱく質が含まれている。
 |
 |
従って、穀類の酒は健全な発酵を経て生成されるが、ワインの原料であるぶどうには糖類は豊富だがアミノ酸は貧弱なので、アミノ酸を補強する必要がある。実は、アミノ酸が十分でないと増殖だけでなく、アミノ酸発酵の代謝産物である多様なフレーバーも少なくなるばかりか、硫化物の生成が多くなる傾向がある。穀類の使用比率が少ない発泡酒や麦芽を使わない第3のビール類も同様で、通常の酒類とは異なる香りが生成しやすい。
ところが、面白いことに、何度も貧栄養の条件で発酵を繰り返すと、次第に酵母もその環境に適応するようで、香り成分も次第に正常化してくることがある。これは恐らく、遠い過去の記憶がゲノムとして残っていて、厳しい条件に適応できるよう、遺伝子が発現して酵素反応が制御されているのではないかと推察している。酵母には大変迷惑なことだと思うし、可哀想な話だ。
醸造技術者は酵母を非常に大切にしていて、できるだけ酵母には「気持ちよく」働いてもらえる環境を提供するか、コントロールするのが醸造技術者の仕事だ。日本では独特の酒税法により、使用できる原料がかなり制限されているし、原料使用率で税率も大きく異なる特殊な国だが、ここは知恵を絞って如何に法的要求事項と酵母の健全性を保ち、かつ安価に供給できるかが重要なポイントになる。しかし、いずれにしても酵母を適切にコントロールすることの重要性には変わりはない。長く酵母と付き合っているとヒトと似たような反応が見られて愛着の湧く実に面白い生物でもある。![]()
いちかわ せいいちろう ディレクトフォース会員(1106)元 サッポロビール
