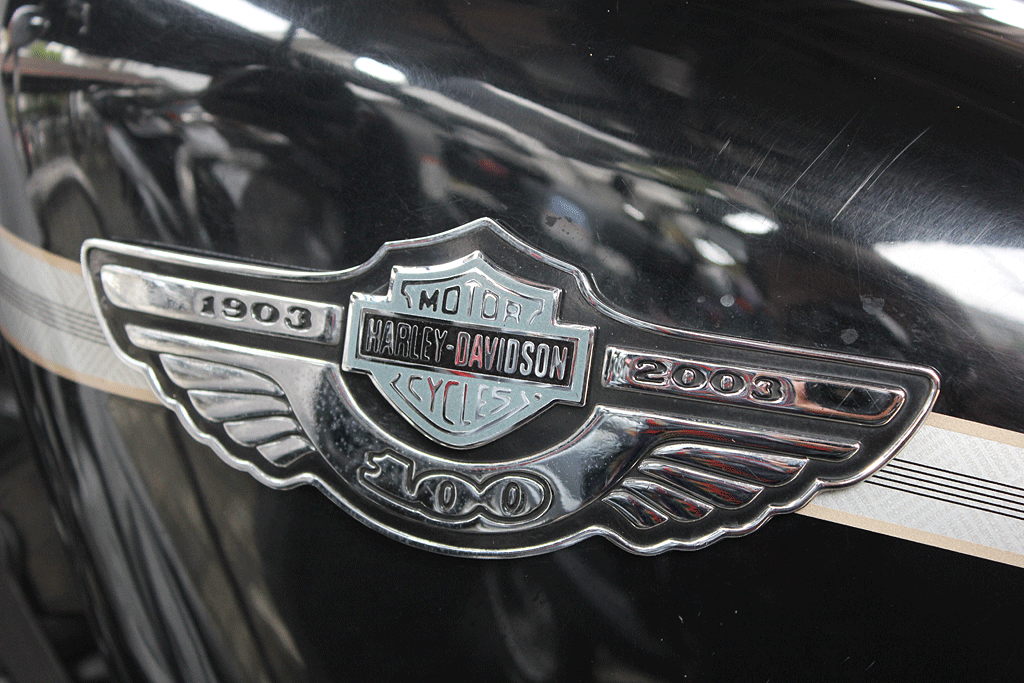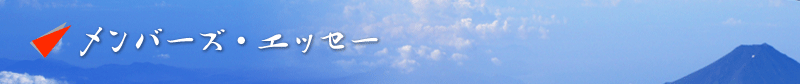
- メンバーズ・エッセー
- 「目 次」
2013/12/16(No163)
還暦の挑戦「ハーレーライダーを目指して」
宮本 昌幸
 小さい時から模型飛行機、鉄道など乗り物好きで、大学では自動車部で活動し、就職では鉄道車両を一生の仕事に選び、仕事優先の日々が続いていた。還暦を迎えるにあたって、捨てがたかった大型バイク免許取得に優先順位を変えて挑戦した。
小さい時から模型飛行機、鉄道など乗り物好きで、大学では自動車部で活動し、就職では鉄道車両を一生の仕事に選び、仕事優先の日々が続いていた。還暦を迎えるにあたって、捨てがたかった大型バイク免許取得に優先順位を変えて挑戦した。
まず最初の仕事は女房の説得であった。「60才にもなるのに何を考えているのだ。生身の体をさらすのだから怪我をする確率は増す。植物人間になったら‥‥」どれも至極正論で説得方法を思案した。ライフワークとしていた安全について日頃思っていた総合的リスク論を使うこととした。「確かに事故に会い怪我をするリスクの確率は増えるだろうが、安全のプロとして運転時には幅広い情報を取得し、安全運転を行うからリスクの増加を抑えられる。また、バイクに乗るために体調維持に努め、筋トレで体力を維持するので、バイク以外の加齢によるリスクを下げることができる。総合的に見れば決してリスクは増加しない」この説得が功を奏したとは思えないが、根負けしたかOKが出た。
59才の11月に自動車学校に通い始めた。20歳前後の若者に交じり、週1回程度となかなか連続して毎日は通えないハンディを克服して、60才の3月に普通2輪の免許取得にこぎつけた。日頃は息子の250ccボルディに乗り、ためしに本田のライディングスクールに行って750ccバイクに乗り、いわれのなき自信を持ち8月に大型2輪免許に挑戦した。教員の説明が力学的には間違っていると思っても、高圧的教え方と思っても封印し、免許を取るまではと従順さをアピールして、最短12回を6回オーバで9月に大型免許を取得できた。その頃は大学教員だったが、「学生は言いたいことも我慢しているのかな」、など久しぶりに学生の立場になって反省する機会になった。
2002年9月10日二俣川試験場で大型2輪の免許証をもらい、ルンルン気分でライディングの本を多数買い込み夜熟読した。次の朝11日、大学へボルディに乗って出かけた。昨夜読んだ攻めのカービングが脳裏に浮かび、交通量の少ない抜け道でバイクを傾斜させ、いつもより高速でカーブに入いった。意に反してバイクは外へ膨らみ前輪がマンホール蓋にかかり、ツルンと滑りバイクは横転。ああ、やってしまったなと、バイクを起こし、曲がったステップを直し、自宅付近のバイク屋さんまで乗っていき、家に戻り4輪で大学に出かけた。ところが夕方になると左ひざが急激に痛くなり歩けなくなってしまった。学生を呼び出し、肩をかりて自動車まで行き、オートマ車で左足を使わなくて良かったので自宅まで運転して帰った。翌朝病院でレントゲンを撮ると、医者が「膝がきれーにスパッと割れている」との宣告。それから3か月の松葉杖生活がスタートした。
2002年9月11日。アメリカ同時多発テロ事件からちょうど1年後、あまりにも出来すぎた話になってしまった。チャレンジをしての失敗だったので、これも財産と思い、めげることはなかった。何事に対しても楽しみを感じられるタイプなので、この3か月は得るものも多かった。
先ず、人間が痛みを感ずるメカニズムの不思議を実感した。膝は転倒時に割れていたにもかかわらず、痛みを感じだしたのは夕方だった。膝部に痛みを感ずるセンサーが無かったか、脳へ伝える経路が無かったか、脳がお取り込み中だったか。この仕組みの探求を楽しんだ。鉄道車両の部品には、私の膝のように故障したとしても痛み情報を発しないものも多い。センサーを車両全体に取り付け、各部品の痛いコール、痛い予兆コールを適切に集約し、メンテナンス時期をきめ細かく決めるという、将来のメンテナンス像を模索したのも思い出す。そのような動きも一部にはあるが、まだ道半ばである。
二つ目は松葉杖での歩行についてである。最も怖いのは前に出した杖の先が地面に着くときに滑り、こけることである。危険そうな状況では慎重に行動するので、それよりも危なかったのは屋内の一見乾いた床を移動する時で、水がほんの少し滴り落ちている所を分からずに杖を突きツルリといくことで、大事には至らなかったが何度かひやりとした。松葉杖にも慣れてきた頃には、見かけの足が長くなった効果を利用した「松葉杖高速歩行の術」をマスターし、通勤の列をごぼう抜きする快感を味わっていた。回復してきて1本松葉杖になった時に、骨折した左か反対の右かどちらに使うか悩んだ。反対の右のほうがリハビリを兼ね適度な荷重を左足にかけるという目的にかなっていることがわかった。その他、骨の再生メカニズムの探求、大学の非バリアフリーマップの作成などをした。ちょうど工事予定の時期だったのだと思うが、その後すぐスロープ化などの工事が行われた。
12月中頃には松葉杖なしの生活に戻り、仕事の合間をぬって大型バイク選びに着手した。ハーレーダビッドソン社製の大排気量空冷OHV、V型ツインエンジンの独特なボンボンボンの鼓動感が魅力であった。しかし主流1500ccのルート66をひたすら東西に真っ直ぐ走るイメージの、ステップが前にあるアメリカンタイプではなく、カーブ走行も楽しめるステップが真下の1200ccスポーツスターSを選んだ。エンジン始動時に暖機運転など手間暇はかかるが愛着の湧くキャブレタータイプで、エンジン振動が直接感じられるエンジンダイレクトマウントの車である。購入した2003モデルはハーレーダビッドソン社創立1903年からの100周年の記念モデルで、タンクには写真のエンブレムが取り付けられている。1903年は米国での乗物に関して他にも二つの大きな出来事があった。一つはフォード・モーター・カンパニーの設立、他の一つはライド兄弟の人類初の動力飛行成功である。その後の航空機の進歩の速さに驚かされる。
| 颯爽としてライディングを楽しむ筆者 | 2003モデルのエンブレム |
ハーレーダビッドソン社では、映画「イージー・ライダー」に象徴される暴走族、無法者のアウトローのイメージからの脱皮を、家族、女性にも受け入れられるソフト路線への転換を行うことで、図ってきた。購入までに何度も通った販売店は女性も入りやすいアパレルのショールームのようなおしゃれな装いだった。日本で二輪市場全体が縮小する中、ハーレーは2001年には日本メーカーを抑え750cc超の大型二輪シェア首位を獲得した。大型自動二輪車免許が自動車教習所で取得可能とする制度改正への働きかけの努力も大きかったと思う。運転免許試験場で10回も実技試験を受けないと受からないと言われた前の制度では、あきらめていたと思う。
ハーレー1200Sに乗り始めマイペースでライディングを楽しみ11年目となった。大学ではバイクの話題が学生との距離を縮めるのに大いに役立ち、最終講義後のパーティで学生達からツーリング用の革ジャンパーを贈られた時はウルウルしてしまった。幸いにも膝骨折以降は怪我もせず「今日も元気だバイクに乗れる」と健康のバロメータとなっている。![]()
みやもとまさゆきディレクトフォース会員(会員No972)
明星大学名誉教授 工博 機械学会名誉員元 国鉄技術研究所
(財)鉄道総合技術研究所 明星大学 運輸安全委員会委員