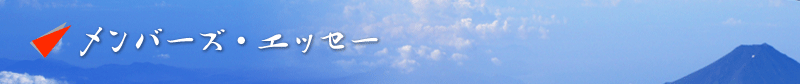
- メンバーズ・エッセー
- 「目 次」
2013/10/16(No159)
ドイツ語(文法)を学ぶという「趣味」
小西 敏夫
 3年半前、ドイツ語の学習を再開した。会話ではなく、主として文法。40数年ぶり。学生の頃からドイツが、そしてドイツ語が好きだった。「何故?」と問われても困るのだが…。
3年半前、ドイツ語の学習を再開した。会話ではなく、主として文法。40数年ぶり。学生の頃からドイツが、そしてドイツ語が好きだった。「何故?」と問われても困るのだが…。
高校時代「ドイツ語」という自由選択科目があり、興味本位で始めた。「専攻はサッカー部」(実際は経済学部)と言いたくなるようなサッカー漬けだった大学生活の中でも、ドイツ語だけはわりとまじめに受講していたし、サッカーの練習で疲れ切ったあとに、語学学校に通っていた時期もあった。大学3年の時には当時としては大変珍しかった西ドイツとの交換学生制度で、夏の3ヶ月間南ドイツの小さな町に滞在していたこともあった。社会人になってからは、希望はしたが、ドイツ駐在は適わなかった。ニューヨークとロンドンに駐在。外国語と言えば英語ばかりの毎日。ドイツ語とは縁遠かった40数年のサラリーマン生活を終え、自由になる時間が増え、ドイツ語の学習を再開。今さらビジネスではもちろん、観光旅行ででもドイツ語を話してみたいという気があるわけでもなく、ただただドイツ語を「趣味として」「学んで」みたかった。何故?
私は「外国語を話す」というよりも「語学を学ぶ」のが好き。「趣味」にいちいち理由は不要だと思うが、英語と比べても発音の決まりや、語順や文法体系がキッチリしているという意味でドイツ語が好きなのだと思う。これは良く言えば几帳面、裏返せば杓子定規で融通の利かない、私自身の性格に拠るところが多いと思っている(あまり、好ましい性格とは思えないが…)。英語は、しっかりとした文法規則がそれほど多くなく、かつ例外だらけで、基本的にはいい意味で融通無碍(ゆうずうむげ)。発音にしても、よく引き合いに出される例だが daughter(娘)は「ドーター」で、laughter(笑い)は「ラーフター」と読む。あるいは read(読む)の現在形は「リード」、過去・過去分詞は「レッド」と発音するということに関しては何の理屈もない。英国の Leicester という町を「レスター」と発音せよ(明らかに字余り)というような無理難題例も沢山ある。
その点ドイツ語の読み方にはいくつかのルールはもちろんあるが、外来語を除いて例外はほぼ皆無。ルールさえ覚えれば読みは完璧に出来る(アクセント、イントネーションは別として)。こういう点が、私のような性格の人間には大変「心地よい」。文法も英語に比べて遥かに多くのルールが存在するが、一つ一つのルールに例外が少なく、一生懸命学び、難解な文章を読み解いていく過程は、規律正しく秩序立って動いている社会みたいに「気持ちがいい」。もっとも「そんな社会は窮屈でいやだ、もっと雑駁でもザワザワした社会の方が楽しい」という人も多いのも良くわかる。これも好き嫌い、趣味の問題だから。ドイツ語を学び始めて、最初に多くの人が挫折するのが「形容詞の語尾変化」だが、これが私にとっては文法の一番好きな部分なのだから、やはり随分変わった性格・嗜好なのだと自分でも思う。学生時代の滞独時、ドイツ人の友人から、「お前はドイツ語の語彙も少ないし、不正確な表現も多いのに、名詞の格変化と形容詞の語尾変化が完璧なのは驚異的だ」と言われたこともあった。今でも独作文では、先生から「ドイツ人より硬いドイツ語ですね!」と言われる。このような「正確さ至上主義」は語学の、とくに会話の上達の足かせになるとよく言われるし、全くその通りだと思う。私は妙に臆病なところがあり、「間違った言葉を話したくない」という変な完璧主義が上達を阻んでいるのは実感としてよくわかる。ここ数年の学習で、文法のレベルは相当上がったと自負はあるが、「では話せるか?」というと全く自信がない(一昨年、思い切ってチャレンジしたドイツ語検定2級は無事合格出来たのだが、これは筆記試験)。
語学学校で「学ぶ」のとは別に、日独協会での「ドイツ語でニュースを読む会」という催しにも参加している。先生は居らず、大学の独文科の女子学生から昔ドイツに住んでいたおじいさんまで10数名が集まって、みんなで新聞・雑誌の記事を読み進んでいく。ニュースの内容に関するディスカッションももちろんあるが、「この関係代名詞の先行詞は何か?」「ここはなぜ接続法第2式なのか?」などといった純文法上の疑問を皆で解き明かして行く過程で、この年になっての自分の「成長」を感じられるのは、これはこれで、なかなか楽しいものである。 (他の方には、なかなか理解して頂けないかもしれませんが、「趣味」の話ですから仕方ないですよね!)![]()
こにしとしお ディレクトフォース会員(No968)元伊藤忠商事 センチュリーメディカル 伊藤忠記念財団
