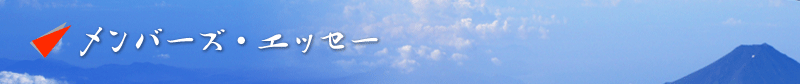
- メンバーズ・エッセー
- 「目 次」
2013/04/01(No146)
「事業再生に新たな枠組みを」
 日本の事業再生能力が再び問われている。この3月末に金融円滑化法が期限切れとなり、これまで経営不振で借入返済を猶予してもらった40万社の中小企業の事業再生を促進させることが急務となってきたからである。
日本の事業再生能力が再び問われている。この3月末に金融円滑化法が期限切れとなり、これまで経営不振で借入返済を猶予してもらった40万社の中小企業の事業再生を促進させることが急務となってきたからである。
国の事業再生=「病院機能」はバブル崩壊後の平成15年頃に銀行の不良債権早期処理を目的として大幅に強化された。当時、整理回収機構・産業再生機構を「病院」として国が資金や人材を投入することで、多くの金融機関や多重債務を抱えた事業会社を復活させることに成功した。「病」は資産バブルの後遺症で、膨張した資産が不稼働になったところにデフレの直撃を受けたためB/Sが債務超過に陥る「急性心不全」であった。
このための処置は不採算事業を整理して出血を止める一方、顕在化した赤字部分の債務の一部を銀行が債権カットに応じることで債務超過を解消する「外科治療」がメインであった。当時はまだ本業は競争力があり、回復力も具備していたが故に出来た手術であった。
ところがリーマンショック以降に発生した「病」は、肝心の本業が度を越えた円高により価格競争力を失って衰弱する深刻なものである。多くの下請け企業を抱える製造業大手にとっても、輸出から海外でのモノつくりに切り替えざるを得なくなった。この結果、取り残された下請中小企業は受注減に加えて割安な輸入部品の国内参入に直面して、にっちもさっちもいかぬ病に苦しんでいる。この「病」を克服するのに、金融を中心とした従来の医療体制だけではまったく迫力不足である。まず円の為替水準を他国並みに引き下げ、中国・韓国等との価格面のハンデを解消し、製品の内容で勝負できるようにすることが急務である。
今一つは事業の抜本的見直しである。今後も成長が見込めるグローバル市場で自らの強みを活かして売れる製品作りに挑戦することしか術はない。その際、再生の糸口を見つけシードとニーズを結びつける知恵者の存在が不可欠となるが、中小企業はこの部分が全く弱い。そこでこれまで第一線で活躍し、技術・経験・人的ネットワークが豊富な中堅・大企業の目利きOBを人材ファンド的に組織化し、事業に即した適材を再生現場に派遣、悩める経営者に持てる暗黙知を伝授するような支援の枠組みを構築することが、いま国に求められているのではなかろうか。任意団体ではあるが、ディレクトフォースは正しくこの主旨に適った組織であると思う。![]()
やまかわゆきお デイレクトフォース会員(会員番号911)
元・東京三菱銀行、ダイヤモンド信用保証、整理回収機構、西武鉄道 現・小野測器、百五銀行
